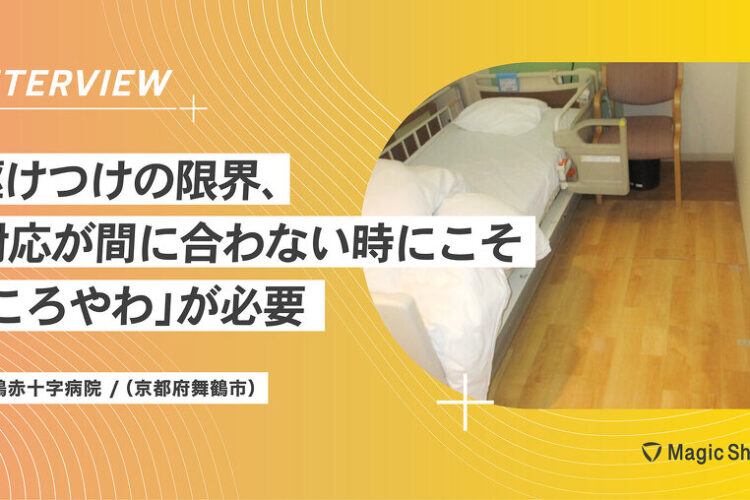目次
社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院(以下、済生会千里病院)の緩和ケア病棟開設に伴い、ころやわフロアが導入されました。

背景
緩和ケア病棟開設に伴い、全病室、トイレ、脱衣所へころやわフロアが導入されました。2025年6月1日の緩和ケア病棟としてのスタートに先立って2025年4月1日より急性期病棟としての稼働が開始しております。


導入経緯インタビュー
◆大嵩ゆき様(がん性疼痛看護認定看護師)
ころやわフロアを設置した病室を見て、どんな印象を受けましたか?

最初の印象として、見た目が木目調であることですごく柔らかい印象を受けました。転倒時の衝撃を吸収するかどうか以前に病室の雰囲気が柔らかくなるというか明るくなった印象を受けました。一般的に病室って、なんとなく無機質なイメージがあって、こういう木目調だと、雰囲気が柔らかいイメージになるので緩和ケア病棟には合っているなと感じました。
患者さんの転倒・転落について、これまでどんな経験がありますか?
私は前職の病院でも緩和ケア病棟の配属だったので、やはりADLがどんどん下がってくる患者さんが、自分ではできるって思って、トイレ行こうとされたり、最後まで自分でしたいという気持ちが強い中で、ナースコールで呼んでくださいねって声をかけていても、なかなか呼んでくださらなくて、結局ひとりで歩いて転んでしまうっていうことをよく経験しました。
特にせん妄の時は大変で、どうしても防ぎきれない転倒があると感じます。転びそうになったところを抱きかかえたこともありますし、ラウンドで回った時に床に横たわっている場面に遭遇することも少なくありませんでした。
今回、緩和ケア病棟のオープンにあたり、ころやわフロアがあることでどんなことが期待できますか?
転倒は避けられないことだと思います。これまでの対策として、緩衝マットが用いられることが多かったですが、緩衝マットだといかにも転落対策しているって感じがしますが、ころやわフロアだと同じような衝撃吸収性があるにも関わらず、見た目がすごいスッキリしてることが看護師としては嬉しいです。
今後、入院される患者さん、ご家族さんとの関わりも非常に深い関わりがあるとは思うのですが、ご家族目線での安心感にもつながるとお考えでしょうか。
以前勤めていた緩和ケア病棟では、緩衝マットがあるがゆえにご家族がベッドに近づきにくかったたので、ご家族が来院された際に緩衝マットを移動させていました。その必要がなくなるのが良いと思います。あとはやはり見た目ですね。緩衝マットがあると空間として生活感がなくなってしまい、落ち着かない感じですが、ころやわは自然な見た目でとても良いです。
今後は、入院時の説明でご家族にもころやわフロアについてお伝えすることになっているので、安心していただけると思っています。転倒転落は100%を防ぐことは難しいですが、転倒してしまった場合でも怪我が最小限に抑えられるっていう説明はご家族にとっても安心感にはつながると思います。
◆福﨑孝幸様(医師/副院長/がん総合診療センター長)
今回の緩和ケア病棟の新設ではどんなことを大切にされましたか?
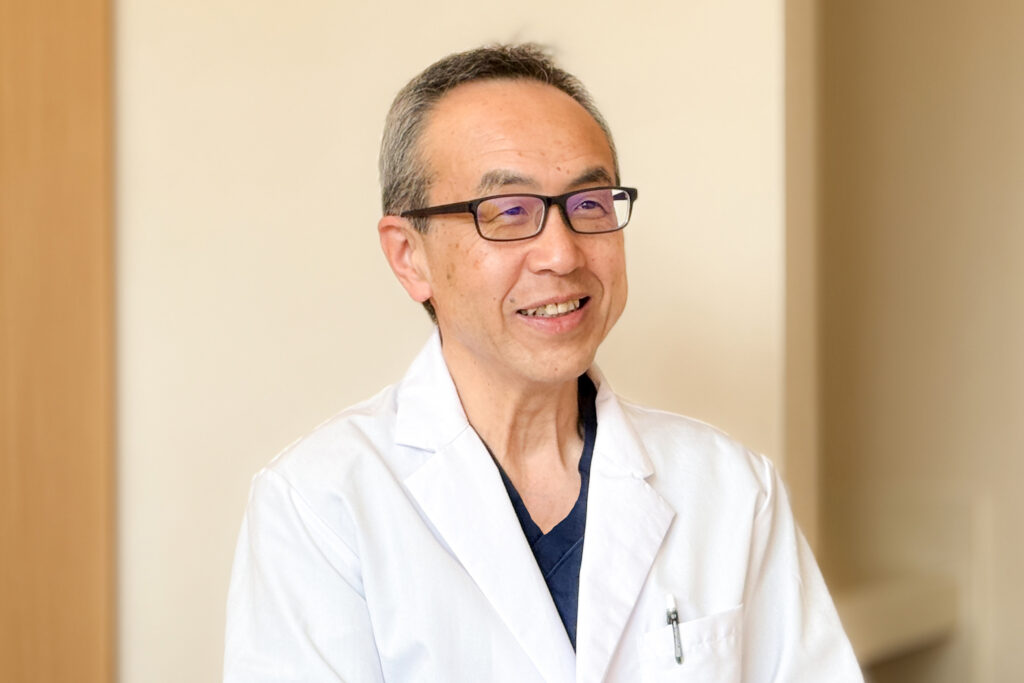
当院は、がん診療拠点病院なので、がん患者の診療を積極的に介入するのですが、その経過の中で病状が進行して、いわゆる終末期の状況で入院が長引く時には、従来では在宅もしくはホスピスへの退院となり、患者さんとの関係がそこでプツンと切れてしまうという状況でした。
私は緩和ケアも治療の一環だと思っています。昨今のがん診療というのは、診断から終末期というのが時点の流れなので、ケアも一連の治療の一環です。その状況で私たちが全く手を離してしまうという状況が起こっていたので、診療にあたる医師たちも不完全燃焼の状況でした。がんの診断からがん診療、緩和と進んでいく、それを全うしたいという意味で、緩和ケア病棟の新設を決めました。
ころやわフロアという製品を知った最初の印象はいかがでしたでしょうか?
正直に言うと、サンプルを触った印象は「硬いな〜、本当に大丈夫なのかな。」と思いました。どのぐらい骨折が予防できるのか疑問はありました。私は医療安全も担当してきたので、医療安全では転倒骨折が非常に大きな課題で、病棟から年間何件も報告が上がってきていました。だから、骨折を減らすための手立てはないのか、行動を制限するのではなく、実現できないかと考えていました。世間的にも抑制をしてはならないという状況なので、患者さんの行動を制限せずに骨折を減らせるものはないのか常々考えてました。
そんな中、ころやわのサンプルを体験しました。歩く時に違和感がなかったですね。もっと柔らかいクッションだとふわふわして、バランスを崩して、余計に転倒リスクも上がりますが、それはないことがすぐにわかりました。ただ、実際に自分が膝をついてみて、衝撃吸収性が本当に骨折予防になるかどうかまでは実感できませんでした。骨折予防効果は今後検証していくものだと思っています。緩和ケア病棟での効果検証が上手くいけば、他の病棟への導入も考慮したいとは考えています。本当に転倒骨折対策は難しいので。
6月から緩和ケア病棟としての稼働がスタートですが、ころやわがどのような価値を提供できるとお考えでしょうか。
緩和ケア病棟の入院生活は、日常の延長線上だとを基本には考えています。そういった意味で、ベッド上でじっとしてもらうのではなく、病室内、病棟内を歩いていただける環境はしっかり提供できる思います。だからこそ、一部の病室だけではなく全病室に入れさせていただきました。トイレと脱衣所にも入れてもらったのもそういった理由からです。
がん末期の方がもし骨折されると、それを契機に動けなくなって食事も取れなくなります。そうすると、一気に状態が悪くなっていく傾向があります。そのようなことにならず、日常の延長線上でそのまま息を引き取っていただくという形を提供したいです。
◆岩上雄一様(がん総合診療センター副センター長/がん看護専門看護師/がん性疼痛看護認定看護師)

緩和ケア病棟を立ち上げにあたり、どのような環境づくりを目指してきたのか教えてください。
当院は急性期病院としてこれまでやってきたので、緩和ケア病棟は全く違う分野だというのが院内全体の雰囲気としてありました。緩和ケア病棟の運営が本当にできるのかという疑問を払拭していく必要があると思いました。緩和ケア病棟は患者さんとの関わり方が急性期病棟と異なる部分があると思います。ゆっくり過ごしていただくために、自分たちにどんなことができるか、そのような質問をたくさん受けたりもしました。
看護師が安心できる環境というと何なのかなと思ったときに、スタッフから最も言われたのは、何か事故が起きた時の責任をどう取っていくのかということでした。終末期だからこそ一人ひとりに対して丁寧なケアをしたいという気持ちが、事故を極力なくしたいという考えにつながっていると感じました。そのようなやりとりから、最も重要なのは病棟の環境整備によって、いかに看護師の安心を担保できるかということでした。
安心できる環境づくりを進めるとなった上で、どういうプロセスでころやわフロア導入の意思決定されたのかを教えてください。
緩和ケア病棟の中で安心できる環境を考えると、スタッフにとっての安心と患者さんにとっての安心、どちらも大切です。それが両立できるのは、センサーマットや身体拘束、患者さんの行動を制限するという前提がありました。それを少しでも減らせるものを探していました。
ころやわフロアは、転んでも怪我しないという発想の逆転がありました。行動を制限するのではなくて、転倒自体は防ぎきれないと捉え、患者さんのADL、QOLを保とうとする考えに強く共感しました。
看護師の事故に対する不安の中でも具体的に出ていたのが転倒転落の課題で、患者さんが怪我をされるとすごく責任を感じてしまうという意見がありました。そのような声を聞いていく中で、緩和ケア病棟の新設にあたり、ころやわフロアを入れたいという気持ちが生まれました。
ころやわフロアの導入が決まってからの周囲の反応はどうでしたか?
他の病棟のスタッフから緩和ケア病棟だけじゃなくて全病棟に入れてほしいという要望がありました。ころやわフロアがあったら安心して患者さんに自由に動いてもらえるというのは全看護師に共通の認識になっているようでした。工事の日に、資材が搬入されているところを見た他の病棟のスタッフから、羨ましいな〜って言われたのが印象に残っています。
先日行ったオープン前の内覧会では、病棟の環境整備についての近隣の医師から、「患者さんを生活者として支える視点が素晴らしい。地域で患者さんを支えるという意味でとても有意義ですね。」というコメントをいただくことができました。
緩和ケア病棟としてのオープンが6月に控えてますが、実現したいことについて改めてお話いただけますか?
自由な発想でケアをしてほしいというのが一番です。看護師は『転倒させない』という意識が非常に強いので、ころやわフロアによって安全性が高まることで、患者さんの自由な行動を促すケアが期待されます。転倒や転落による怪我に対して責任を感じてしまう看護師も多いので、怪我のリスクが軽減するということは看護師の働きやすさにも寄与すると考えています。
緩和ケア病棟は穏やかに過ごしていただくのが大事ですが、緩和ケア病棟だからこそできるチャレンジで、最期の時間の過ごし方をより広げるチャレンジをしたいです。単に行動制限が減るというだけでなく、患者さんの活動をより積極的にサポートする考え方が緩和ケア病棟におけるケア自体の可能性を広げていくことになると思っています。
お問い合わせは以下よりご連絡ください。
お問い合わせ窓口:https://www.magicshields.co.jp/contact/
TEL:050 – 1742 – 4400(平日/10:00 – 17:00)



施工後写真ベッドあり1.png)