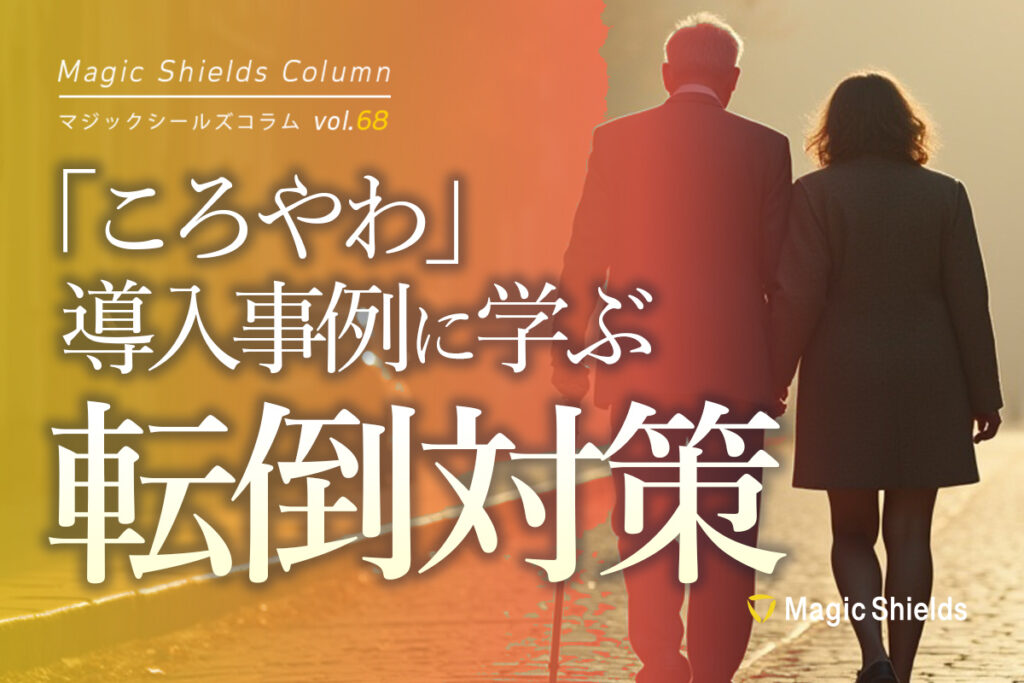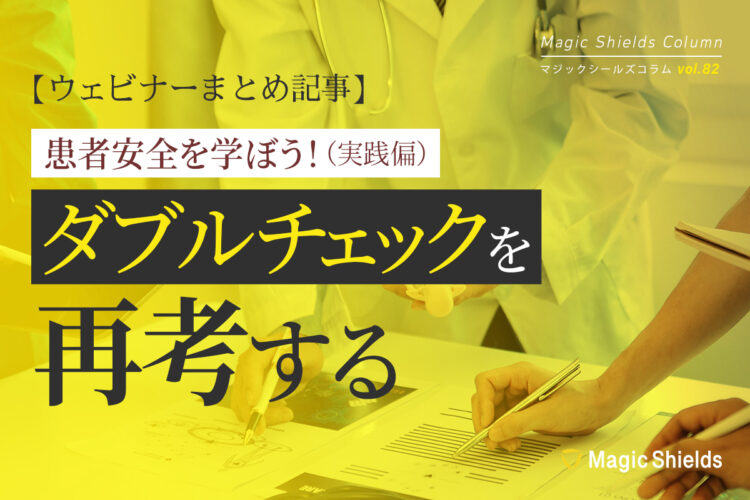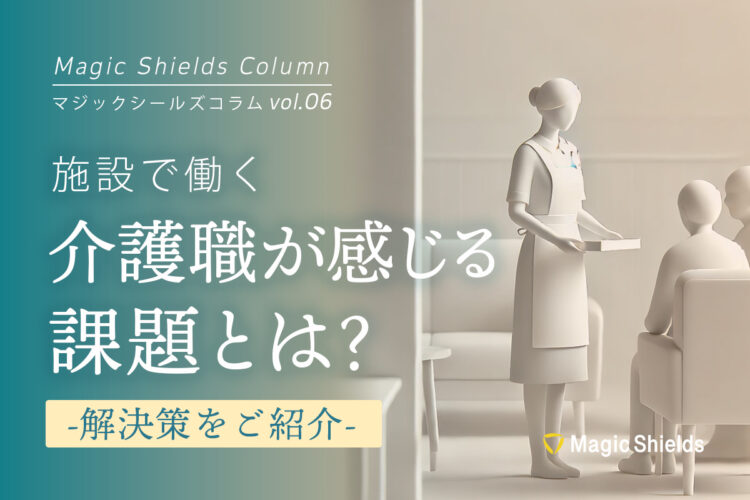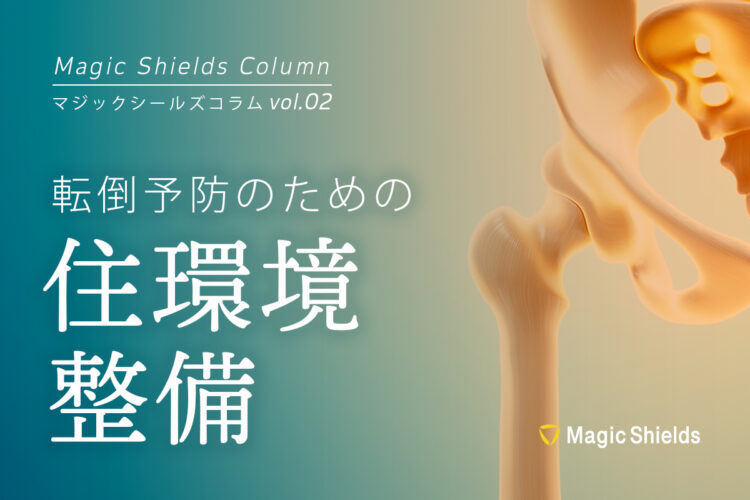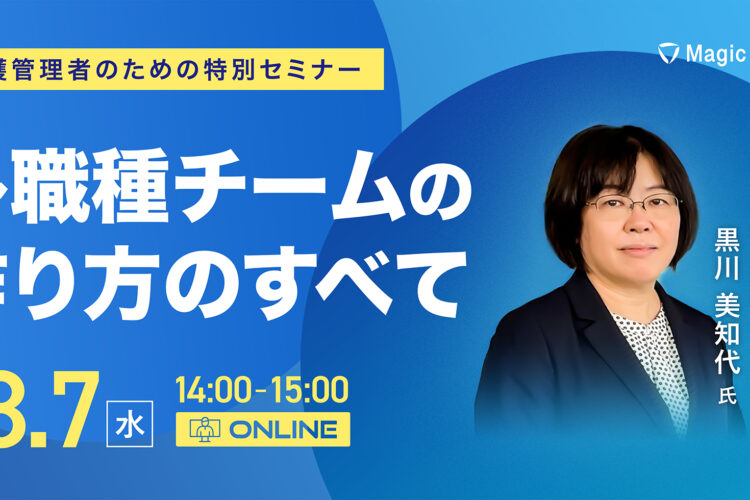目次
・転倒対策に力を入れたい
・「ころやわ」に興味があるが、導入後の変化や詳細をもっと知りたい
上記のように思っている人もいるのではないでしょうか。
今回は、「ころやわ」を導入している病院の担当者様より、実際の導入事例をもとに転倒対策についての講演をしていただきました。
この記事では、特別ウェビナーにて紹介いただいた導入事例について、紹介していきます。
また、製品「ころやわ」の紹介もしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
身体的拘束最小化のひみつ道具「ころやわ」導入事例に学ぶ転倒対策
今回は、実際に「ころやわ」を導入してくださった3病院の職員様より、導入事例について紹介いただきましたので、その具体的な内容を解説します。
特に、以下のことをピックアップしてそれぞれ講演いただきました。
・どのような患者様に「ころやわ」を使用するのが効果的であるか
・現場での設置における工夫やポイントについて
・導入後の変化について
・現場で利用いただくために行なったこと
・現場の課題と今後の展望
・身体拘束最小化にどのように貢献したか
どのような背景があり導入に至ったのか、または、導入後の効果と今後の取り組み・課題についてお話しいただいた内容をまとめましたので、紹介していきます。
事例1:重症化予防に焦点を当てた転倒・転落対策の導入とその効果

宗像水光会総合病院 医療安全管理室 / 髙橋 博愛 様
転倒や転落による重症外傷による転帰不良の事例が増えたことにより、その予防策として
「ころやわ」を導入された宗像水光会総合病院様。
医療安全管理室の髙橋 博愛様より、背景や導入後の効果等についての詳細をご紹介いただきましたので、以下で解説していきます。
導入の目的と背景
入院患者様の高齢化の進展により、入院中の転倒・転落発生が増加したり、重症外傷により転帰不良につながる事例が相次いで発生したりしたことが「ころやわ」導入の大きな背景となります。
また、2021年に医療安全に関する緊急事態を発令し、病院全体で転倒・転落発生を予防する目的にてさまざまな取り組みを講じました。
例えば、次のような取り組みです。
・低床ベッド
・リストバンドへの転倒リスク度色分け表示による可視化
・患者・家族への啓発
上記の取り組みにより、とにかく転倒を減らすことに着目していました。
しかし、結果、生命予後に直結する重症事例は減少しましたが、転倒・転落発生率および骨折などの重症外傷は減少に至りませんでした。
分析した結果、センサー使用していたとしても転倒件数は減っていなかったことや、センサーを使用しても転倒は大幅に減少させることができなかったことが現状の課題ということが明らかになりました。
そこで、転倒を防ぐという視点から重症化を予防するという取り組みに変えていったのが「ころやわ」導入のきっかけです。
導入時や導入後の効果について
早速、衝撃低減マットの「ころやわ」を導入しました。
導入当初は次のようなネガティブな意見も聞かれました。
・使い方がわからない
・大きくて邪魔だな
・本当に転んでも大丈夫なの?
しかし、効果測定ができるまではとにかく「使う」ということに統一したのです。
導入後、2023年1月から半年でマット上の転倒は6件ありましたが、そのうち重症化した事故は0件で、重症化の予防に効果を感じました。
効果を実感した現場からはマットが足りないという声も聞かれるようになりましたので、センサー類を減らしマットを追加購入することにしました。
年次別の重症件数及び重症化率は次のとおりでした。
| 年次別 | 重症化率 |
| 2021年度 | 5.74 |
| 2022年度 | 5.58 |
| 2023年度 | 3.77 |
ころやわ導入台数:2023年1月9台+2024年2月12台 計21台
導入後の2023年からは転倒・転落事故による重症化率は減少していることがわかります。
今後の取り組みについて
従来の対策は患者の行動を制限することに焦点が置かれていましたが、今回の取り組みでは患者様の自立を尊重しつつ重症化を防ぐ対策に転換しています。
これにより、患者のADLの向上につなげることができるからです。
また、身体的拘束最小化に向けてのチームを発足させ、これまでの運用を見直し、今後も実施していきます。
その他、身体的拘束の三原則を現場に周知し、基準の全てを満たさない限り身体的拘束を実施できないこととしました。
事例2:身体的拘束最小化の取り組みに向けて

札幌東徳洲会病院 医療安全管理室 / 松山 尚子 様
転倒転落発生率は上昇、重度損傷発生率は下降傾向だが全国平均を上回り横ばいが続いており、その予防策として「ころやわ」を導入された宗像水光会総合病院様。
医療安全管理室の先生より、松山 尚子 様より背景や導入後の効果等についての詳細をご紹介いただきましたので、以下で解説していきます。
導入の目的と背景
院内の転倒転落発生率、または転落による損傷レベル4以上の発生率は次のとおりです。
【年次別、転倒・転落発生率】
| 年次別 | 転倒・転落発生率 |
| 2021年度 | 2.62‰ |
| 2022年度 | 2.82‰ |
| 2023年度 | 3.20‰ |
【年次別、転倒による損傷レベル4以上発生率】
| 年次別 | 転倒による損傷レベル4以上発生率 |
| 2021年度 | 0.11‰ |
| 2022年度 | 0.07‰ |
| 2023年度 | 0.07‰ |
転倒転落発生率は上昇し、重度損傷発生率は下降傾向ですが、全国平均を上回り横ばいが続いている状況でした。
また、リスク管理面からやむを得ない事情で身体拘束を実施したとしても、転倒・転落は減少しませんでした。
それどころか患者様の行動を制限することでADLが低下し、それが悪影響となり転落・転倒の発生によりつながっていた事実もあります。
身体拘束をしても、転倒転落による損傷を減らすことにはならないと気づいたのです。
これが、身体拘束をしない看護と転倒・転落発生率から見えた課題であり、ころやわの導入を検討した理由になります。
導入時や導入後の効果について
2022年頃からころやわを数枚から使用開始しました。
ころやわの導入にあたって、届くまでの期間、保管方法などを決めて周知しました。
また、導入時の研修を実施したり、院内ニュースでころやわの使用例などを呼びかけたりしました。
導入後は、認知症ケアチームとの協同活動を行い、現場には「身体拘束しないケアにはころやわ」と働きかけています。
導入後の効果については残念ながら、院内全体のデータからは、転倒による損傷レベル4以上発生率を減少させることはできませんでした。
しかし、ころやわを使用した上での骨折につながる事故はありませんでした。
今後の取り組み
転倒による損傷レベル4以上発生率を抑えられなかった原因としては、骨折リスクの高い患者様にころやわを使えていなかったのではないかと分析しています。
今後はころやわを増やし、リスクある患者様にできる限り設置することが課題となります。
事例3:ころやわ導入の取り組みと定着について

公立藤田総合病院 医療安全管理対策室 / 東 泰弘 様
入院患者様の転倒・転落事故の増加は、物質資源の不十分によるものと気づいたことがきっかけで「ころやわ」を導入された宗像水光会総合病院様。
医療安全管理対策室の 東 泰弘様よりこれまでの背景や導入後の効果等についての詳細をご紹介いただきましたので、以下で解説していきます。
導入の目的と背景
院内の入院患者様の転倒・転落状況は、次のとおりです。
| 年度 | 発生率 |
| 2019年度 | 3.03‰ |
| 2020年度 | 2.65‰ |
| 2021年度 | 3.32‰ |
| 2022年度 | 3.48‰ |
| 2023年度 | 2.86‰ |
| 2024年度 | 2.87‰ |
表のとおり、入院患者様の転倒・転落事故が増加している現実がありました。
また、2022年度の院内の事故発生率は3.48‰で同年の全国平均(QI指標)を上回ってしまいました。
さらに、転倒・転落による骨折事例は全国平均より高くなってしまいました。
その要因として、人的・物的な資源が不十分であったり、組織的な質改善の仕組みがなかったりすることが理由の一つであることに気づきました。
そこで事故発生率、または骨折事例発生数の減少を目指し、3つの対策を行うことにしました。
・未然防止策(転倒転落の機会を軽減)
・直前防止策(直前防止策)
・被害軽減策(転倒転落の損傷を軽減)
しかし、上記の対策を行うための物的資源が不十分であることに気づいたのです。
そこで、ころやわの導入を決断しました。
導入時や導入後の効果について
ころやわの導入と定着に向けて、行った取り組みは次のとおりです。
・デモによるイメージの共有
・ルール作りとリーフレットでの周知
・転倒転落チームメンバーのリーダーの配置
・使用状況がわかる仕組みづくり
・ころやわ設置の工夫(設置と管理の基準をつくり、院内に周知)
転倒転落対策チームを中心に、現場でころやわの効果を最大限発揮できるような取り組みを事前に行いました。
それが、デモによるイメージの共有やルールづくり、リーフレットでの共有などです。
また、分析しやすいよう使用状況がわかる仕組みづくりも行いました。
ころやわ導入後3か月の変化としましては、導入前2か月前に比べ、導入後2カ月は転倒転落発生率が3.34‰から2.78‰になり減少していたことが明らかになりました。
しかし、損傷レベル2以上発生率は0.73‰から0.83‰に増加。
その背景としては、ナースコールが押せない患者の増加し、擦過傷や表皮剥離といった損傷レベル2以上の発生率が上がってしまったことにあると推測しています。
また、職員へのアンケート結果、ころやわの効果の実感については現段階では50%の満足度でした。
今後の取り組みと課題
今後の取り組み内容としては、次のとおりです。
・PDCAサイクルを回し続ける
・フィードバック・情報発信
・人材育成・教育的支援
効果的な運用に向け、転倒転落チームのサポートを続けるとともに、「転倒転落通信」を院内に発信し、そのなかでころやわの使用状況や身体拘束の情報を伝えていきます。
転倒転落やそれによる損傷の発生増加により、被害軽減策が不十分を見直したことから、転倒転落対策チームを発足させてきました。
今後も転倒転落チームを中心にころやわの使用状況の共有やころやわを使用している患者様へのラウンドを続け、さらなるころやわ使用の定着につなげていきたいと思います。
ころやわについて

ころやわの主な特徴は、次のとおりです。
・転んだ時の衝撃吸収
・歩行の安定性、車椅子の走行性の確保
ころやわは、普段は堅い床で歩きやすく、転んだときだけ凹んで転倒の衝撃を吸収し、骨折予防として活用できるマットです。
転倒時の衝撃は、一般的なフローリングの約半分程度まで抑えられる設計となっています。
マットの特徴としては、より浅い設計となっており、誰でも安全に歩くことができる仕様です。
緩やかな勾配であり、車椅子でも自走可能。
滑りにくさの基準を満たした表面材になっているのもポイントです。
また、転倒による骨折予防としては、各商品をそれぞれ使い分けることができます。
転ばせない対策:ころやわマットセンサー
ケガさせない対策:ころやわマット
また、ころやわにつきましては、設置範囲や目的に合わせたラインナップをご用意しています。
気になる方はぜひこちらをチェックしてみてください。
まとめ

今回は実際にころやわを導入いただいている3件の病院職員様に、導入目的や導入中の工夫、導入後の効果や今後の取り組み・課題について紹介いただきました。
その他にも、まだまだ導入された方のお声や事例はこちらで確認できますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
なお、株式会社Magic Shieldsでは、今後もさまざまなウェビナーを開催していきます。
今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。