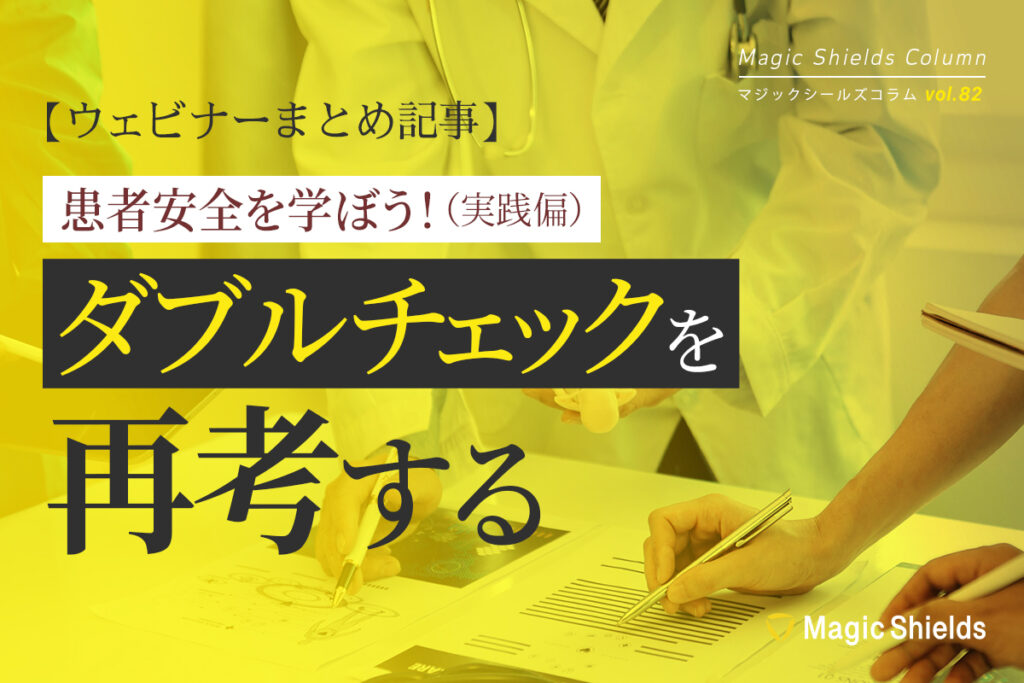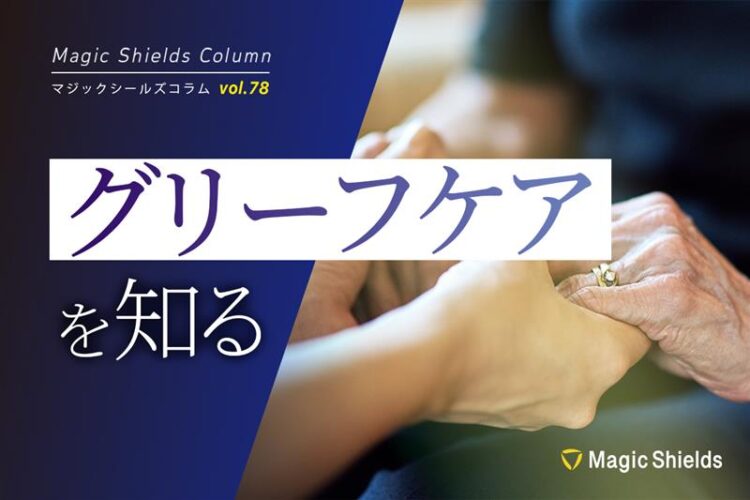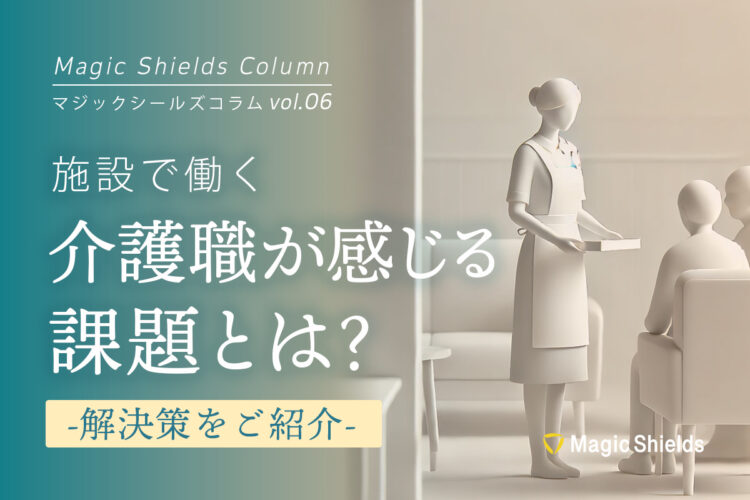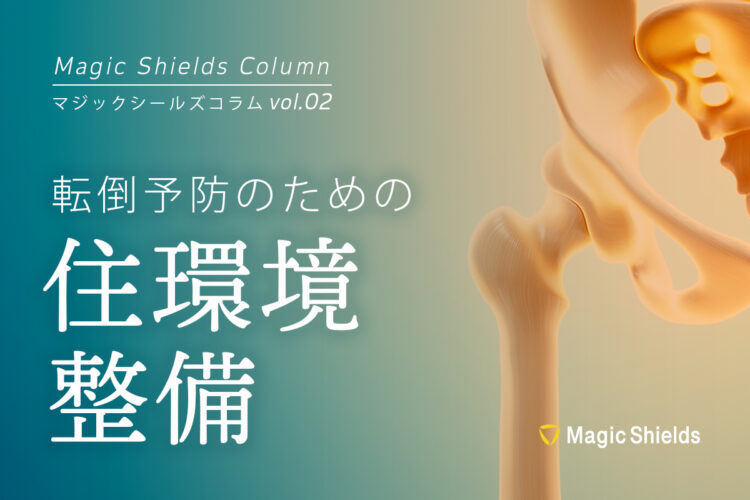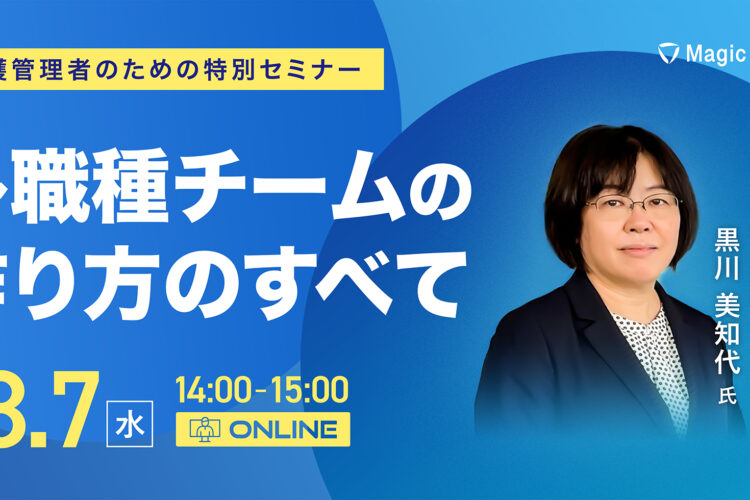目次
「日頃の業務の中で、ミスをしてしまわないか常に心配に思っている」または、「看護管理者として、安全な医療の提供のためにヒューマンエラーを減らしたいと思っている」と感じている方のために、前回は松村先生患者安全についての基礎編を講義していただきました。
今回はそれを踏まえての患者安全実践編をお話しいただきましたので、その内容を紹介していきます。
※前編の基礎編の動画やまとめ記事もぜひご参照ください。
ダブルチェックをしたのになぜ?【無効なダブルチェックを挙げて批判的に考えてみよう!】

ダブルチェックが実は無駄だったということがあります。
ダブルチェックしたのに患者誤認してしまった仮想事例を元に、ダブルチェックが有効ではない理由を紹介していきます。
【誤薬の仮想事例】
看護師Aさんは、患者の織田信長さんのベッドサイドに行き、抗がん剤の投与準備を始めました。
「お名前をフルネームで名乗ってください」と伝え「織田信長です」と返事。
手元の注射指示書を見て、指示書の患者氏名が織田信長であることを確認しました。
次に患者のリストバンドと駐車ラベルをPDAで読み込みました。
投与する薬剤は3つあり、3つとも読み込んで〇がでたので、薬剤の入った輸液バッグを点滴棒につるしました。
他の看護師Bさんにバッグが違うかもと指摘を受け、よく確認したら豊臣秀吉さんの氏名が書かれていたバッグでした。
あやうく他の患者の抗がん剤を投与してしまうところでした。
ダブルチェックをしたのに誤薬につながってしまった原因
上記の仮想事例ではダブルチェックをしていたのに、なぜ誤薬につながってしまったのでしょうか。
原因は次のとおりです。
原因1:ダブルチェック原理の理解不足
本来であれば、注射薬投与時の患者と注射薬の照合の極意となります。
しかし、上記では注射指示書を見て、名乗らせ確認をし、PDAによる照合をしています。
投与するのは、注射薬であって指示書ではないため、正しくは注射薬との照合が必要でした。
原因2:PDA照合時にヒューマンエラー発生
上記のPDA照合時、〇✕〇の順に表示されたことが調査によって判明しました。
しかし、看護師Aさんは確認不足により、✕を見落としてしまったのです。
確認不足は、実施者本人の思い込みや時間プレッシャーの存在により発生しやすくなります。
原因3:スタッフステーションでの取り揃え段階でダブルチェックした際、他患者の注射薬を混在させた
取り揃え段階でダブルチェックをした際に、他患者の注射薬を混在させてしまっていたのも原因の一つです。
ダブルチェック前は正しい位置にあったものの、ダブルチェックを実施する過程で注射薬を動かしてしまい、結果混在してしまったのです。
根本原因と再発防止策
ダブルチェックで誤薬につながってしまった事例から、見えてきた根本原因は次のとおりです。
ダブルチェック時間帯が集中している
ダブルチェック時間帯が集中すると、多くの患者トレーが並び、エラーを余計に誘発してしまいます。
ダブルチェックの必要のない注射薬もダブルチェックしている
抗がん剤は薬剤部で無菌調製され、調製済みの状態にて搬送されています。
そのため、調製後のダブルチェックに意義はないということになります。
再発防止策
上記から再発防止策としては、以下が有効です。
・ダブルチェック対象を絞り込み、不要なダブルチェックを廃止する
・残った必要なダブルチェックに対し、作業時間をスペースを確保する
看護師によるダブルチェックの現状
看護師は同時ダブルチェックが多いです。
例えば、指差ししながら合っているか確認する、または指示簿とラベルと薬剤を二人で一緒に同じものをみるなどです。
一方で薬剤師は時間差でダブルチェックをします。
一人が処方箋に記載のある薬剤を取り揃え、もう一人が薬剤が処方箋通りか確認します。
そうすることで、例えば同時服用が禁忌である薬剤を処方する際にも、患者の状態に薬が適切であるかの妥当性のチェックが可能です。
独立してチェックを実施することで、相手に依存しない確認ができます。
医療機能評価「年報」の医療事故情報の報告事例には「ダブルチェック」の記載が、2019年時点で30823件の医療事故のうち、834件ありました。
医療事故の報告のうち、約3%がダブルチェックの記載があることがわかります。
特に、医療事故事例では、改善策としてダブルチェックを記載していることが多いです。
多くの看護師が、ダブルチェックを事故再発防止策と認識している傾向にあります。
しかし、ダブルチェックは本当に有効な改善策であるのかを今一度、立ち止まって考えていただきたいのです。
ダブルチェックは、Sacred cow「神聖な牛」と同じような扱いをされている可能性があります。
Sacred cow「神聖な牛」とは、インドで大切に扱われている聖牛を神聖にして犯すべからざると考えられていることからきている言葉です。
つまり、大衆に大切にされているからこそ、批判や攻撃がしづらいものということになります。
ダブルチェックの罠
ダブルチェックとは、そもそも本当に有効な対策なのでしょうか。
ダブルチェックが広まった経緯は、過去、大学病院や公的病院での医療事故が次々に報道されたことで、その改善策として医療事故防止緊急合同会議が、ダブルチェックができるような体制をつくることが大切であるという声明を出したことがきっかけでした。
ダブルチェックの有効性を確認した実験「確認の多重化とエラー検出率」によると、確認する人数を増やしても(多重化)エラー検出率が比例して上がることはないことが明らかになっています。
それどころか、何重にもチェックを行うことでエラー対策は大丈夫と考えるため、単なる気休めや責任逃れになってしまうのです。
これは、リンゲルマン効果と呼ばれる社会的手抜き現象によるものです。
リンゲルマン効果とは、フランスの農学者であるマクシミリアン・リンゲルマン氏によって提唱された理論です。
集団で共同作業を行う場合、一人で作業をするときと比較すると他の人がいる安心感により無意識に手抜きしてしまい生産性が下がってしまうという意味になります。
また、2名の人的資源を投与することにより、その分時間を使うため、時間プレッシャーが増加してしまいます。
参照:地方厚生局「ダブルチェックの有効性を再考する」確認の多重化とエラー検出率
ダブルチェックエラーが起こった際には工程を確認する

ダブルチェックをしていても、なぜミスが起こってしまうのでしょうか。
その原因である作業工程を確認していくことが大切です。
事例:配薬時の患者誤り
例えば、配薬時の患者誤りの事例を紹介します。
患者の織田さんは配られた袋の中に薬がひとつないことに気づきました。
患者の豊臣さんが空の薬を持ってきたため、配薬時に誤りがあったことが発覚しました。
上記の事例の場合、作業工程をまず確認します。
当時の内服薬の配薬手順は、患者別薬袋をタイミング別に配薬ボックスに入れ、そして配薬します。
このように、インシデント報告があったら、まず標準工程を確認しましょう。
そして標準通りできなかった背景を考えます。
【背景】
当時、多忙のためダブルチェックができず、一人目の看護師が配薬ボックスに薬剤を準備し、別の看護師に再確認を依頼しました。
二人目の看護師が配薬ボックスの中身を再確認する際に乱雑なテーブルの上に作業スペースを確保せずに投薬ポケットの内服薬を広げて確認してしまったことで、他患者の薬剤を誤って混入してしまったことが原因でした。
事例にみるエラー誘発因子
上記の事例からわかる、エラーを誘発しやすい原因は次の通りです。
- ・適切な時間が確保されない
- ・中断業務、注意が逸れる
- ・適切なスペースがない
- ・他患者の薬が混じりやすい
上記の悪条件があると、いくらダブルチェックを実施していてもエラーが発生しやすくなります。
ダブルチェックの対象の絞り込みのすすめ

ダブルチェックは全てを対象とするのではなく、対象を絞り込み実施していくことが大切です。
ここからは、ダブルチェックの対象の絞り込みがなぜ重要なのか、また有効なダブルチェックの方法などを紹介していきます。
ダブルチェックが有効なのはミステイクのエラー(判断のエラー)
ダブルチェックは、4つのエラー(錯誤、失念、考え違い、違反)の全てに有効なわけではありません。
実は、考え違い(計画段階でのエラー、計画そのものが間違っている、思い込み)のみに有効なのです。
2種類の思考パターンを利用した確認方法
私達の思考パターンには、大きくわけて2種類があります。
速い思考(システム1)と遅い思考(システム2)です。
- ・システム1
速い思考、指導的に高速に働く思考モード、自動運転、省エネモード
- ・システム2
遅い思考、複雑な計算など頭を使わなければできない困難な知的活動にしかるべき注意を払う思考モード
上記の思考パターン2種類を利用した確認方法が指差し呼称になります。
指差し呼称は、速い思考モードと遅い思考モードの両者を利用して行うため、エラーが発生しにくくなるのです。
指差し呼称のエラー防止効果の室内実験による検証によると、指差し呼称を行った場合のエラー発生率が実施しないときよりも大幅に下がっていたことが明らかになっています。
また、「指差し確認」や「確認呼称」は、一人での作業精度を高めることがわかります。
ただし妥当性のチェックが必要なときには、ダブルチェックが必要になります。
例えば、体重8㎏の小児への薬剤処方量など複雑な作業が必要な場合は、妥当性のチェックとしてダブルチェックを実施しましょう。
確認方法の使い分け
上記の確認方法をまとめると以下になります。
- ・照合型チェック:一人で指差し確認
- ・妥当性チェック:ダブルチェック
照合型のチェックなのにダブルチェックを実施してしまうと、以下のようなリスクが残ります。
- ・二人とも手抜きをしてどちらも見落とす
- ・二人目の時間を奪い、作業効率が下がる
つまり、確認には種類により適切な方法で実施していくことが大切だということです。
一人でチェックするのが心配な場合は機械チェックを追加する
照合型チェックだとしても、一人でチェックするのは心配と感じる人もいるでしょう。
そういった場合には、機械チェックを追加することが有効です。
例えば、注射薬と患者の電子照合システムがそれに該当します。
人間は臨機応変である一方で、機械は融通が利かないため、お互いの性格を組み合わせた確認が有効になります。
チェックを増やすという防止策は悪手
ダブルチェックを安易に増やすことはひとつひとつの作業の精度が下がり、さらにエラーを誘発してしまいます。
ミスが発生したときに、ダブルチェックを増やすという防止策は悪手になります。
こういった場合、ただダブルチェックを増やすのではなく、なぜ単純なエラーが発生するかという根本原因への対応が必要です。
エラーサイクルをブロックします。
ダブルチェックは、認知的作業を行う場面で2名で独立した方法で実施しましょう。
ルーチンの照合型チェックにダブルチェックは向かず、シングルチェックが有効となります。
有効なダブルチェックの条件
有効なダブルチェックの条件は次のとおりです。
- ・独立したダブルチェックをすること
- ・賢明な方法で実施すること
- ・ダブルチェックだけに頼らないこと
全てのハイアラート薬をダブルチェックしてはいけません。
少数のリスクの高い薬剤へのダブルチェックに限定するほうが、多数の薬剤に実施するよりも効果が高いです。
また、ダブルチェック以外の方法も組み合わせてリスクを最小化しましょう。
例えば、薬剤の計算のダブルチェックは、看護師Aと看護師Bが別々に計算して照合するのみが有効になります。
対象となるハイリスク薬
ダブルチェックの対象となるハイリスク薬は次のとおりです。
・抗凝固薬
・化学療法薬
・インスリン
・麻薬
・その他部署で決定
エラーが生命に直結するものに限定しましょう。
まとめ

単純エラー発見目的でのダブルチェックをやめることで得られるメリットは、多く存在します。
【得られるメリット】
- ・時間を抽出できる
- ・より時間をかけてひとりで確認できる
- ・中断業務が発生しづらくなる(ダブルチェック)
エラーの減少につながるよう、目的に合った適切な確認方法を実施していきましょう。
株式会社Magic Shieldsでは、今後もさまざまなウェビナーを開催していきます。
今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。