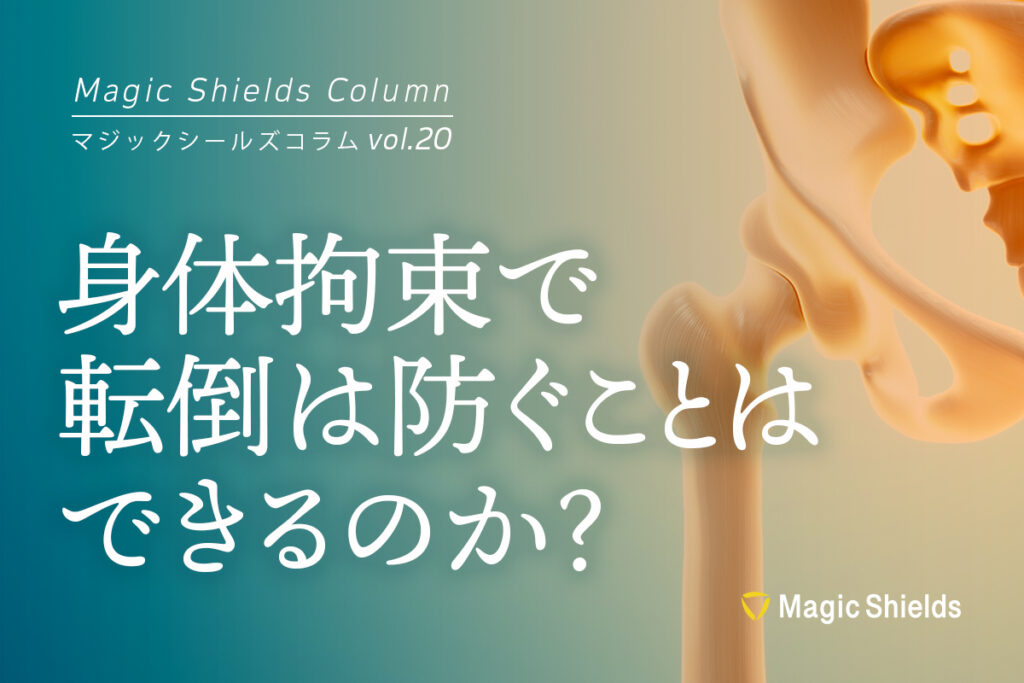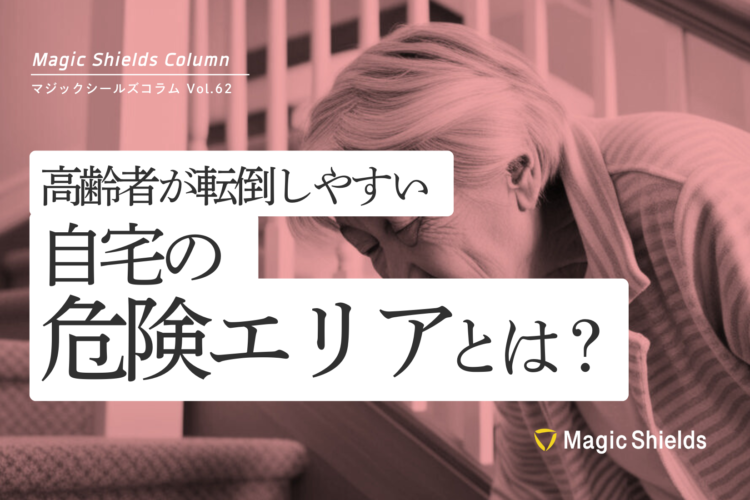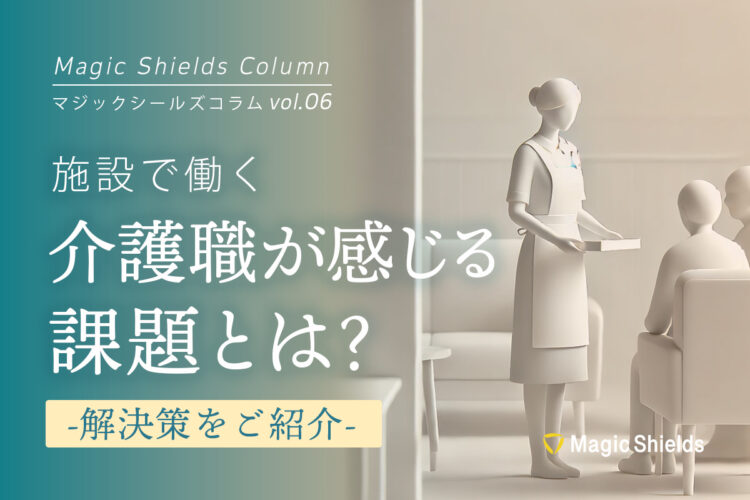身体拘束はその名の通り、身体を拘束して自由に動けないようにすることです。医療現場では、転倒の防止など患者の安全確保のためにやむを得ず行われてきました。しかし、身体拘束は人権を考える上で非常に大きな問題であり、国も身体拘束をなくす方針を打ち出しています。にもかかわらず、今日の医療現場に身体拘束は残っています。
今回の記事では、なぜ身体拘束はなくならないのか?身体拘束をしないためにはどうすればいいのか?を考えていきたいと思います。
医療現場における身体拘束とは?
医療現場における身体拘束は、古くは昭和63年に当時の厚生省が「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」と、定義を告示しています。
また、身体拘束は「やむを得ない場合」に行われますが、それは“切迫性(本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合)”、“非代替性(身体拘束以外に代替する介護方法がない場合)“、“一時性(身体拘束は一時的なものであること)”といった“身体拘束の3原則”が全て満たされた状況を指します。
医療現場の身体拘束の例
- 転倒リスクの高い患者が1人でベッドから降りられないようにベッド柵で囲う。
- ベッドの片側を壁に付ける、またはテーブルを固定して患者がベッドから降りる方向を制限する。
- 認知症のため点滴の必要性が理解できない患者が自己抜去しないよう、手をベッドに括り付ける。
- 手術後の創部を掻いたり触ったりできないよう、つなぎの服を着せて服の中に手を入れられないようにする。
- 患者が車いすから1人で立ち上がらないように抑制帯で体と車いすを括り付ける。
- 興奮状態の患者が落ち着くようにと過剰に向精神薬を服用させる。



例えば、転倒・転落は大腿骨骨折のリスクがあり、患者の身体と生命を脅かす危険があります。そう考えると転倒のリスクが高い患者に身体拘束が行われるのは「やむを得ない場合」なのかもしれません。
しかし、身体拘束により転倒などの事故から患者の安全を守れるというエビデンスは得られていません。ベッドから降りられないよう柵で周囲を囲ってもそれを超えて降りようとする患者や、向精神薬を服用することで歩行のバランスが悪くなる患者もいるのです。これでは身体拘束をする意義が見出せません。
医療と介護の違い
介護現場では、身体拘束ゼロの動きが医療現場より先行しています。平成11年に厚生労働省から介護保険施設などにおける「身体拘束禁止」が省令されました。ここでは「緊急、やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない 」と記載されています。この「緊急、やむを得ない場合」は前述の“身体拘束の3原則”を満たす状況を指します。

しかし、医療現場には、手術後や点滴による治療といった「緊急、やむを得ない場合」が介護現場に比べて多く、患者の安全を守るため身体拘束という手段を取ってしまいます。限られた人員で患者の安全を守ろうとすると、患者の自由度を奪う身体拘束に行き着いてしまうのです。もちろん、身体拘束をする側の看護師をはじめとした現場スタッフは、患者の自由を奪うことに対する申し訳ない気持ちと「安全のため、やむを得ない」というジレンマにいつも悩まされています。

身体拘束をなくすには?
身体拘束がなくならない1つの理由に「人員不足」が挙げられます。看護師は1日に何名もの患者を担当し、看護助手も配膳やおむつ交換など多くの業務があります。つまり1人の患者につきっきりになれる時間は限られているのです。しかし、経営面を考えた時、患者の見守り強化のために過度に人員を増やすのは現実的ではありません。そこで、考えられる対策は2つあります。
意識を変える
1つ目は、「医療事故への意識を変えること」です。例えば、転倒や点滴の自己抜去が起こった際、上長がその日の担当の看護師を責めるような言動をしてしまうと「事故を起こしてはいけない!」という雰囲気が醸成されてしまいます。そうなると、患者の人権より安全を優先した身体拘束のような対応が広がってしまいます。例えば転倒はいくら対策をしても起こってしまう事故です。それはスタッフ1人の責任ではないという意識が必要です。事故が起こった時、病棟やチームでフォローや対応を考える体制が望まれます。
多職種チームで取り組む
2つ目は、多職種チームでケアの方針を考えることです。認知症患者は治療上の安静度の理解が乏しく身体拘束の対象になることが多いですが、診療報酬の“認知症ケア加算“の要件には「身体拘束を実施するかどうかは職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師など複数職員で検討すること」「やむを得ず実施する場合であっても、代替の方法が見出されるまでのやむを得ない対応であり、できる限り早期に解除すること」と記載されています。つまり、認知症があるからと安直に身体拘束をするのではなく、多職種で継続的に評価し対策を練ることが重要であると国が示しています。医師は当該患者の病態の把握と治療の選択、看護師は日常のケア、薬剤師は服薬の見直し、リハビリ職は看護師と協働して早期離床を促す、など多職種で関わる意義は大きいです。

まとめ
別の記事でも取り上げた「転倒事故による医療訴訟」の結果、転倒させた病院に非があるという判決が下りたことは、現場での身体拘束への依存を高めるのではないかと個人的に危惧しています。身体拘束は患者の自由と人権を奪います。さらにそれを行うスタッフも相当な葛藤を強いられます。まずは、「事故は個人の責任ではない」という意識を持ち、多職種チームで認知症ケアにあたることで、少しでも身体拘束が減少することを願っています。