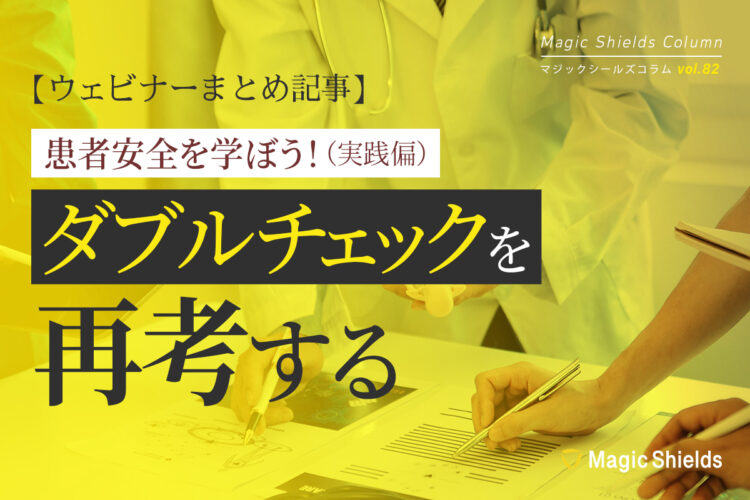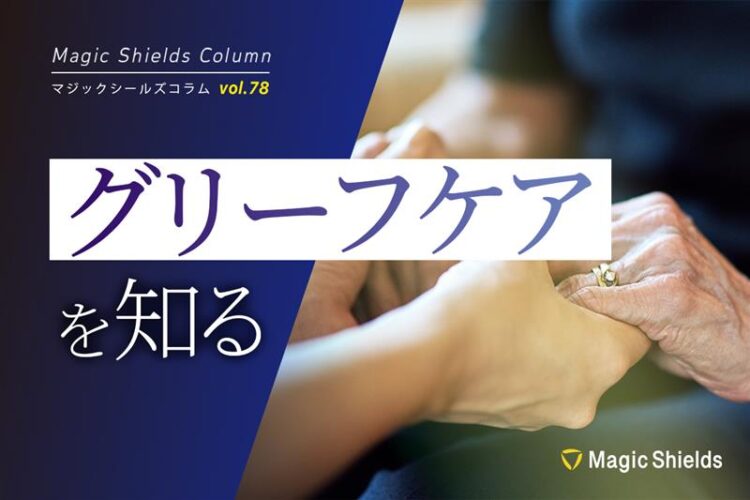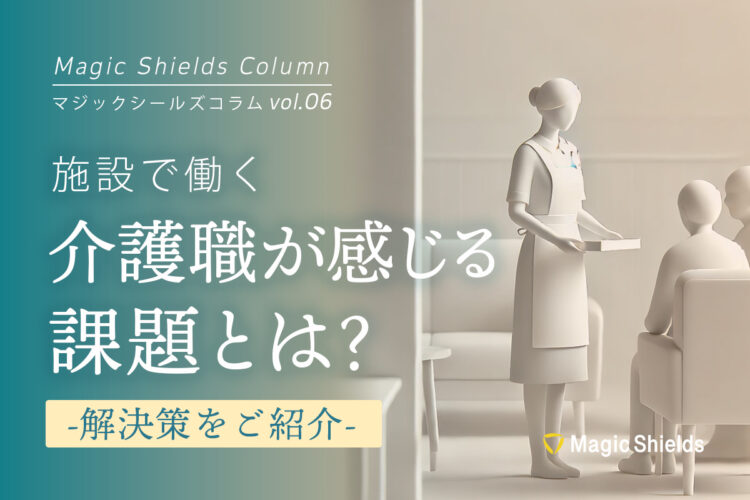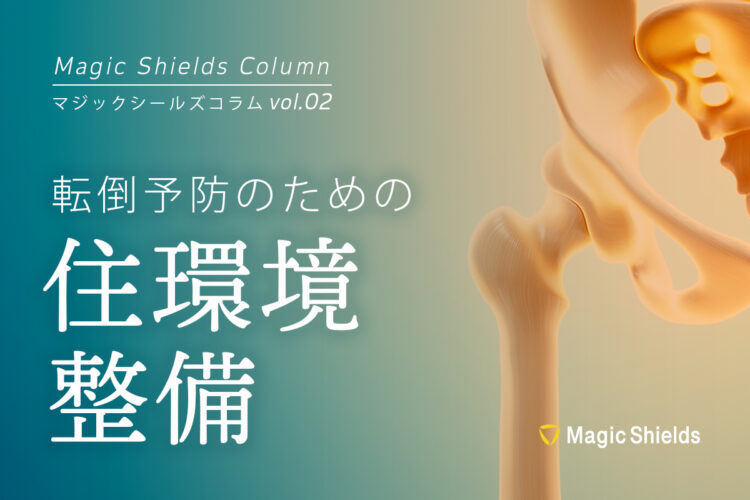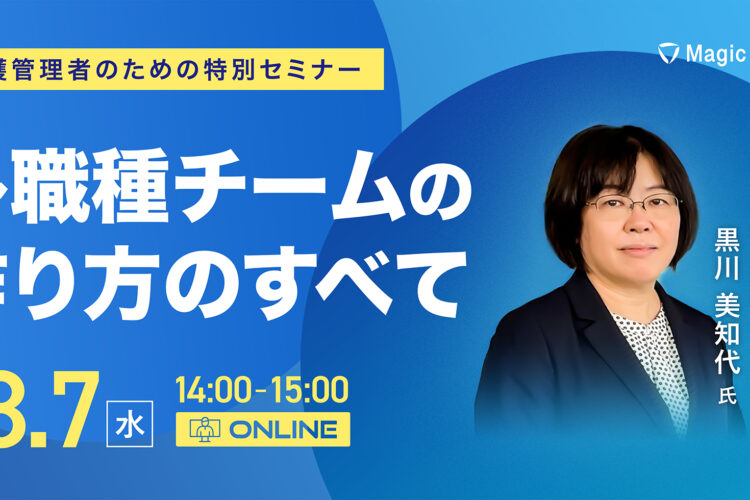目次
「自組織の認知症ケアの質が上がらない」「転倒のリスクアセスメントをしていても認知症の影響で転倒が防ぎきれない」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
認知症ケアには、ぜひ本人の立場に立って行うケア「パーソン・センタード・ケア」を取り入れていきたいところです。
今回は、高齢者の転倒や認知症に関する数多くの論文や書籍を執筆されている鈴木みずえ先生に、認知症ケアに必要な「パーソン・センタード・ケア」についてお話いただきました。
その内容を記事にまとめましたので、ぜひご覧ください。
認知症の人は何も理解できないのか?

認知症の人の行動や気持ちがよくわからないと思う人もいるのではないでしょうか。
そこで、認知症の人の気持ちが体験できる仮想事例を紹介していきます。
以下の事例から、認知症の人の視点で考え想像してみてください。
わからない自分に対して不安になる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【事例】
あなたは、高齢者のケアに関する研修会に参加しています。
講師が登場し、挨拶の後、学級崩壊による児童問題を喋り出します。
「あれおかしいな」と思って周囲を見渡すと他の参加者は頷きながらメモを取っています。
会場を間違えたはずはないのに、不安が強くなってきます。
どうなっているのかと思いつつ隣の人に「これは高齢者のケアの研修会ですよね」と尋ねると何を言っているんだという表情で「児童問題でしょう」と言われてしまいます。信じられず後ろに座ってる人にも、同じこと聞くと迷惑そうに「児童問題でしょう」と言われます。戸惑い不安は増幅し、 そんなバカなという相手への不信感も生まれます。
どこかで「あの人は何も分からなくなっているから」という声がします。
じっとしてるわけにはいかないので、席を立って主催者に確認しようとします。
すると職員らしい人がやってきて、穏やかではあるものの有無を言わせぬ口調で「お席に戻りましょうね」 と言われます。
そういうわけにはいかないので「確認に来たいのです」と扉から出ようとするともう1人の職員もやってきて2人掛かりで席に戻されます。
不当な扱いを受けてるという怒りが湧き上がってきます。
何がどうなってるのか分からないため、帰ろうと思い、再び席を立とうとすると押えつけられて自分では外せないベルトをかけられます。
まるで囚人のような扱いに1人の社会人としてのプライドが傷つけられます。
帰りたいと叫ぶが相手にしてもらえません。
誰も信じられなくなり、もしかしたら 自分がおかしいのではないかという不安、自信のなさも起こってきますが、そんな ことはないと打ち消しています。長時間そのような状況に置かれ、イライラとした継続的なストレス状態になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の事例を読んで、どのような気持ちになったでしょうか。
こんなときには、本当は次のように声をかけてほしいものだと思います。
- ・「何かあったのですか?」
- ・「お困りですか?」
わからない状態で不安なのにも関わらず、誰もわかってくれないどころか、さらに行動を抑制されたら反発したくなったり、自尊心が失われたりするのではないでしょうか。
認知症の人の状況
認知症の人は認知機能が失われたこと、失われそうな戦いの中で悲しみや不安を感じ自分の状況を一番わかっているのに認知症に対する社会の偏見により、話すことがゆるされない状況にいます。
行き場のない苦しみの感情は怒りになったり無気力になったりします。
また、認知症の人は、認知機能の低下に伴う記憶障害や見当識障害、理解・判断力の障害や実行機能障害があるために、入院による環境の変化から混乱して恐怖を感じています。
私たちの「何もわからない人」「理解できない人」という決めつけや偏見は、いつの間にか認知症の人に伝わり、さらに認知症の人を苦しめてBPSDを増大させてしまうのです。
認知症に苦しむご本人の気持ちに向き合うこと、理解しようと努力することが重要です。
反対に、認知症の人を放置したり苦痛を与えたりするとBPSDを発症し、それが原因で生活障害の増大やQOLの低下などさまざまな弊害をもたらします。
認知症とBPSD

ここからは、認知症とBPSDについて詳しく解説していきます。
認知症の行動・心理症状(BPSD)には理由がある
認知症の人の苦痛や苦悩の表現やチャレンジ行動(訴えかける行動)には、理由があります。
認知症の人の行動背景がわからないと思ったら、まずは認知症症状の特徴を考えましょう。
認知症による障害や心理症状(BPSD)を、以下に紹介していきます。
認知機能障害
- 記憶障害:新しいことを覚えられない
- 失行:手足は動くが動作や操作ができない
- 失認:モノが何かわからない
- 失語:モノの名前がでてこない
- 実行機能障害:段取りができない
治療・ケアによる痛み・苦痛
- 認知機能に合わせた治療・ケアの説明がされていない
- 身体疾患による苦痛・痛み
- 慣れない生活環境
- 家族や親しい人がいない
- 安静臥床、雑音が多い環境
認知症の行動・心理症状
- ものを盗まれたという(妄想)
- いない人の声が聞こえる
- 実際にないものが見える(幻覚)
- 大きな声をあげる(暴言)
- 点滴や着替え等を嫌がる(治療・ケアの拒否)
- 歩き回る(徘徊)
BPSDのとらえ方
認知症の行動・心理症状で表面化し、私たちがみえる部分はほんの少しです。
実は、みえない行動に本人のニーズが隠されていることもあります。
みえない行動の原因は、不安や孤独感、痛みや苦痛です。
目にみえる行動を抑えたり、抑えるための身体拘束をしていた過去もありますが、今後は見えない行動の原因に着目し、本人視点で行動の背景にある原因やニーズを満たすことが大切です。
原因が緩和されれば、それに伴いBPSDの緩和につながります。
本人・家族・ケア提供者の想いのズレ
認知症の本人と、その家族やケア提供者の3者に想いのズレが発生することがあります。
例えば、帰宅願望が強く「家に帰る。母が待っている」と自宅にいるのに出て行ってしまうという事例に合わせて、よくある3者の想いをみていきましょう。
| 認知症の本人 | 家族 | ケア提供者 |
| ここには居場所がない自分で動きたい、行動したい自分はしたいことを否定されるためイライラする | 家族のものを買って位にいじるのでカギをかけるしかない勝手に外出して事故を起こす可能性があるので部屋に閉じ込めるしかない静かにしてほしい | 事故を起こさないで安全に過ごしてほしい本人の家族への対応をよくしてほしい |
このようにズレがあると、ケアがうまくいかず、本人のBPSDが増大します。
その結果、認知症の本人の問題行動や心理状態が悪化し、介護者の負担になってしまうのです。
海馬と偏桃体
記憶の中枢「海馬」と感情の中枢「偏桃体」は隣り合っています。
そして、海馬の活動が弱まると偏桃体の活動が高まるのです。
海馬が萎縮したアルツハイマー型認知症の人に楽しい雰囲気の経験をすると、海馬に刺激が届いて記憶に残りやすいです。
認知症の人の維持される機能
認知症の人には、維持できない機能もありますが、反対に維持される機能もあります。
いつ、誰が、何をしたかなどを記憶する認知機能は維持できませんが、相手や自分がどう感じたかなどの感情機能は維持されているのです。
認知症の人は、本当に言いたい思いまでわからなくなっているわけではありません。
認知症の人の維持されている機能に、よい刺激をもたらすことを意識していきましょう。
パーソン・センタード・ケア

ここからはパーソン・センタード・ケアについて解説していきます。
パーソン・センタード・ケアとは
パーソン・センタード・ケアとは、認知症高齢者を一人の人として尊重してその人の視点や立場に立って理解し、ケアを実践しようとする認知症ケアの理念です。
認知症高齢者の状況は、一人ひとり異なります。
そして、認知症は、5つの要因から影響を受けています。
- ・脳の障害
- ・身体の健康状態
- ・生活歴
- ・性格傾向
- ・社会心理
その人の個別性をふまえ、また関わりを通してその人が今どのような体験をし、その人が今どのような体験をし、どう感じているかを周囲の人が理解し、支えようとすることが大切です。
私たちのケアの質により、認知症の人の状態を左右する
認知症の人のよい状態を持続できることは理想的ですが、反対によくない状態に陥ってしまうこともあります。
認知症の人のよい状態とよくない状態は、次のとおりです。
| よい状態 | よくない状態 |
| 喜び、楽しさを表す、リラックスしている、自分のことを話す、他の人を話をする、他者に愛情を表現する、人の役に立とうとする | 絶望・非常に強い怒り、深い悲しみ、不安・恐れ・退屈、身体的な苦痛、不快感、身体が緊張している |
よい状態が継続できれば、いわゆるBPSD・認知症の緩和や身体疾患の回復、在宅復帰や人間性の回復などポジティブな改善につながります。
反対によくない状態が続いてしまうと、BPSDの増加や認知症の悪化、ADLの低下や身体疾患の悪化など、マイナスな状況を導いてしまうのです。
認知症の人の状態は、私たちのケアの質により、よい状態もよくない状態になり得ます。
認知症の人の心理的ニーズは、大きくわけると次の5つです。
- ・くつろぎ
- ・共にあること
- ・たずさわること
- ・アイデンティティ
- ・愛、結びつき
認知症の人の声に耳を傾け、話をよく聴くことが大切です。
諦めずに感情を共有し、認知症の人に信頼できる人であるということを感じてもらうようにしましょう。
また、認知症の人のコミュニケーション能力を軽度〜重度にわけると以下になります。
- ・軽度:言語的な訴えができる
- ・中度:工夫すれば言語的な訴えがほぼできる
- ・重度:言語的な訴えができない場合でも、表情や行動から訴えをアセスメントできる
このように、重度であっても嬉しい・悲しいなどの感情表現をすることができるときもありますし、こちらのメッセージを受け取ることができる可能性があります。
認知症の人の訴えとBPSDにつながりやすい対応
認知症の人の心理的ニーズを無視した個人の価値を低める行為は、BPSDにつながりやすいです。
例えば、次のような対応です。
- ・怖がらせる
- ・ケアをするときにおどしたり怖がらせたりして無理に従わせる
- ・満たされない気持ちを訴えているときに、気づかないふりをして後回しにする
- ・急がせる
- ・能力や障害をまったく配慮せず早くケアを終わらせることを目指す
- ・非難する
- ・騙す、あざむく
- ・能力を使わせない
個人の価値を低める行為は、認知症の人の症状を悪化させます。
ケアを怖がったり拒否したりする人には、無理強いをするのではなく、誠実な思いやりをもって接することが大切です。
反対に個人の価値を高める行為は、次のとおりです。
- ・誠実である
- ・尊重する
- ・喜び合う
- ・必要とされる支援をする
- ・能力を発揮してもらう
- ・共感をもってわかろうとする
- ・個性を認めること
- ・リラックスできるペースで見守る
- ・一緒に楽しむ
- ・関わりを継続できるようにする
- ・共に行う
- ・思いやりを持つ
価値を高める行為は、認知症の人の心理的ニーズを満たします。
人としてイキイキとその人らしく生活するためのケアであるともいえるでしょう。
パーソン・センタード・ケアの実践への活用

パーソン・センタード・ケアを理解したら、現場でも実践していきましょう。
例えば、夜間頻尿の認知症高齢者に対し、頻回の排泄により転倒リスクが高いために、身体拘束の必要性が検討されているとします。
本人は、排泄障害のためくつろぎのニーズが満たされない。または、入院中に交流できる人がおらず共にあることへのニーズが満たされないと感じています。
そういった場合は、夜間、自分でトイレに行けるように室内で十分転倒予防をしたうえで、排泄動作のリハビリテーション等の自立支援の検討をしていきましょう。
転倒対策として、ポータブルトイレの工夫やトイレまで手すりや家具などで伝い歩きできるような工夫がよいでしょう。
また、くつろぎを満たすためのリラックスしたペースの排泄を意識していくことも大切です。
ケア中は、本人の排泄に関する苦痛を聞いたり、一緒に本人がしてほしい介助を聴き、心を通わせるあたたかい交流ができると理想的です。
まとめ

認知症の人は、記憶障害や実行機能障害によって、今までできていたことができなくなる不安を感じ、自信を喪失しながらも懸命に生きておられます。
本人の視点に立ったパーソン・センタード・ケアを取り入れ、安心感を与えられるようなケアを心がけていきましょう。
今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。