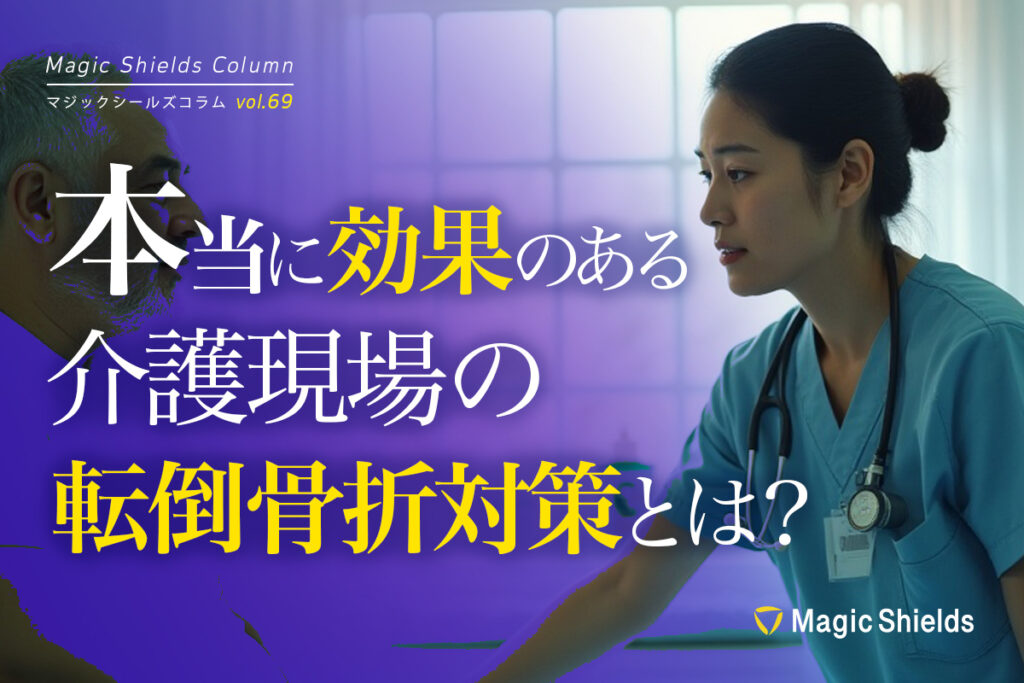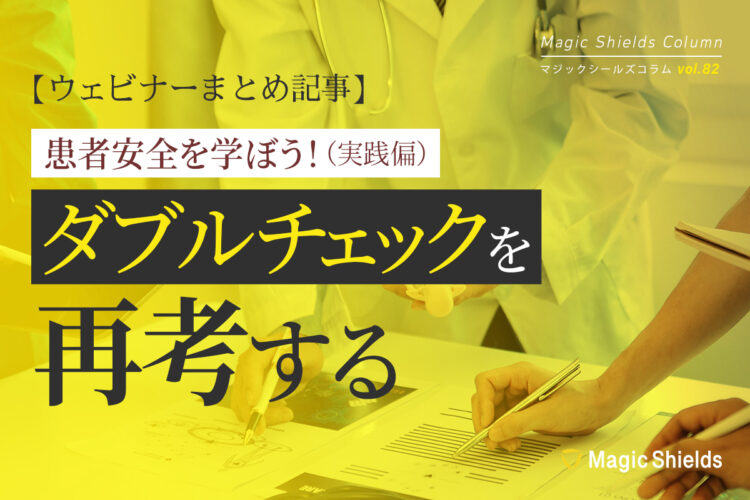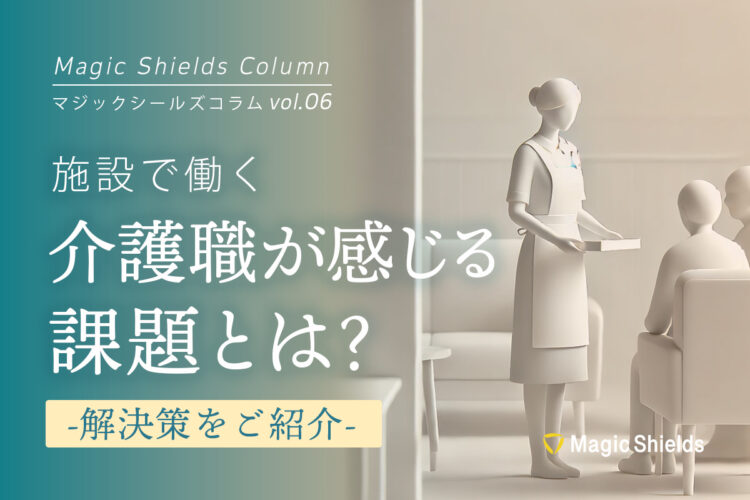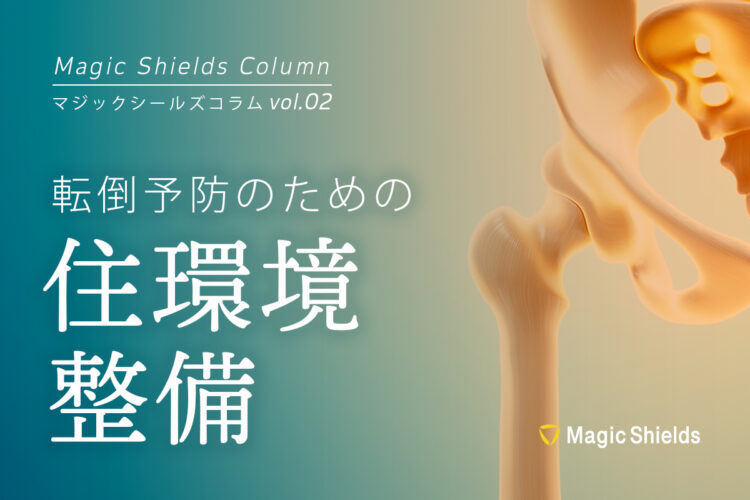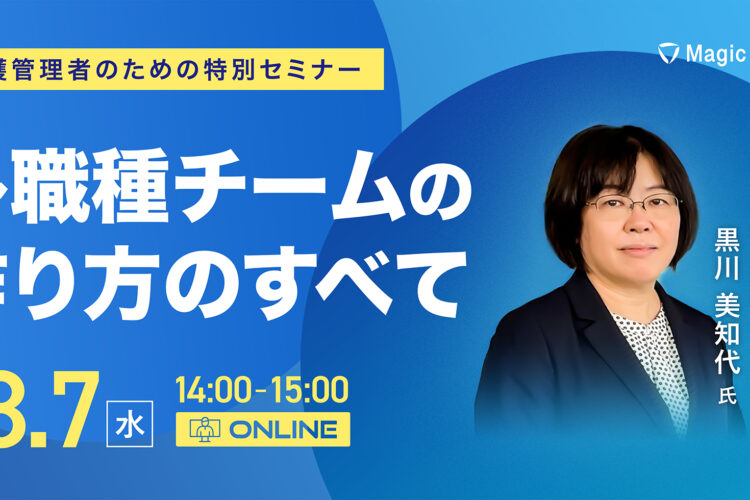目次
介護施設で「事故が起きる度に対策を見直しているはずなのに転倒事故が減らない」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
人員不足のために充分な対策ができなかったり、転倒骨折による入院で空室ができてしまったりすると、入居者様だけでなく施設側にとってもネガティブな影響を受けてしまいます。
それを防ぐためには、正しい対策の仕方を学んでおきたいところです。
今回のWEBセミナーは、メディカル・ケア・サービス株式会社 介護福祉士/介護支援専門員/修士(医療福祉学)である杉本様をお招きし、本当に効果のある介護現場の転倒骨折対策についてお話いただきました。
この記事では、その具体的な内容を紹介していきます。
転倒骨折入院により起こること

転倒骨折入院のあとには、一体何が起こるのでしょうか。
主に転倒で起こることは次のとおりです。
①転倒後症候群
高齢者が転倒してしまうと、その後に骨折などの大きな外傷がなくても、歩くことへの自信を喪失してしまう可能性があります。
自信を失い、「また転んでしまうのではないか」「もううまく歩けないのではないか」と思い込むと、外出に不安を感じ外に出たがらなくなってしまいます。
その結果、日常の活動量が低下し、生活不活発病につながってしまうのです。
②生存率の低下
高齢者の転倒・骨折はQOLの維持・向上に大きく影響します。
一般社団法人日本骨粗鬆症学会資料によると、80歳以上の大腿骨近位部骨折患者の1年半後の生存率は約50%であることが明らかになっています。
転倒骨折をすると完治までに時間がかかります。
ベッド上の生活や車椅子での移動により、活動量が減少し、その影響で食欲の低下・意欲の低下が起こってしまいます。
その結果、身体的や精神的、さらには社会的な悪化につながり生存率が低下してしまうのです。
転倒を起こさないことが重要

転倒骨折が発生すると、転倒骨折が起きるとご利用者様本人も辛い思いをし、また「事故を起こしてしまった」という後ろめたさから職員のモチベーションも下がってしまいます。
さらに、転倒骨折入院で空室ができ、退院後に戻ってこれたとしてもご利用者様の状態は重度化してしまう可能性もあります。
そうすると、施設の運営にも影響が出てしまうのです。
全てネガティブなことにつながり、患者様やご家族、さらに施設側にとっても不利益になります。
そういった事態を防止するために、転倒事故を起こさないための対策が大切です。
転倒を起こさないために

「対策を立てているのになぜまた同じ事故が起こるのか」と思っている人は多いかもしれません。
本当に効果のある具体的な対策をすると、転倒骨折入院を防ぐことができます。
実際にメディカル・ケア・サービス株式会社の38ホームで転倒骨折の対策を実施したところ、1年間で約30%入院件数を削減することができました。
また入院日数に至っては、1年で59.9%削減することができています。
大幅な削減ができた理由は、事故の正しい原因分析をしていたからです。
ここからは、本当に効果のある転倒骨折に対しての具体的な対策について解説していきます。
問題と原因と分けて考える思考のマインドセットと正しい事故報告書
事故が起きたときに、問題点と原因を分けて考えることが大切です。
なぜなら、問題点と原因は別物であり、ここが整理できないと本当に効果的な事故対策が導き出せないからです。
例えば、次のような事例で問題点と原因を考えたとき、分け方は以下のようになります。
【事例】
出勤予定の鈴木さんが体調不良で欠勤しました。
田村さんは鈴木さんの分まで一生懸命働きました。
昼食の服薬介助はダブルチェックをするルールになっています。
田村さんは疲れていました。
田村さんは糖尿病を持病にしているご利用者様への昼食の薬のダブルチェックの投薬を忘れてしまいました。
- ・問題点:投薬を忘れた
- ・原因①:ダブルチェックをしなかった
- ・原因②:田村さんが疲れていた
- ・原因③:鈴木さんが休んだ
人は起きた事故に対しての原因を直感的にいくつかあげてしまいます。
その結果、正しい事故対策ができず、同じような事故が頻発します。
問題点は起きた事実そのもののことです。
事故の問題点は一つしかないため、その他のことは全て原因になります。
このように、まずは問題点と原因を切り分けることが大切です。
そのうえで、可能性のある原因はすべて書き出しましょう。
原因をすべて書き出したら、問題点に対して直接的な原因の順番に並び替えます。
問題点と原因を分けて、直接的な原因から解決策を考えていくとスムーズです。
また、事故報告書についても、上記の考え方を取り入れていくと解決策の考案がしやすくなります。
そのためには、正しい事故報告書のフォーマットに切り替えていくことがおすすめです。
一般的な事故報告書と正しい事故報告書に用意された項目の違いは、次のとおりです。
| 一般的なフォーマット | 正しいフォーマット | |
| 対象者氏名や要介護度などの前提情報がある | 〇 | 〇 |
| 状況を記載する欄がある | 〇 | 〇 |
| 問題点を記載する欄がある | × | 〇 |
| 原因を記載する欄がある | △(ひとつしか書く欄がない) | 〇(複数書ける欄がある) |
| 原因を細分化し分析できる欄がある | × | 〇 |
| 今後の対策についての欄がある | 〇 | 〇 |
一般的な事故報告書と正しい事故報告書の大きな違いは、問題点と原因を切り分けて考えられる欄があるか、または原因を詳細に分析できる欄があるかです。
正しい事故報告書の記載項目は、以下になります。
- ・事故発生日時
- ・次回モニタリング日
- ・対象者氏名
- ・要介護度
- ・歩行状態
- ・状況
- ・問題点
- ・受診結果
- ・原因
- ・直接的な原因順(短期・長期)
- ・対策(短期・長期)
上記の項目をあらかじめフォーマットに組み込んでおくことで、事故が起こったときにいくつかの原因を分析しながら報告書に記載することができます。
また、対策自体が正しいのかのモニタリングをすることも大切です。
事故が発生した後、対策を決めたら、それが正しいかどうかのモニタリングを行うようにしましょう。
再発防止のロードマップ
再発防止のために対策を行う場合、ロードマップが重要になります。
具体的には、次の3つに分かれます。
- ・超短期的:すぐに結果が出るもの
- ・短期的:物品購入すれば実施できるもの
- ・長期的:今日、明日から取り組むことはできるが結果はすぐに出ないもの
ここからは3つの対策について、具体的に解説していきます。
超短期的な対策
超短期的な対策は、ルール変更などが該当します。
例えば、見守り方法や意識改革などです。
介護施設で挙がりやすいのが、こちらの対策だと思います。
しかし、ルール変更や職員の意識改革などの超短期的な対策だけでは、同じ事故が再発する可能性は高いです。
なぜなら、効果分析や定義が曖昧で難しいため、モニタリングがしにくいためです。
そのため、短期的・長期的な対策も実施していくことで、より効果的な対策へとつなげることができます。
長期的な対策
長期的対策としては、転倒しても骨折しない身体づくりが該当します。
具体的には、脱水改善と低栄養改善です。
水分や栄養が不足すると、意識障害や気分にムラが生じます。
また、覚醒水準や運動能力が低下し、転倒骨折につながりやすくなります。
それを防ぐためには、水分や栄養に着目することが大切です。
体内水分の1%ずつ水分摂取量を増量したり、食事時にタンパク質を摂るように意識したりするとよいでしょう。
短期的な対策
短期的な対策は、環境整備や物品の用意になります。
転倒を防ぐための環境整備・商品は、次のとおりです。
- ・ヒッププロテクター
- ・衝撃吸収材
- ・片手でつたえる環境をつくる、手を置ける場所をつくっていく
手すりについてはご利用者様により身長が違うため、教養部では腰部から胸部の平均の高さの物が必要になります。
また、転倒をしても骨折しないための環境づくりには、骨折リスクを防いでくれる衝撃吸収材「ころやわ」もおすすめです。
ころやわについては、次の章で詳しく解説していきます。
転んだ時だけ柔らかい床・マット「ころやわ」

ころやわの採用実績は現在600施設以上であり、多くの施設に導入されています。
ころやわは、歩行快適・衝撃低減の両立を実現した床・マットです。
転倒時には床面が凹み、骨折や外傷のリスクを低減してくれます。
また、通常時は硬いため、安定して快適に歩くことができます。
転倒をすべて防ぐことは難しいため、転倒リスクに悩む福祉・医療事業者の方は多いでしょう。
ころやわなら、「転んでも安心できる環境づくり」の実現が可能です。
介護施設入居者の転倒骨折による入院数を削減したいなら、ころやわの導入がおすすめです。
まとめ

転倒骨折による入院を防ぐためにも、正しい対策方法を実践していきたいところです。
今回のウェビナーで紹介された方法を、実践し、転倒防止対策をしていきましょう。
また、転倒による骨折の予防ができる「ころやわ」の導入も、ぜひ検討してみてください。
株式会社Magic Shieldsでは、今後もさまざまなウェビナーを開催していきます。
今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。