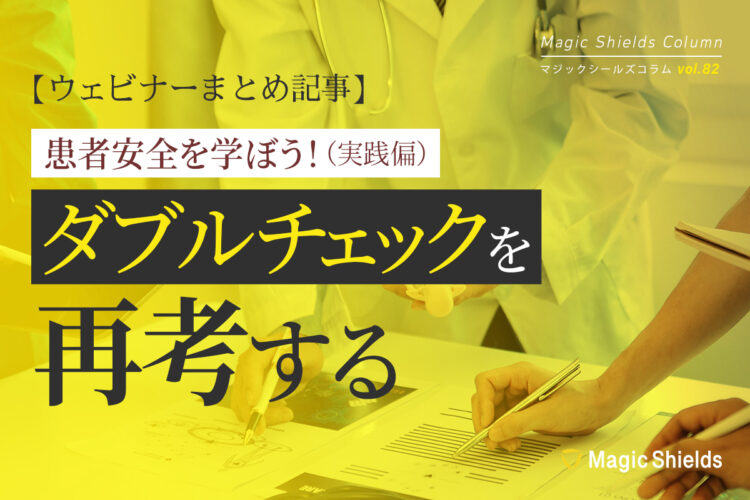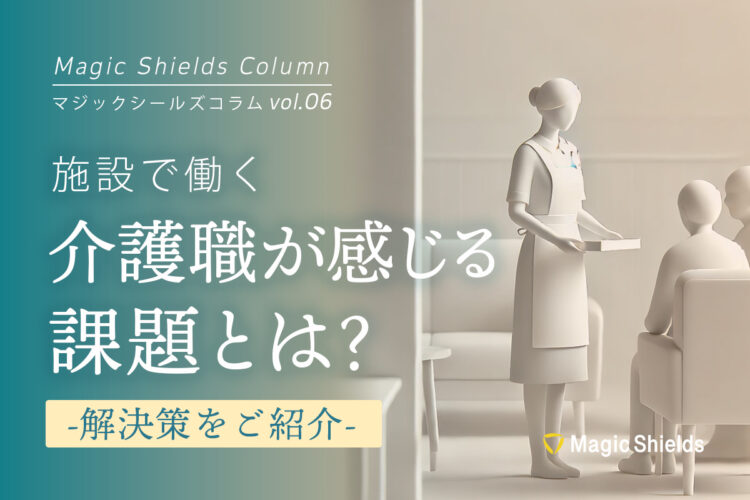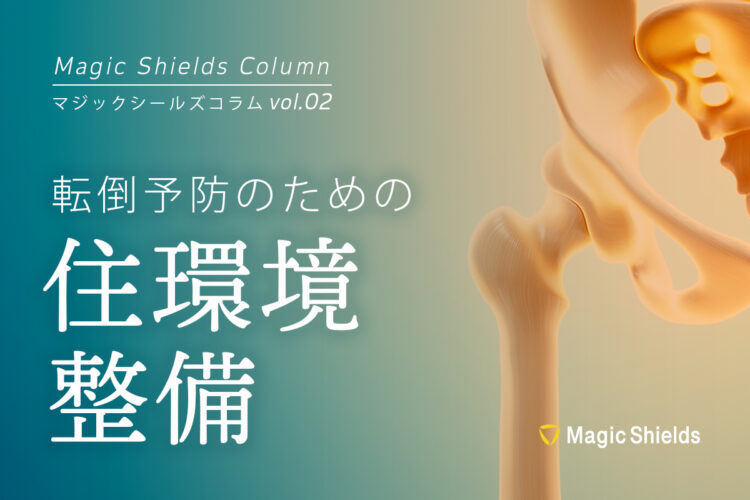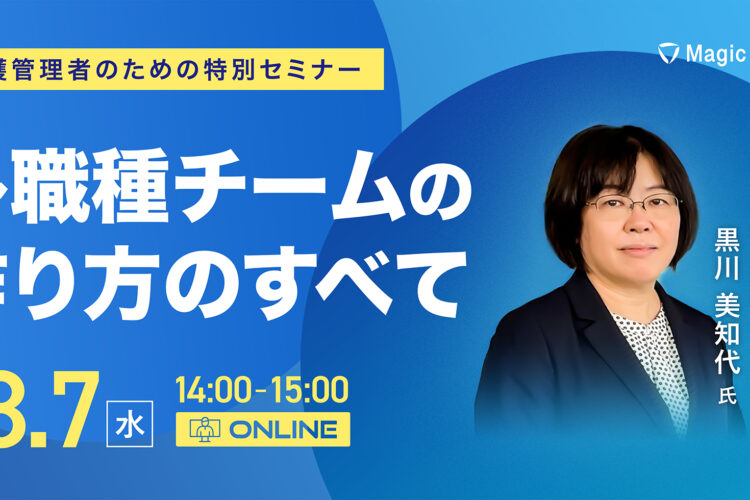目次
「医療安全管理者に就任したが何をしたらよいかわからない」「医療事故を防ぐために多職種で協力する体制を強化したい」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
株式会社Magic Shieldsでは、患者安全のための品質管理手法についてのウェビナーを開催しました。
今回は、名古屋大学医学部附属病院 患者安全推進部 市川 真由美様より、医療安全管理者の方に向けた、患者安全のための品質管理手法ついてお話いただきましたので、この記事では、その内容について詳しく解説していきます。
医療現場で問題解決の手法が大切な理由

WHO患者安全カリキュラムガイドのトピック7には以下の内容が記載されています。
ここ数十年で膨大な数の委員会や業種団体から医療の安全と質を改善するための推奨策が数えきれないほど提唱されてきたが、その中でわかったのは、査読付き医学雑誌にエビデンスを発表するだけでは医療従事者の行動は変容させられないということであった。
出典:WHO患者安全カリキュラムガイド
また、カリキュラムガイドには、ギャップに対処すべく一連の改善手法が考案されています。
それは次のとおりです。
- ・問題の特定
- ・問題の測定
- ・問題解決のための介入方法の考案
- ・介入の有効性の検討
上記、問題解決の4つの段階で活用されるツールが医療専門家に提案されてきました。
医療業界で安全の質向上を目指し、問題解決をしていくためにはエビデンスを発表するだけでなく、その手法が重要であることがわかります。
そこで、今回は、品質管理における問題解決のための手法について紹介していきます。
患者安全活動のループ

PDCAサイクル(方針管理)の中で特に難しいのがプランです。
しかし、問題解決において特に大切なのがプランになります。
建築に例えるなら、必要に応じて増改築を繰り返した建築よりもきちんとした設計に基づく基礎の確実な高層建築で暮らしたいはずです。
しかし、医療業界では現状、有害事象が起きた後のさまざまな改善策を継ぎ足しで実施していく形になっている傾向にあります。
安全管理を行ううえでは、継ぎ足しの改善策よりも根本的な見直しが大切です。
それを改善していくためには、手法とツールが必要になります。
そこで、産業界で用いられる「品質管理手法」(問題解説手法)を医療現場に応用していくことがおすすめです。
品質管理における問題解決手法 8ステップ

医療現場において、安全の質向上のための問題解決はよく課題にあげられると思います。
品質管理における問題解決手法には8つのステップがあります。
問題とは、あるべき姿と現状のギャップです。
そのギャップを埋めていくことが問題解決になります。
ここからは、品質管理における問題解決手法の8ステップについて解説していきます。
ステップ1:テーマ選定と問題の明確化
何をテーマとして選定するかが問題解決のスタートです。
まず、困っていること、解決したいことを洗い出しましょう。
洗い出した後は、解決すべき困りごとに優先順位をつけます。
以下の項目を意識してみると、スムーズに優先順位がつけられます。
- ・重要度:そのことの影響が及ぶ範囲は大きいか?
- ・緊急度:すぐに手を打たないと重大な結果を招くか?
- ・拡大傾向:放置した場合、その影響の範囲や大きさは拡大するか?
問題の影響が及ぶ範囲や結果について、十分に考慮し優先順位をつけていきましょう。
また、本来あるべき姿を最初にはっきりさせておくことも大切です。
ステップ2:現状把握
次に、データから抽出された現状把握をしていくことが大切になります。
エビデンスを調査することで、多角的な視点で問題把握ができるためです。
まずは結果系の現状把握をしましょう。
結果系の現状把握とは、データから抽出された現状把握になります。
思いついた一つの視点にとらわれることなく、いろいろな視点で層別してみましょう。
例えば、以下のような層別です。
- ・種類別、影響度別
- ・平日・土日別、時間帯別
- ・性別、年齢別
- ・部署、部位別
さまざまな視点で比較してみると、重点的に問題を発見することができます。
ただし、すでにあるデータの分析だけでは、机上の空論になってしまう可能性もあります。
そこで、大切なのが、要因系の現状把握です。
要因系の現状把握は、アンケート結果やヒアリング等から導かれる要因の一つと考えられる現状把握です。
問題が発生するまでのプロセスを明確にするための現状把握になります。
要因解析する前に、現状把握の深堀ができます。
現場の実態がどのようになっているのか、実際に現場で検証することも大切です。
事実を大切にし、盲点なく物事を客観的にみるためです。
実際に問題が起こった現場に足を運び、実際の現場で自分の目と足で事実を確認しましょう。
ステップ3:目標設定
ステップ2で選定した重要特性に対する目標を立てます。
「あるべき姿」に向けて、まずは目指す目標を立てましょう。
あるべき姿とは実現したい姿ともいえます。
また、目標設定のメリットは次のとおりです。
- ・設定レベルにより必要な対策やスケジュールがみえてくる
- ・関係者のメンタルモデルが一致するチームワークがよくなる
- ・効果確認の基準となる
目標設定は具体的で、関係者が取り組みたいと思えるような挑戦的な目標を設定することが理想的です。
また、達成することで最終的にあるべき姿にたどり着けそうかについて、イメージしておくことも大切になります。
目標は「いつまでに」「なにを」「どれだけ」などの要素を入れて、定量的に表現するようにしましょう。
ステップ4:要因解析
要因解析とは、原因と結果の関係を明らかにすることといわれています。
つまり、あるべき姿と現状とのギャップの要因(原因)を明確にすることです。
以下の手順で進めます。
①要因を洗い出す
まずは要因を洗い出します。
「なぜ」の観点からブレインストーミングを用いて、多くのスタッフから意見を集めましょう。
現状把握で得た情報も反映させるとよいでしょう。
②洗い出した要因を整理分析します
次に、洗い出した要因を整理分析します。
要因の整理のために、さまざまな図を作成することがおすすめです。
例えば、以下の図を作成してみましょう。
- ・特性要因図
- ・親和図
- ・系統図
- ・関連図
上記のような図を利用することで、主要因から真因を追求することができます。
また、要因を掘り下げるポイントは以下になります。
- ・因果関係を確認する
- ・具体的に記載する
- ・対策が見えるまで掘り下げる
- ・意識の要因は「さらになぜ」を掘り下げる
- ・最後は自責で掘り下げる
導き出した真因を改善することで、最初に揚げた問題を解決できることを論理的に説明してみましょう。
論理的に説明できたら次のステップに進みます。
ステップ5:対策立案
ステップ4で特定した真因に対し、対策案をまずはたくさん考えましょう。
できる、できないに関係なく、ここではより多くの対策案を出していきます。
そして、たくさん対策案を出した後は、以下の基準で絞り込みます。
- 効果:対策により真因を解決し、目標を達成できるか
- リスク:対策を行う際に想定外のこと、不具合が起こる可能性はないか
絞り込みをする際には、効果やリスクに着目し決定していくことが大切です。
「できる」「やりたい」ではなく、目標を達成するために必要な対策について絞り込むようにしましょう。
対策立案・実施計画は、5W+1Hを踏まえて、具体的に考えます。
「誰が」「いつまでに」「どこで」「何を」「どのように」など、具体的にわかるように表現しましょう。
対策実施後の評価方法も、この段階で考えておくことが理想的です。
ステップ6:対策実施
対策実施のポイントは、実施計画と進捗の見える化です。
実施の際にはガントチャート等を用いて、誰がいつまでに何をするか、どこまで進んでいるかを一目でわかるようにしておきましょう。
ステップ7:効果確認
ステップ6の対策実施の結果と取り組み過程を、振り返りましょう。
結果はすでに過去のことであるので、今後に活かせるのは「取り組み過程」になります。
特に次の2つを振り返っていきましょう。
- ・成功要因:上手くいった秘訣、今後も続けたいこと
- ・失敗要因:次回は止めること、改善すべきこと
ここでの結果で次のフローが以下のように分かれます。
- ・結果はよかったけど、取り組み過程がよくなかった→要因の見直し「ステップ4:要因解析」に戻る
- ・結果がよくなかったけど、取り組み過程はよかった→対策立案の見直し「ステップ5:対策立案」に戻る
- ・結果も取り組み過程もよくなかった→継続した実行「ステップ6:対策実施」に戻る
- ・結果も取り組みもよかった→「ステップ8:標準化」に進む
効果確認をしながら、次に進むべきステップを検討していきましょう。
ステップ8:標準化
効果確認で結果・取り組みもよかった場合は、結果を出し続けるために、「良い取り組み」を定着させることが大切です。
次の2つを意識して定着化を図っていきましょう。
- ・標準化:いつだれが同じことを実施しても、同じようにできるような仕組みをつくる
- ・横展開:標準化した内容を拡大・共有していく
また、達成し続けるために、業務・作業の最適な方法を可視化したり、やり方を広めたりすることも大切です。
広めたり、可視化したりすることで、どの職員でも実施しやすくなるためです。
その他、よい結果を継続させていくために、目標の達成状況を把握する仕組みをつくるようにしましょう。
SDCA(日常管理)サイクルとは
SDCAとは、問題発見からのサイクルのことを指します。
標準化された方法を実施していくうえで大切なサイクルです。
具体的には、以下4つのサイクルをローテーションで実施していきます。
- ・Stanndardize 標準化:業務や作業の最適な方法を標準として設定する
- ・Do 実施:標準化された手順に従って業務を行う
- ・Check 評価・異常への気づき:実行した結果を確認する
- ・Action 改善:必要な改善・是正処置をとる
ステップ8まで実施した後も、SDCAサイクルをローテーションで実施していく必要があります。
問題解決手法で使用する主なツール(道具)

ここからは、データの整理と見える化のために活用できるツールについて、紹介していきます。
①チェックシート(漏れをなくす)
チェックシートは、マトリックスのような二軸の表を示します。
データの記録や集計、整理を容易にして、不具合の出現状態を把握する手法になります。
現状把握のためによく用いられるシートです。
②パレート図(層別)
パレート図は、棒グラフと折れ線グラフを用いて重要特性を把握する手法になります。
問題となっていることを現象別に分類し、多い順に並べることで重要な特性がわかります。
主要な問題を分析したいときに用いられるシートです。
③特性要因図
特定要因図は、要因解析に活用できるシートです。
結果と原因の関係を表した図であり、問題の原因を検討し、問題の原因を整理する際に有効です。
④管理図
実線と点線、折れ線グラフなどを用いたシートです。
異常が確認できる手法になります。
自然のばらつきと異常原因のよるばらつきを区分して、工程の状態が正常化以上かを客観的に判断ができます。
⑤散布図
対になった2つの特性を横軸と縦軸とし、観測値を1組ずつ打点した図です。
散布図を用いることで、二つの関係がわかるようになります。
上記5つの他、ヒストグラムやグラフ、プロセスフローチャートなども問題解決において、よく使われる手法です。
活用方法
問題解決のための8つのステップのなかで、上記のツールを活用することができます。
どこで、活用できるかについて以下の表にまとめました。
| 8つのステップ | 良く使われる道具・手法 |
| 1:テーマ選定 | |
| 2:現状把握 | パレード図、P管理図、フローチャート、チェックシート、相関図、多変量解析 |
| 3:目標設定 | |
| 4:要因解析 | 特性要因図、RCA(根本原因分析) |
| 5:対策立案 | |
| 6:対策実施 | |
| 7:効果確認 | パレード図、P管理図、統計学的検定 |
| 8:標準化 |
ツールを用いて問題解決に取り組むことで、効率化や正確性をより高めることができます。
表については、アーカイブでさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
品質管理のために適切な問題解決手法を応用していくことで、より正確で効率的に目標に向かって対策実施を進めていくことができます。
患者様のために、質の高い医療サービスを提供していくためにも、問題解決のためのフローを今一度見直していきたいところです。
今回の記事を参考に、現場内でぜひ8つのステップを実践してみましょう。
また、今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。