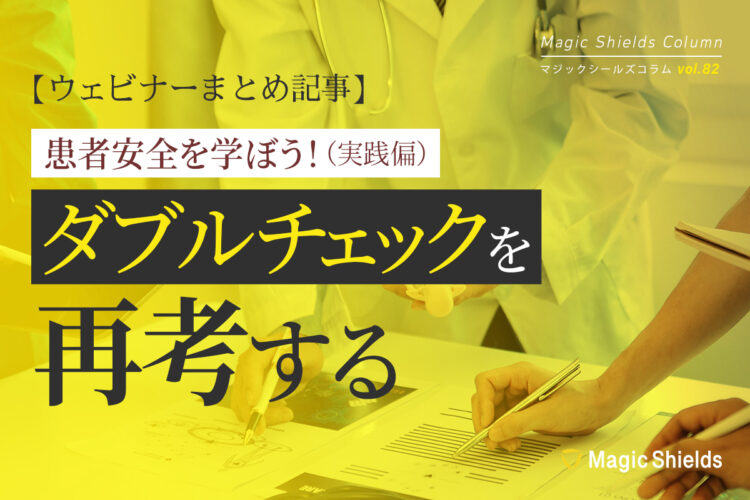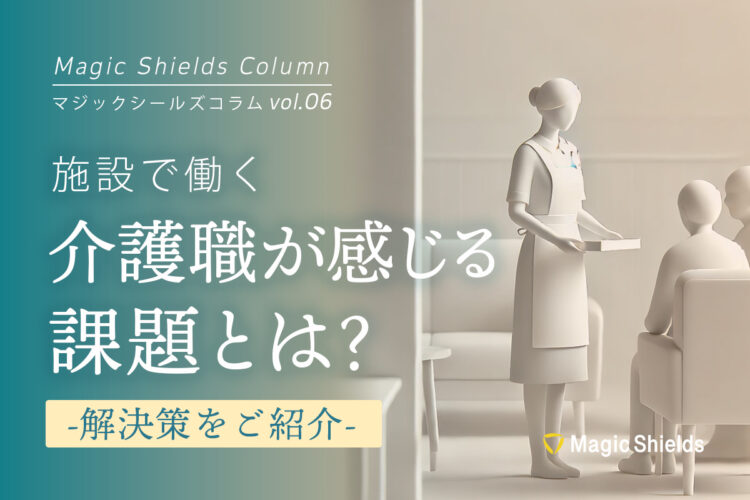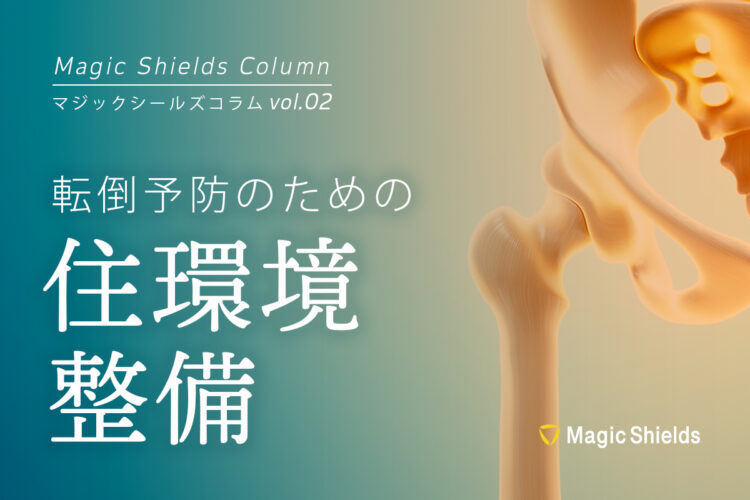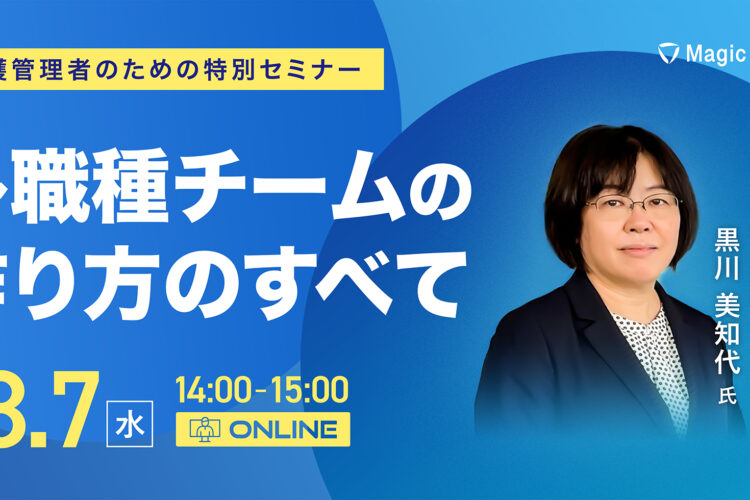目次
医療現場で「身体拘束を減らしたい」「認知症患者のケアで困っている」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
株式会社Magic Shieldsでは、看護管理者の皆様に向け認知症患者様の転倒対策を考えるWEBセミナーを開催いたしました。
今回は、認知症看護認定看護師のパイオニア的存在である梅原様に、認知症患者様の転倒対策を考える上で大切なエッセンスをお話いただきました。
この記事では、WEBセミナーでお話しいただいた内容を紹介していきます。
身体拘束廃止の強化が推進されている現在

令和6年に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が設立されましたが、この基盤となるのが高齢者の尊厳を損なう不当な身体拘束を廃止・防止しようという考え方です。
そして、高齢者の尊厳をいかに保持するか、自立支援ができるかが大きなポイントとなります。
身体拘束(行動抑制)とは

厚生労働省「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限」では、身体拘束について「衣類または綿入り帯等を使用して、一時的に患者様の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」としています。
また、身体拘束は、以下3要件を満たす場合に実施されています。
- 切迫性:自己・他者の生命や身体の危険が及ぶ可能性が高い場合
- 非代替性:身体拘束以外に代替するケア方法がない場合
- 一時性:一時的なものである場合
上記、3要件を全て満たす場合、医療現場では致し方なく身体拘束が実施されていることもあるというのが現状です。
身体拘束の実施を検討する場合、前提として上記の3要件を満たしている必要がありますが、課題となりやすいのが「一時性」の部分です。
実施当初は「一時性」であったはずなのに、身体拘束によりリスクが回避されると、一時的ではなくそれが継続的に行われてしまうというケースもあります。
出典:昭和63年4月8日 厚生省告示 第129号における身体拘束の定義
参考:介護施設・事業所などで働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き
認知症看護の困難感と課題
必要以上に身体拘束が行われてしまう背景には、以下のような問題があります。
- 疾患の理解不足:疾患の理解不足、症状・BPSDへの対応不足
- 経験の共有不足:経験不足・蓄積がない、ジレンマ・否定的感情
- 管理:人員不足、システムの不備、連携不足
上記により、身体拘束が常態化してしまうのです。
また、「どうしたらよいかわからない」「すべきことはわかっているけどジレンマを抱えそれが慢性化してしまっている」ということにより、問題意識が薄れ業務改善への意欲が低下してしまうという負の連鎖に陥ってしまうこともあります。
身体拘束の弊害
身体拘束には、さまざまな弊害があります。
主な弊害は、大きくわけて以下3つです。
- 身体的弊害:関節の拘縮、筋力低下、食欲の低下
- 精神的弊害:人間の尊厳の侵害、認知症の進行、家族の罪悪感
- 社会的弊害:介護保険施設等に対する社会的な不信・偏見、医療の増加による経済的損失等
2次的な弊害として上記のさまざまな理由により、体力が消耗し、萎縮等により転倒したり、心理症状として幻想・妄想を引き起こしたりすることもあります。
また、さまざまな身体拘束の弊害により、結果的に高齢者の「死期」を早めてしまう可能性も。
身体拘束は、高齢者のQOLを根本から損なう危険性が高い行為なのです。
行動抑制とストレスの関係
人間は拘束をされると、思うように動けないことから、ノルアドレナリンの分泌が亢進します。
それにより、以下のような流れで身体的・心理的に悪影響を及ぼします。
- 攻撃性が増して切れたりイライラする
- ハイテンションになる
- やがて鬱傾向になる
- 小さな事が気になる
- 血圧が上昇する
血圧が上昇することで、高血圧症などの生活習慣病につながるリスクもあります。
身体拘束の理由

身体拘束は誰でも、進んで行いたいものではありません。
しかし致し方なく実施する背景には、以下のような看護師の声があります。
- ・点滴や酸素チューブ、ドレーン類を外すため
- ・安静の指示を守れないため
- ・一人で歩行し転倒のリスクがあるため
- ・落ち着きがない、興奮するため
- ・攻撃的な行動や言動があるため
医療やケアの安全な提供をしたい一方で、上記のような懸念があるとジレンマを抱えながらも身体拘束をせざるを得ない状況にあることがわかります。
ハイリスクであり、また再発を繰り返す恐れもあることから、リスクマネジメントが困難になり、結局、身体拘束を実施してしまうのが現状です。
認知症の特徴
身体拘束を実施してしまう背景には、認知症の特徴も大きく影響しています。
そこで、ここからは、認知症の主な特徴を解説していきます。
特徴①:ニーズの把握が困難
認知症は、ニーズの把握が難しいのが特徴です。
認知症4大疾患といわれている疾患それぞれに、コミュニケーション障害につながる症状があります。
例えば、アルツハイマー型認知症の場合は喚語困難、前頭側頭型認知症の場合は進行性非流暢性失語喚語等があり、患者様のニーズに沿ったケアがしたくても、職員側が患者様の心の状態や意向を把握することが難しいのです。
特徴②:運動機能の維持が困難
認知症の特徴の二つ目は、運動機能の維持が困難ということです。
認知症は進行に伴って、運動機能が低下していく傾向にあります。
そのため、転びやすくなったり、日常生活動作の自立の能力が低下したりします。
さらに認知症症状に加え、高齢者特有の疾患があるケースも多く、高度なケア・技術が求められるのも現状です。
原因から考える対応方法

身体拘束をしない安全対策を考えるとき、大切なのは行動の原因です。
ここからは、行動分析学を応用してできる安全対策を事例を紹介しながら解説していきます。
行動に影響を与える3つの原因
機能主義心理学のWilliam James氏は、「人間の考えや行動には何らかの意味がある」ということをいっています。
行動とは、以下全てを網羅したことを指します。
- 見る
- 聞く
- 話す
- 持つ
- 感じる
- 考える
行動に影響を与える3つの原因は、次のとおりです。
- 遺伝的要因:人間としての身体構造・働き
- 過去の経験:人生史
- 現在の環境
なんからのきっかけから行動をし、よい結果が得られると次も同じ行動をする可能性が高くなります。
逆に行動をしてもよい結果が得られなかった場合は、次は同じ行動をしなくなる傾向にあります。
行動分析学を応用
行動分析学を応用して、安全性を確保しながら患者様の尊厳を大切にしたケアを考えていきたいところです。
次のようなケースを事例として、対応策を考えていきましょう。
- 「家に帰る」と訴え続ける患者様
- 職員の制止を払いのけ患者様が歩き出す
- 患者様がバランスを崩して転倒する
上記は、医療・介護現場でよくあるシーンではないでしょうか。
上記のようなケースを「リスクがあるから」といって身体拘束につなげてしまうことは避けたいところです。
そこで、「きっかけ」を変えていくことにシフトしていくことがおすすめです。
行動の理由を環境から検討するようにしましょう。
上記の行動をする患者様は、今いる場所の居心地の悪さを感じている可能性が高いです。
居心地の悪さは、以下の要因が重なって感じているかもしれません。
- 環境要因:リロケーション、ショック、ダメージ
- 身体的要因:身体的苦痛
- 心理的要因:不安、恐怖
上記のような不安や苦痛を少しでも取り除くことで、患者様に対しての望ましい行動につながり、ADLの自立支援や自分でできることを増やすことができるようになります。
リスクがあるからといって抑制するのではなく、できたときの達成感をもっていただくケアを実施していくことが理想的です。
きっかけを変えることでの2つの対応例
ここからは具体的な事例を用いて、きっかけ(先行条件)を変えることで、身体拘束のない安全対策につなげていく方法を解説していきます。
事例1:点滴や酸素チューブ、ドレーン類を外す
例えば、点滴や酸素チューブ、ドレーン類を外してしまう患者様を例に挙げて対応策を考えてみましょう。
点滴や酸素チューブなどを外してしまうきっかけ(先行条件)は次のとおりです。
- 何かに引っ張られて思うように動けない
- なんだか腕やわき腹あたりがチクチクする
- 鼻がむずむずする、鼻が乾いて仕方がない
- 口の周りがなにかに覆われて息苦しい
このようなきっかけにより「これを取りたい」と考え、刺入部やルートを触り続けたり、ルートを意識せずに行動したりした結果、ルートを抜いてしまうということが考えられます。
上記のような場合でも、きっかけを変える思考が大切です。
具体的には、次のような対応例があります。
- 活動を妨げない長さや固定方法を検討する
- 頻回な訪室を行い、わかりやすい声掛けや対話、観察をする
- 安心できるような柔らかなまなざしで対応を行う
- 鼻がかゆくないか、かんそうしていないかを丁寧に確認・ケアする
- 皮膚や耳の心地よいフィット感につながるケアを考える
丁寧に様子を伺い、観察を続けていくことで患者様の不快感を取ってあげるようなケアにつながります。
このような根本を見直す対応を実施し、拘束しなくてもリスクが低減できるように考えていくことがポイントです。
事例2:安静の指示を守らず一人で歩くことで転倒・転落してしまう
安静の指示を守らず、一人で歩きたがる患者様もいるでしょう。
こういった場合にも、すぐに身体拘束の対応に直結させることなく、きっかけの見直しをしていくことが大切です。
安静にしたほうがよい患者様が、その言いつけを守らず一人で動いてしまうきっかけは、次のとおりです。
- トイレに行きたいと思う
- 家で子どもが待っていると思う
- いつもの散歩に行きたいと思う
- 歩けなくなるのではないかと思う
このようなきっかけにより、トイレの場所や出口を探す・座る・立ち上がる・散歩に行こうと靴を履くなどの行動を行います。
その結果、歩き出して転倒したり、病状が悪化してしまったりという二次的障害につながります。
上記のような場合は、患者様と一緒に過ごす時間を大切にし、患者様の想いを聞くということが重要です。
また、きっかけを変えるためには、以下のような対応がおすすめです。
- ルート類やおむつをみてもらう
- ゆっくりと簡単な説明にする
- 排泄パターンを観察する
- さりげない声掛けを行う
- 思いを伺える環境を用意する(家族のメモや写真、メッセージなど)
- 可能な範囲で活動を支援する
身体拘束をしない形で、事故防止に対して最善をつくすということがポイントです。
患者様の尊厳を守ったケアを実施していきましょう

医療現場で、事故をゼロにするのは困難です。
そして、身体拘束は安全を担保できるものではありません。
身体拘束の神話を解き、医療を提供する場だからこそ、患者様の生活を見据えたケアが大切です。
患者様の安全を確保する対策を、再検討するようにしましょう。
安全の確保は、本当に身体拘束をすれば可能なのか、また安全対策のためにどのような方法があるのかを考えることが大切です。
専門職チーム活動やAI機能の導入、予防用具の活用を検討していくとよいでしょう。
また、看護の視点を見直すこともポイントです。
特に以下のことに着目するようにしましょう。
- ・患者様の視点からニーズを推測し看護を行う
- ・環境面からの介入を再検討する
- ・患者様の自尊感情を高め、自分でできることを増やす
対策は、明確な方針に基づく具体的な目標設定が重要になります。
患者安全に基づき、患者様の視点で考える組織づくりに皆で取り組むことが大切です。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
医療現場で安全性を担保しながら身体拘束を廃止していく考えは、重要な一方で、難しい課題でもあります。
しかし、患者様の尊厳を守ることを重視した場合、身体拘束の廃止はより大切になってきます。
記事を参考に、患者様の行動の原因を分析し、適切な対応を皆で考えていきましょう。
今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方は、ぜひアーカイブ動画をチェックしてみてください。
また、株式会社Magic Shieldsでは、定期的にさまざまなウェビナーを実施しています。
医療・介護現場の悩みの解決の糸口となるようなウェビナーをこれからも開催していきます。
興味のある方はぜひご参加くださいませ。
医療・介護現場の悩みの解決策をみつけるきっかけにしていきましょう!