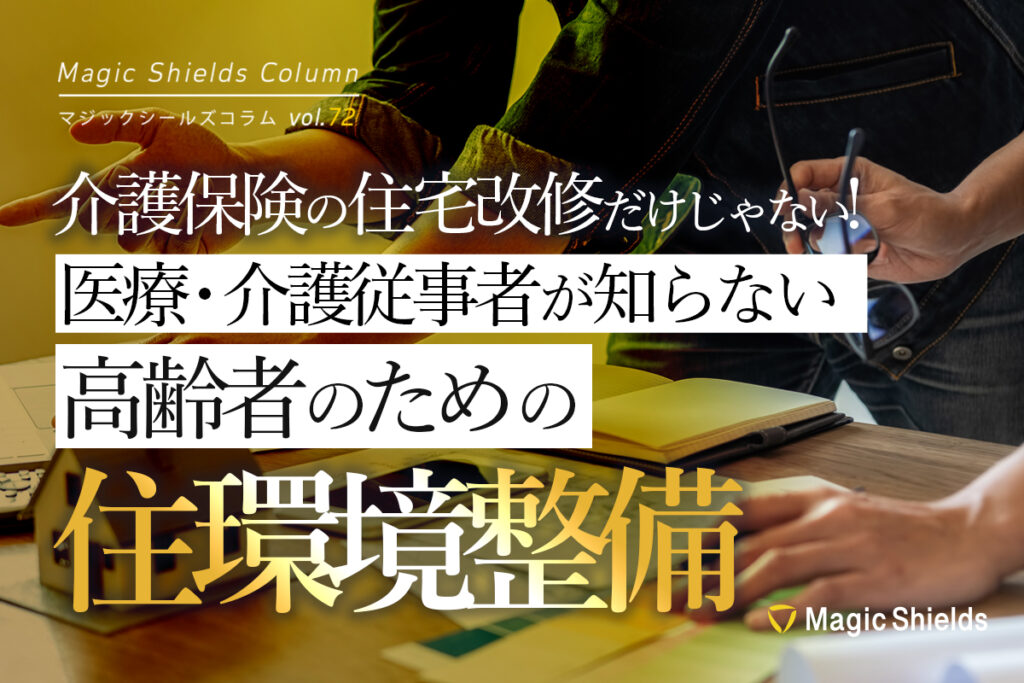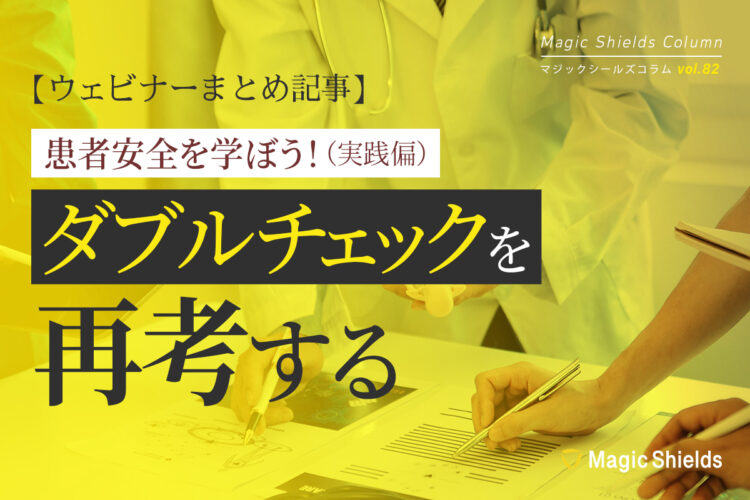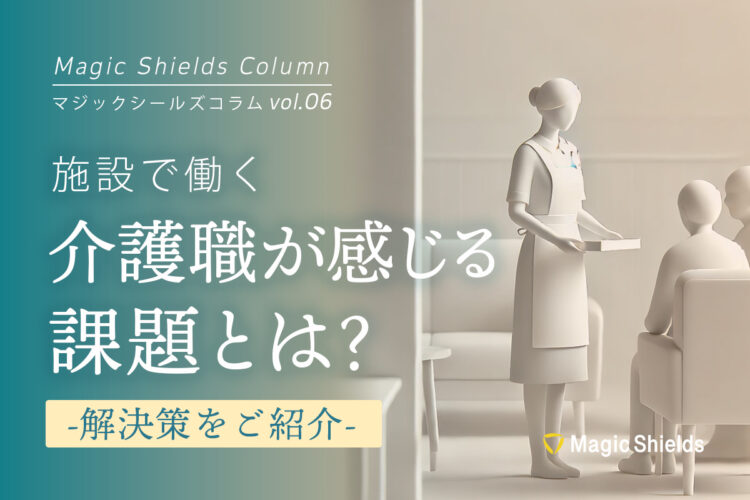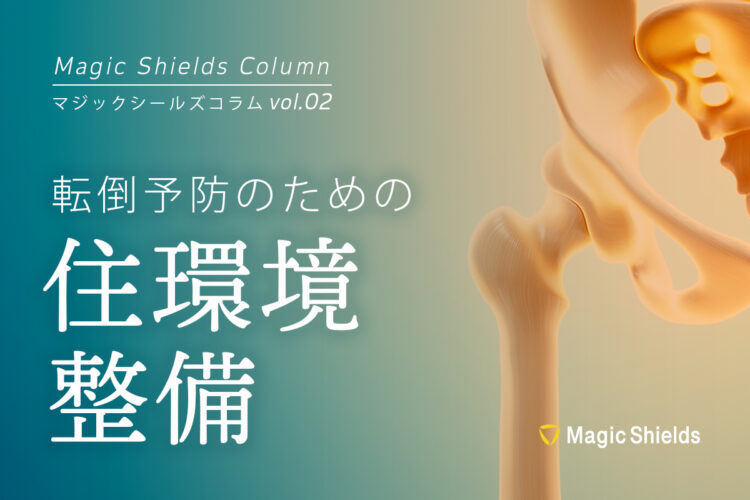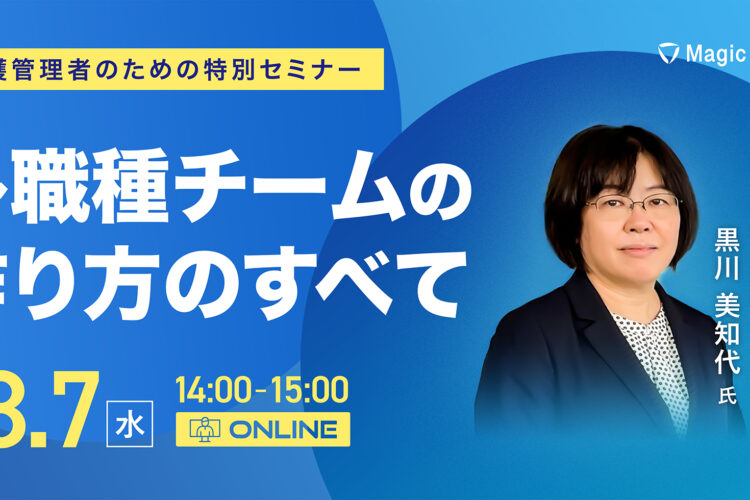「在宅高齢者の転倒骨折対策として住環境を整えたい」「ご利用者様の生活を住環境の視点から良くしたい」と思っている方もいるのではないでしょうか。
また、自分自身や家族の住環境を改善したいと考えている方もいるかもしれません。
しかし、提案するのは、いつも介護保険内の住宅改修や福祉用具の提案になってしまっているのではないでしょうか。
実は、それ以外にも住環境整備の提案方法はあります。
今回は、住宅業界で働く作業療法士である長谷川様に高齢者のための住環境整備についてお話いただきましたので、その内容を紹介していきます。
住環境に潜む健康リスク

住環境が整っていないことによる、健康リスクはさまざまです。
ここからは、住環境に潜む健康リスクについて詳しく解説していきます。
住環境が整っていないことによる日常災害リスク
日常的に起きているのは、自然災害より日常災害です。
国土交通省の「住生活総合調査」によると、住宅の各要素に対する(不満立)評価を調査したところ一番不満が、43.4%の「高齢者への配慮」でした。
内閣府「高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査」によると、高齢者の90%が住宅に住んでいて、施設入所は10%未満となっています。
つまり、高齢者の安全な生活を守りたいと思ったら、住環境に着目することが大切ということがわかります。
加齢による体の変化は、次のとおりです。
- ・筋力の衰え
- ・バランス感覚が鈍る
- ・感覚機能が低下する
- ・認知機能の低下
- ・視力の衰え
加齢により心身機能が低下すると、転倒リスクが増大します。
日常生活のなかで、一度でも転倒すると恐怖心をもつようになるでしょう。
そして、恐怖心をもってしまうと、活動性が低下します。
活動性が低下すれば、必然的に転倒リスクがさらに増えます。
このように、心身機能の低下による転倒は、負の連鎖を引き起こしてしまうのです。
東京消防「救急搬送データからみる日常生活の事故」によると、70〜100万人の高齢者が、転倒・転落による救急搬送をされています。
そのうち、55%は住宅内で発生しています。
転倒・転落の発生場所ランキングは、次のとおりです。
- ・1位:居室
- ・2位:階段
- ・3位:廊下
居室の中で多いのが、リビングになります。
リビングでつまづいたり、滑ったりする原因がカーペットやコード、おもちゃだとしたら、すぐに対策できるでしょう。
しかし昔ながらのお家の構造が原因だとしたら、そうはいきません。
なぜなら、昔ながらのお家をリフォームするためには、お金や時間がかかるからです。
ホームハザードとは
ホームハザードとは、直訳すると「住宅の危険」です。
つまり、家のなかのリスクがある部分になります。
リスクが高いつくりの具体例としては、次のとおりです。
【玄関の上がり框】
- ・段差が高い
- ・手すりがない
- ・靴の着脱時の椅子がない
【階段】
- ・手すりが短い
- ・証明が少ない
- ・段差の幅が狭く高いため勾配が急
【収納棚】
- ・台や椅子にのぼって取り出す、掃除する必要がある
【トイレ】
- ・開き戸である
- ・入口の幅が狭い
- ・広さが十分ではない
その他、寝室に代わる部屋が一階になく、階段を使用しなければならないケースや、洗濯機から屋外に洗濯物を運ばないといけない場合も日常生活上での負担が重く、転倒リスクを高めます。
室内温度と健康への影響

室温の高齢者の健康は、密接に関係しています。
そこで、ここからは住宅の室温が高齢者の健康にどのような影響を及ぼすかを解説していきます。
室温が低いことによるリスク
WHO「住宅と健康に関するガイドライン」では、心疾患・脳血管疾患は寒い住宅で発生しやすく、家の中で最低温度を18度以上に保つ必要があることを伝えています。
室温による健康リスクは以下のとおりです。
- ・18度:座り仕事をする人の健康に対するリスクを抑える
- ・18度以下:心疾患・脳血管疾患のリスクを高める可能性がある
- ・16度以下:転倒・怪我のリスクを高める、病気の抵抗力を低下させる可能性がある
住環境の改善は、QOLを高めます。
しかし、日本においては低い室温で過ごしていても、違和感をもたなくなっているというのが現状です。
それは、日本の平均室温に原因があります。
日本の平均室温は、次のとおりです。
- ・居間:16.8度 在宅中平均居間室温
- ・寝室:12.8度 就寝中の平均居間室温
どちらもWHOが勧告している18度を大幅に下回っていることがわかります。
室温18度以下の健康リスクは、具体的に次のとおりです。
- ・血圧の上昇:高血圧によえい心疾患や脳血管疾患のリスク
- ・入浴中の溺れ・溺水
消費庁「高齢者の不慮の事故」によると、65歳以上の家の浴槽における溺死は4750人だということが明らかになっております。
つまり、室温の影響により、高齢者の死につながる可能性もあるということです。
また、暑い家での健康リスクとしては、熱中症が挙げられます。
65歳以上の熱中症による救急搬送の約5割は、室内で発生しています。
高断熱住宅と室温
住宅の熱の出入りは、開口部(窓や玄関ドア)夏は家の外からなかに熱がどんどんはいってきて、冬は熱が外に出ていきます。
その結果、室温が上がりすぎたり、下がりすぎたりし、快適な温度が保てなくなってしまうのです。
そこで、おすすめなのが高断熱住宅です。
高断熱住宅とは、外壁と床下、天井裏などに断熱材を詰めて、断熱効果を高めた住宅断熱性が高い住宅のことをいいます。
外気温による影響を受けにくいのが特徴です。
また、高断熱住宅に暮らすことにより、健康リスクを回避することができる可能性があります。
高断熱住宅での、具体的な効果は以下になります。
【循環器疾患の改善】
- 高血圧疾患:8.6%→3.6%
- 心疾患:2.0%→0.4%
- 脳血管疾患:1.4%→0.2%
参照:日本サステナブル建築協会2023年のデータ
【血圧低下】
・最高血圧:3.1mmHg低下
・最低血圧:2.1mmHg低下
参照:日本サステナブル建築協会2023年のデータ
また、高断熱住宅で平均室温が18度以上になることで、寒暖差が少なく高温浴による健康リスクも減少させることができます。
リスクを防ぐために

介護保険による住宅改修(居宅介護住宅改修費)を行えば、次のような改修が可能です。
- ・手すり取付
- ・段差解消
- ・扉の取り換え
- ・床の材料変更
- ・便器の取り換え
住環境の改善を提案するときには、どうしても介護保険内での改修・福祉用具ばかりになってしまう傾向にあると思います。
その背景には、次のような想いがあるのではないでしょうか。
- ・「福祉用具以外の商品がわからない」
- ・「お金儲けのための提案になってしまうような気がして気が引ける」
しかし、高齢者の住環境を考えたときに、本当に必要なことを伝えることは大切です。
例えば、窓のリノベーション補助金制度を利用すれば、内窓の設置や窓ガラス、外窓の交換費用の二分の一に当たる金額の補助を受けることが可能です。
窓のリノベーション補助金制度を利用して、窓を改修した事例では、外気温が10度でも無暖房で室温22度にすることができました。
また、全窓にかかった費用114万円のうち、約70万円の補助金を受けています。
高齢者の健康の安全を考えた住環境において、今すぐできることは、室温の調整です。
温度計の設置の他、冬でも18度以上を保ち、部屋内の温度差を可能な限り小さくしておきましょう。
また、ヒートショックを回避するために、浴槽の温度を41度にして10分以内に入浴を済ませることも重要です。
上記のように今すぐできることはすぐに実施し、それだけではなく今後のために対策したほうがよいことを相談できるのが理想的です。
まとめ

高齢者の健康や生活の安全を維持していくためにも、快適で安全性の高い住環境は大切になります。
介護保険内の改修・福祉用具のみに囚われず、多角的な視点で住環境の整備について提案をしていけることが理想的です。
特に適切な室温を保つことができるような、住環境の改修を提案できるとよいでしょう。
また、安全な住環境においては室温の調整だけでなく、転倒・骨折につながらない環境も重要です。
歩く時は硬く、転倒時には衝撃を低減するころやわなら、高齢者の転倒による骨折リスクを抑えることができます。
安全性の高い床「ころやわ」の導入も、ぜひ検討してみてください。
そして、今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をチェックしてみましょう。