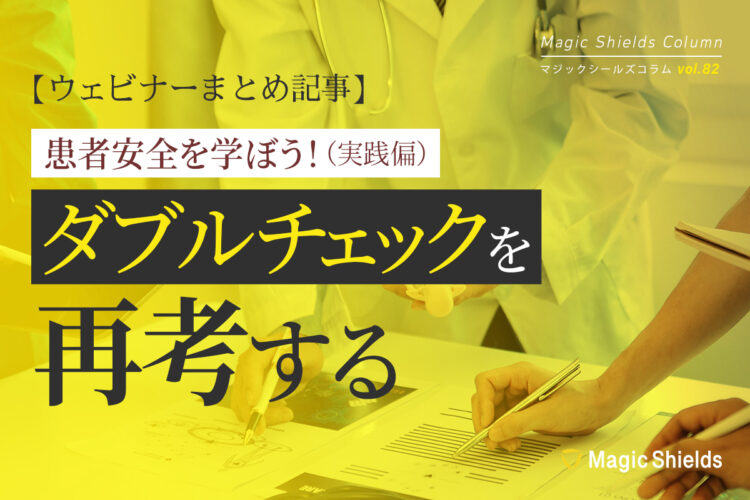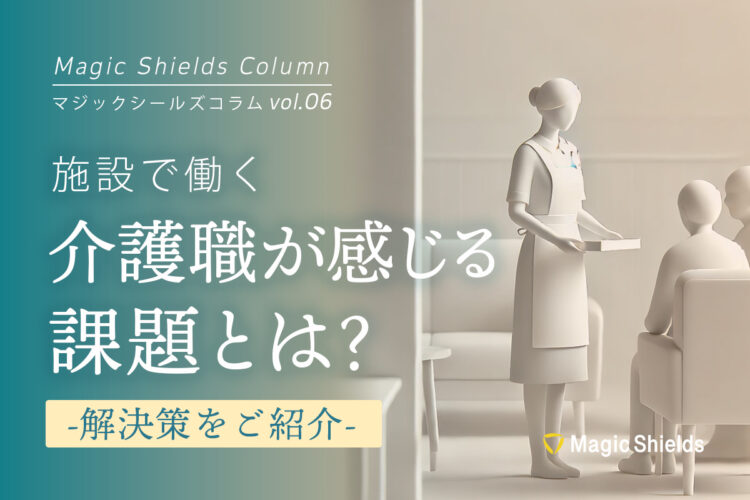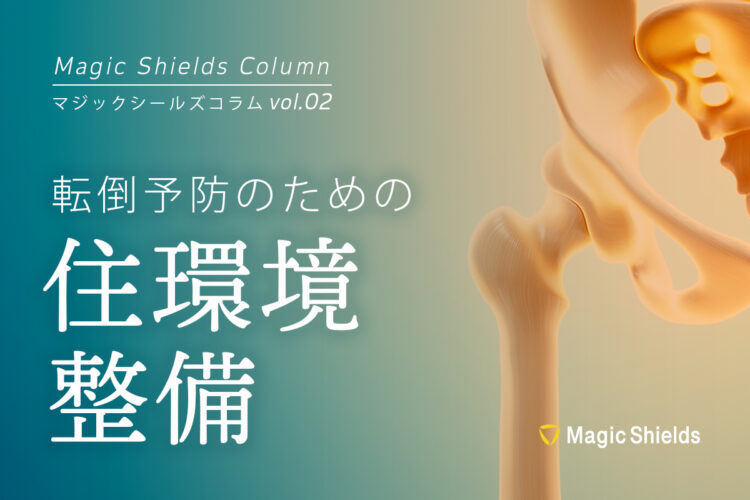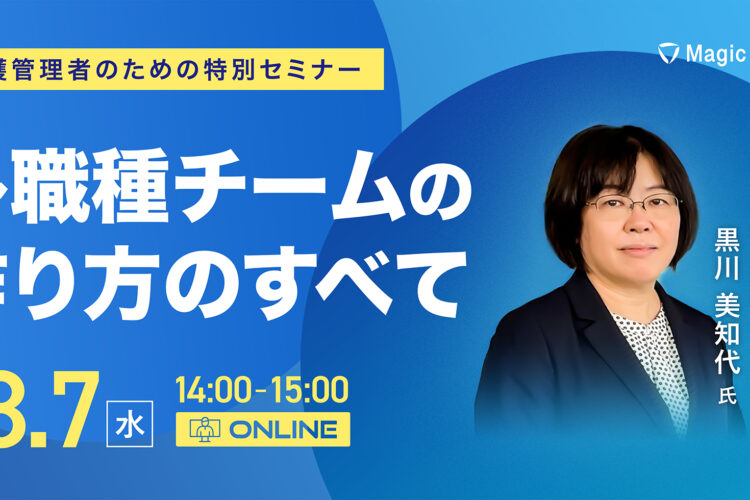目次
「新人教育で与薬について自信を持って指導ができない」「久々の病棟勤務で与薬業務に対する不安が大きい」といった悩みを抱えている看護師の方もいるのではないしょうか。
そのような不安を抱えたままでいると、気持ちが不安定になり、ヒューマンエラーを起こしやすい状態になってしまいます。
今回は、ウェビナーでは、薬剤師・看護師のダブルライセンスホルダーである荒井様(北里大学大学病院医療安全管理者)をお招きし、薬剤関連の医療事故を防ぐための安全な与薬についてお話いただきました。
公益社団法人日本医療機能評価機構の医療事故収集等事業より、与薬に関するエラーの事例を元に防止方法等を紹介していきます。
記事では、その内容をまとめていますので、ぜひご覧ください。
与薬エラーのリスク

与薬エラーは、医療現場でも発生しやすいものです。
ここからは、公益社団法人日本医療機能評価機構の医療事故収集等事業に記載されていた与薬エラーの事例を紹介します。
【事例】
当直医は、セレネース注を投与するよう口頭で看護師に指示しました。
看護師は指示されたセレネース注をサイレース静注と思い込み、カギのかかった薬品庫から取り出しました。
当直医は電子カルテの注射指示に「セレネース注1A+生理食塩液9mlのうち5mlIV」と入力しましたが、看護師は見ていませんでした。
看護師はサイレース静注1A+生理食塩液9mlを調製し、静脈注射しました。その後、患者様はSpO2が74%まで低下し、BiPAPマスクを装着しました。
勤務交代後、リーダー看護師が薬品庫の薬剤を確認したところ、サイレース静注の数が減っており、誤ってサイレース静注を投与したことに気づきました。
引用:日本医療機能評価機構「医療事故収集等事業」
くすりは「リスク」と表裏一体です。
医薬品(くすり)は、疾患の治療や予防に有益です。
しかし、使い方を間違えてしまうと与薬に関連するリスクや有害事象が増加してしまう怖さがあります。
メディケーションエラー(誤薬)は、有害事象の主な原因なのです。
WHO患者安全カリキュラムガイドの11番目にも、「投薬の安全性を改善する」との記載があります。
本来、薬は直接作用部位に接触し、循環血液に入ることで効果を発揮させることができます。
それらを踏まえたうえで、薬をどのように取り扱わなければならないのか、一度原点に立ち返ることが大切です。
与薬プロセスには複数の医療職が関与
与薬プロセスには複数の医療職が関与します。
与薬プロセスに関与する医療職は、簡単に表すと以下のとおりです。
医師→複写→薬剤師→看護師
医師が指示してから、患者様に薬が投与されるまで、さまざまな職種が関わります。
さらに与薬エラーに関する発生率や未然に防止された率を医師・看護師で比較したところ、次のような結果となりました。
【エラー発生率】
- ・医師:39%
- ・看護師:38%
【患者に提供されるまでに未然に防止された率】
- ・医師:48%
- ・看護師:2%
医師と看護師のエラー発生率を比較すると差ほど変わらないことに対し、未然に防止された率を比較すると医師が48%にあることに対し看護師は2%と、看護師の防止率が圧倒的に少ないのがわかります。
これは看護師は、患者様に直接薬を与薬することが関係しています。
参考:incidence of adverse drug events and potential adverse drug events
厚生労働省研究「医療リスクマネジメント構築に関する研究」で記載されている、川村治子先生が研究された調査書によると、注射エラー発生にはさまざまな要因があることが明らかになっています。
注射エラーの発生要因は、次のとおりです。
- ・情報伝達の混乱
- ・エラーを誘発する「モノ」のデザイン
- ・エラーを誘発する患者様の類似性
- ・注射準備・実施業務の途中中断と不誠実な業務連携
- ・不明確な作業区分と狭い注射準備作業空間
- ・時間切迫
- ・薬剤知識の不足
- ・急性期医療に対応困難な新卒者の知識と技術
参照:厚生労働省研究「医療リスクマネジメント構築に関する研究」
つまり、エラーは情報(Software)とモノ(Hardware)、そしてヒト(Humanware)の条件が不足した場合に起こりやすいということがわかります。
逆に言えば、看護師が薬剤の知識だけ豊富であっても、事故を防ぎきれないということなのです。
エラー防止をするために
薬は、正しく使用すれば効果を発揮できるものですが、適切に使用しないと害になります。
まずは、看護師一人ひとりが専門職としての正しい知識をもつこと、そして疑問を解決する知恵を持つことが大切です。
それを前提として、人は不安全な行動を引き起こすものとして、不安全行動に対しての対策が必要です。
不安全な行動で挙げられる事例は、次のとおりです。
【ヒューマン・エラー】
- 人間の能力の限界:見えない、聞こえない、覚えられない
- スリップ:思い込み、考え違い
- 失念:うっかり、ぼんやり、一時的な物忘れ
- 知識不足、技術不足:知らない、できない
【違反】
- めんどう、たぶん大丈夫、少しだけなら、みんなもやっているから
うっかりミスから、慣れによる「これくらい大丈夫だろう」の油断がエラーにつながります。
ヒューマンエラー対策の発想
エラーの防止対策は、次の順番で検討していく必要があります。
- エラー発生防止
- その作業をなくす
- 物理的に制約する
- 認知的負担を軽減する
- 自分で気づかせる
- 被害を最小化する
参考:河野龍太郎:医療におけるヒューマンエラー
以下に防止対策のなかの「エラー発生防止」について、実際に実施された事例がありますので紹介していきます。
事例:キシロカインの10ml発売中止の経緯
キシロカインの10mlの投与に関する事故が相次いだことにより、「点滴専用」のラベルをわかりやすく貼付する対策をしました。
しかし、それでも事故が発生したため、今度はキャップをつける対策をしました。
それでも事故の発生は防げず、最終的にはキシロカインの10ml発売中止を国と製薬会社が決定したのです。
発売自体をなくすことで、事故は起こらなくなり、「エラー発生の防止」ができた事例になります。
次に2番目の「その作業をなくす」を実施した事例を紹介します。
事例:ワーファリンと併用注意の食べ物を献立に入れるのをやめる
急性期の病院での荒井先生のご経験談です。
ワーファリンを投与していた患者様に併用注意の食品である納豆を供給してしまった事例が増えたことがありました。
それにより、誤って供給しないよう、最初から納豆を献立に入れるのをやめました。
これもエラー対策の一つになります。
安全な医療環境にするために

安全な医療環境にするために着目したい要素は、大きくわけて3つです。
次の表では、実施すべき3つの対策、Software・Hardware・Humanwareをそれぞれわけて紹介します。
| Software(情報)対策 | Hardware(モノ)対策 | Humanware(ヒト)対策 |
| 教育・訓練 | エラー発生時に安全確保(Fail-safe化) | 危険予測訓練(KYT)健康確認や指示差し呼称 |
| マニュアルの設備 | エラーを起こさない工夫(foot-proof化) | チームトレーニング・コミュニケーション・リーダーシップ・復唱等 |
| 作業・指示方法の統一化、標準化、明確化 | 環境整備(スペース、照度、レイアウト、動線など) | |
| ラウンド |
参考:医療安全KYセミナーガイド「医療安全のための危険予知活動の進め方」
また、Humanware対策に「コミュニケーション」と記載していますが、与薬のプロセスにおいて、口頭指示のみは危険です。
WHO患者安全カリキュラムガイド多職種版では、次のように伝えています。
コミュニケーションエラー防止
- ・十分なコミュニケーションには注意(書面、口頭、患者説明も)
- ・指示を出すときには、相手の名前を呼ぶ
- ・はっきりとしゃべる
- ・記録時は、読みやすい字ではっきりと書く。略語は使用しない
- ・6つのRを意識し、確認しながら指示を出す
- ・コミュニケーションのループを完成させる→復唱してもらう
- ・単位は省略しない
- 例:「ミリ」と省略せず「ミリリットル」や「ミリグラム」まで具体的に言う、または記載する
参照:WHO患者安全カリキュラムガイド多職種版
口頭指示には、復唱し確認してもらう
医師から口頭指示をされたときには、復唱することが大切です。
なぜなら、復唱することで、自分の認識に相違がないかを再確認できるからです。
例えば、「フロセミド注射を1ミリグラム静脈注射してください」と指示を受けたら、「フロセミド注射を1ミリグラム静脈注射ですね」と復唱しましょう。
これにより、看護師が情報の正確な受信やフィードバックの確認ができるだけでなく、医師側にとっても伝達されたことへの確認が可能になります。
また、同じ成分でもさまざまな名前がありますので、以下3要素で特定・確認する必要があります。
- ・ブランド名
- ・剤形
- ・規格単位
接尾が違うだけで他剤を表しますので、医療品名称も必ずフルネームで確認しましょう。
特にブランド名の接尾語のアルファベットには、注意してください。
薬剤の誤投薬防止の基本

誤薬防止のためには、基本を忠実に守ることが大切です。
ここからは、薬剤の誤投防止の基本6つ、またその他注視すべき点を紹介していきます。
1.正しい患者様か
投薬をする場合、患者様の正確な特定が大切です。
薬を投与する患者様を特定する場合には、次の対策を行いましょう。
- ・可能な限り患者自らフルネームを名乗ってもらう(イエス/ノーで聞かない)
- ・同姓同名に注意する
- ・フルネームだけで同定しない(生年月日など2要素で確認)
顔見知りだから名乗ってもらう必要は無いのではなく、患者様に名乗ってもらうことで手元資料(処方箋・指示書)と照合することが大切です。
2.正しい薬剤か
正しい薬剤かの確認も、誤薬を防止するうえで重要です。
薬は同じ成分の製剤でも複数の商品が販売されているため、間違えやすいです。
例えば、一般名(成分名称)アセトアミノフェンは、次のような類似商品があります。
【先発医薬品】
カロナール、アセリオ、アンビバ等
【後発医薬品(ジェネリック)】
アセトアミノフェン錠200㎎「トーワ」等
薬には多くの名前があるため、投薬の際には間違えないように充分注意をしましょう。
3.正しい用量か
次に、正しい用量かの確認も大切です。
個々の医薬品の特徴と患者様の病態に合わせた用量は医師が決定しますが、看護師も確認しましょう。
医薬品添付文書の用量・用法を確認し、年齢や体重、服薬回数や腎機能障害時と照らし合わせます。
また、薬用量の単位にも注意が必要です。
4.正しい経路か
薬の投与方法を再度確認しましょう。
投薬には、さまざまな経路があります。
- ・経口投与
- ・血管内投与
- ・皮下注・筋肉内注射
- ・眼、気道、髄腔内
- ・舌下・肛門
特に、血液に直接投与する注射に関しては、リスクが高いことを再認識しておきましょう。
異なる方法(経路)で薬剤を投与してしまう事故の事例は、実際にあります。
経路を誤ってしまうと、患者様に害を及ぼしてしまいますので、十分な注意が必要です。
5.正しい時間・スケジュールであるか
投薬の時間・スケジュールは、正しいものであるかの確認も必要です。
昨今では、休薬期間を置く必要がある「連日投与しない特殊なスケジュール」も存在します。
そういった場合にスケジュールを誤って連日投与してしまえば、血中濃度が高くなり薬が強く作用してしまうリスクがあります。
6.正しい目的か
看護師が「何のために与薬をするか」の目的を把握することも、大切です。
それを理解しておくことで、万が一、薬が誤っていた場合、早期発見につなげることができます。
使用後の観察(モニタリング)
使用する薬剤の効能と副作用の症状を理解しましょう。
特に、重大な副作用とその初期症状や対処法が理解できていると、万が一の際に迅速で適切な対応ができるようになります。
特に、あらゆる薬剤で発症の可能性があるアナフィラキシーへの反応には、注意が必要です。
静脈内注射の場合は、投与開始から5分前後で呼吸停止・心停止が起こることが多いため、発症リスクの高い薬剤を使用する際には、投与後5分くらいは注意深く観察しましょう。
また、発症リスクの高い薬剤を使用する際には、必ずアドレナリン注射液の筋肉注射の準備や救急処置の準備をしておく必要があります。
医薬品添付文書の確認
医薬品添付文書には、看護師に必要な情報が記載されています。
添付文書は難しく表現されていますが、読み方を知っていると必要な情報が効率よく手に入ります。
添付文書の右肩に赤色の帯が印刷されている場合は、「警告」が記載されているという意味です。
こういった場合は、必ず「警告文」を確認しましょう。
また、「適用上の注意」についても必要な情報が記載されていることが多いです。
最新の添付文書情報は、医薬品医療機器総合機構のホームページから入手できます。
ハイリスク薬とは
ハイリスク薬とは、治療濃度域が狭く、医療事故やインシデントが多数報告されているものを指します。
診療報酬上のハイリスク薬例は、次のとおりです。
- ・抗悪性腫瘍剤
- ・免疫抑制剤
- ・不整脈用剤
- ・抗てんかん剤
- ・血液凝固阻止剤
- ・ジギタリス製剤
- ・テオフィリン製剤
- ・カリウム製剤
- ・精神神経用剤
- ・糖尿病用剤
- ・膵臓ホルモン剤
- ・抗HIV薬
各機関ごとに「ハイリスク薬」を指定する場合もあります。
リスクは全ての薬にあるものですが、特にハイリスク薬には注意するようにしましょう。
メディケーションエラー防止と患者要因

メディケーションエラーの防止をするために、まずはその要因について理解しておきたいところです。
メディケーションエラー発生の患者様要因については、次の6つが挙げられます。
- 複数の薬剤を使用している患者様
- 併存疾患がある患者様
- 良好なコミュニケーションがとれない患者様
- 複数の医師に受診している患者様
- 自身が薬剤療法に対して積極的に関与しない患者様
- 小児や幼児の患者様
特に、自身が薬剤療法に対して積極的に関与しない患者様については、誤薬の発見が遅れることがあります。
上記の要因を踏まえ、メディケーションエラー防止のためには、患者様に薬剤療法に対し関心をもってもらう、また医療職のチームワークも大切になります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
与薬エラーは、誰にでも発生する可能性があります。
薬とリスクは表裏一体であり、与薬エラーのリスクを理解し、適切な方法でそれを防止していくことが大切です。
記事内で紹介した6つの基本は、重要なポイントになりますので、ぜひ現場でも実践してください。
また、今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はアーカイブ動画をチェックしてみましょう!