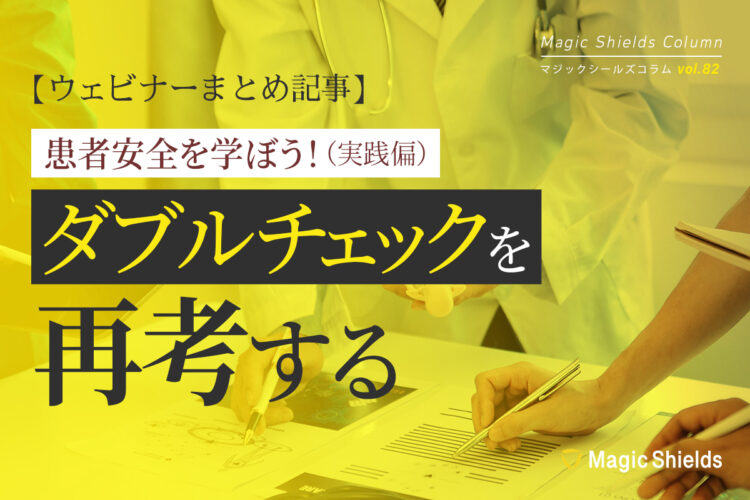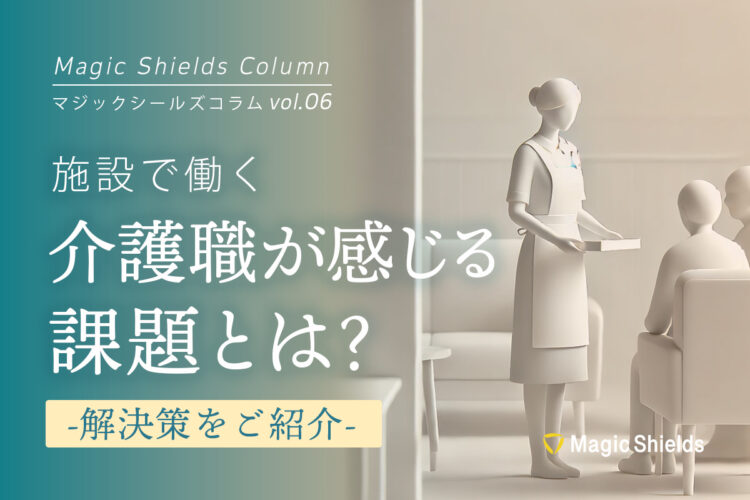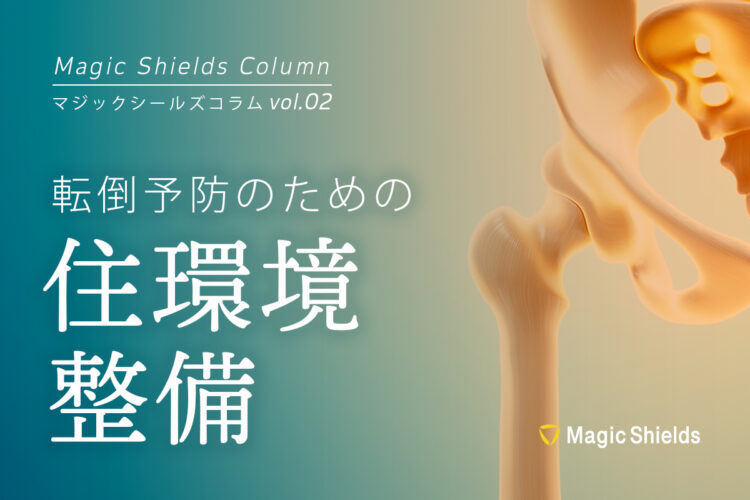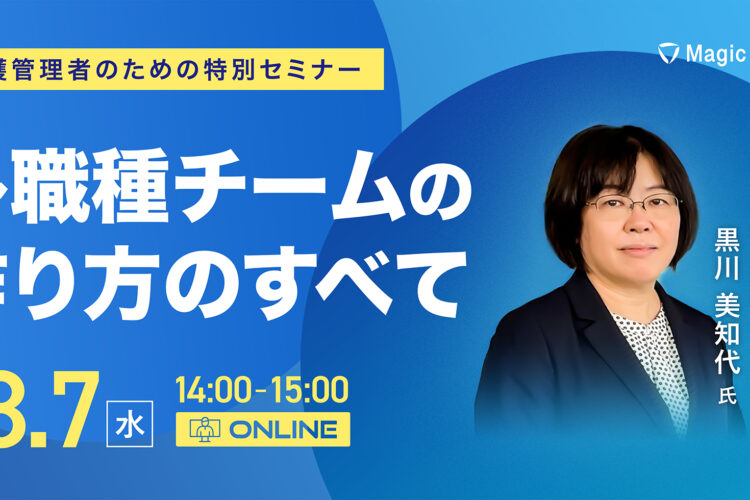目次
「がん患者との関わり方に悩んでいる」「エビデンスに基づいたケアとその人らしさの両立に課題を感じている」と思っている方もいるのではないでしょうか。
今回は済生会千里病院 がん総合診療センター副センター長であり、がん看護専門看護師/がん性疼痛看護認定看護師でもある岩上様をお招きし、エビデンスに基づく実践と、患者の「その人らしさ」を支える看護についてお話しいただきました。
そのウェビナーの内容を詳しく紹介していきます。
がん看護の最新の動向と臨床現場の課題

がん看護のあり方は、時代の変化により変わります。
ここからは、がん看護の最新の動向と臨床現場の課題について解説していきます。
疾患構造の変化
疾患構造は時代により変化しています。
次の表では1950年から2021年の主な変化をまとめました。
| 1950年 | 1980年 | 2021年 | |
| 主な死因 | 1.結核 2.脳血管疾患 3.肺炎、気管支炎 | 1.脳血管疾患 2.悪性新生物 3.心疾患 | 1.悪性新生物 2.心疾患 3.老衰 |
| 主な死亡場所 | 自宅(7割) | 自宅→病院 | 病院(65.9%) |
| 死亡者数 | 約90万人 | 約72万人 | 約143.9万人 |
| 高齢人口割合 | 4.9% | 9.1% | 28.9% |
| 平均世帯人数 | 5.07人 | 3.25人 | 2.37人 |
参照:厚生労働省HP
1950年に比べ、2021年は高齢人口割合が大きく変化していることがわかります。
また、死亡場所も現在は半分以上が病院であることも明らかになっています。
がん患者の置かれる状況の変化
がん患者の置かれる状況は、時代の流れにより変化してきました。
それによる医療現場における課題としては、主に2つになります。
1.患者の高齢者
2021年頃から日本の高齢化率は約30%となっており、超高齢化社会に突入しています。
がん患者の多くが高齢者であるという現状があります。
そのことから、患者様の疾病だけでなく加齢により併発される症状にも向き合っていかなければなりません。
2.疾患の複雑化
次にあげられるのが疾患の複雑化です。
特にがん以外に「認知症」や「心不全」、「糖尿病」などを抱えている「多疾患併存」の患者様が多いのも事実です。
その他、「独居」により「社会的孤立」や「経済的問題」など、生活上の他の課題を抱える患者様もいます。
上記2つが患者様の置かれる状況での主な課題ですが、昨今では医療の発展に伴い複雑な状況にあるがん患者様に対しても、多様な治療が適用可能になりました。
ゲノム情報に基づく薬物療法や免疫療法などです。
老化に伴う脆弱化
加齢により恒常性の維持が困難になり、予備力・適用力・回復力・防衛力の機能低下が起こります。
こうした背景から、高齢者を対象としたがん治療は特に、集団から個へのアプローチが大切になります。
変化を踏まえた3つのアプローチ

高齢がん患者様は病気が進行するにつれ、さまざまな変化に苦しむことがあります。
そのような苦しみを和らげるために大切なのは3つのアプローチです。
ここからは、3つのアプローチについてそれぞれ解説していきます。
症状マネジメントのアプローチ
終末期の症状の変化として、病気の進行につれて、多様な症状が生じる割合が高くなります。
それに伴い、さまざまなアプローチの検討が必要です。
高齢がん患者様の主な症状としては次の特性があげられます。
高齢者の症状、疾患の特性
- ・複数の疾患に罹患していることが多い
- ・症状や所見は非定型的であることが多い
- ・疾患を契機として日常生活機能低下などによりQOL低下を生じやすい
- ・多くの治癒を期待できない慢性疾患である
- ・症状が急変しやすい
- ・せん妄などの精神疾患や廃用症候群を生じやすい
- ・薬物の有害事象が起こりやすい
参考:日本老年医学会
高齢がん患者様の症状の特性から、マネジメントのポイントは以下になります。
症状マネジメントのポイント
- ・症状は心身の不調を知らせる重要なサインである
- ・症状の個人的な意味に焦点を当てる
- ・患者と症状マネジメントの目標を共有する
- ・薬物療法とケアを並行して行う
- ・専門的なチームワークが必要である
その人らしさへのアプローチ
その人らしさへのアプローチとしては、尊厳の保持が重要になります。
特に、高齢者は疾患や加齢に伴う機能の低下で、自分のことが自分でできなくなっていく傾向にあります。
他人の手を借りなければ生活を送ることが難しくなるからこそ、日々繰り返される日常生活上のケアが大切です。
日々の日常生活上のケアを丁寧に行うことが、高齢者の尊厳を保持することにつながります。
日常生活上のケアにおける高齢者の苦痛と尊厳を保持するためのケア
高齢者の日常生活上において、苦痛に感じやすいケアの例は次のとおりです。
- 姿勢:褥瘡を起こしやすい
- 移動:意思に反した移動
- 食事:無理強いされる
- 入浴:勢いよく湯をかけられる
- 清潔:入浴させてもらえない
- 更衣:無理に腕を引っ張られる
- 排泄:排泄物を見られる
- 整容:意思に反しひげを剃られる
このように、本人の意思に沿わないケアは尊厳を傷つけてしまう恐れがあります。
尊厳を保持するための日常生活上のケアを心がけていくことが大切です。
尊厳を保持するための日常生活上に以下のような工夫をしていきましょう。
- ・拘縮予防の配慮:関節他動運動を行う
- ・食を楽しめる配慮:少量でも好物を堪能できるように工夫する
- ・清潔保持への配慮:入浴や整容、口腔ケアを積極的に実施する
- ・安楽な呼吸への配慮:体力に合った活動を検討する
- ・苦痛の緩和の配慮:姿勢への配慮や慢性的な痛みの緩和に取り組む
- ・心地よい排泄の配慮:自然な排便を促す、プライバシーへの配慮を心がける
ACPのアプローチ
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)とは、今後の治療・療養について患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセスのことです。
引用:厚生労働省「アドバンス・ケア・プランニング」
認知機能の低下や患者様自身が病状を受け入れられないことにより、ACPのアプローチが困難な場合もあります。
今回は、困難な状況であっても、連携し合ってアプローチ・支援を実現した事例を紹介します。
【事例】
- 75歳男性
- 病名:進行S状結腸がん、横行結腸がん
- 併存疾患:早期直腸がん、心房細動、バセドウ病、2型糖尿病、肺気腫、認知症等
- 治療方針:人工肛門造設術
がんの状況から人工肛門の造設が必要と判断された患者様です。
この患者様は、変化する意志が課題となりました。
例えば、認知機能の低下や「受け入れたくない」という気持ちからか、手術の説明をしても意見が変わったり、忘れていたりと、意思が定まらず方針が決定しないという状況にありました。
このような状況から、病棟看護師からもストーマ管理ができるのかと不安な声が聞かれました。
しかし、手術を受けるほうが今後のQOLを支えられるのではないかという考えも現場でありました。
そこで、意思決定の阻害因子を振り返ってみました。
挙がったのは、以下2つのポイントです。
- ・ストーマに対するイメージができていない
- ・病棟看護師も術後管理に不安を抱えている
本人がストーマに対するイメージができていないことで意思が決定できない、また病棟看護師もその様子をみて術後の支援に不安を感じているということが課題に挙げられました。
その2つのポイントから、以下の対策を考案しました。
- 意思決定能力の評価
- ストーマに対する抵抗感への支援
- 患者様の思いや一番大切にしていることはなにかの確認
- 病棟看護師への支援
意思決定能力の評価
認知症は、大きくわけると以下3つのタイプになります。
| アルツハイマー型認知症 | 血管性認知症 | レビー小体型認知症 | |
| 記憶障害 | 必ず見られる | 比較的記憶力は、保持できているが、思考速度が遅くなる | 初期は目立たない場合がある |
| 記憶障害の変動 | ない | よくある | 5人中4人に見られる |
| 脳内変化 | 神経細胞が死滅し、記憶を司る海馬を中心に脳内が萎縮 | 脳梗塞や脳出血により部分的に脳が座礁を受けるため、脳の神経細胞が死滅 | 大脳皮質にタンパク質「レビー小体」が現れ、神経細胞を死滅 |
タイプによって支援のあり方が変わります。
例えば、血管性認知症については、比較的比較的記憶力は、保持できているが、思考速度が遅くなります。
認知症看護師が介入し、意思決定能力の評価・支援方法を検討しました。
今回の患者様については、理解・認識・論理的思考・表明ができているかを確認しました。
ストーマの抵抗感を減少する
意思決定能力の評価結果では、理解・認識・論理的思考・表明ができると判断されました。
そのため、次に
皮膚・排泄ケア認定看護師が介入し、ストーマの抵抗感を減少する取り組みを行いました。
例えば、ストーマ―のパンフレットを用いて説明をする、ストーマ―の位置をマーキングし、マーキング部位に装具を当てる練習をするなどです。
この取り組みから、ストーマ装着について、患者様は「いいよ」と答えるようになりました。
しかし、まだ本当の思いが不明確だと思ったため、患者様の一番の思いをくみ取るためのコミュニケーションを心がけました。
何度も患者様とコミュニケーションを取るなかでわかったのが、一番の思いは「また口から食べられるようになりたい」ということでした。
その思いを尊重し、医師からは「手術はしんどいかもしれないけど、食べることを諦めてもらいたくないです」と告げると、患者様は「頑張って手術を受けることに決めた」と自己決定することができました。
また、術後の指導方法の工夫の提案やストーマ指導など、病棟看護師への支援も行いました。
多職種で連携し、患者様が自分で意思決定できた事例でした。
患者様の高齢化による自己決定阻害因子の対策は、以下2つが重要です。
- ・話しを聴き、受け止め、患者様にとって大切なことを共に考える
- ・受け入れられないことによる患者様への不利益を理解してもらう
疾病構造の変化に応じたACPは、患者様の高齢化や疾病の複雑性により困難になることもあるでしょう。
そういった場合は、事例のように専門チームによる多職種の連携が大切です。
緩和ケア病棟の取り組み

大阪府済生会千里病院様は、地域に根差した病院を目指し緩和ケア病棟を設置しました。
地域での生活を重視した支援体制を整えています。
治療期から地域へのスムーズな移行の仕組みの構築として、在宅緩和ケアと病院緩和ケアの一体化を実現しています。
また、病棟の全病室に「ころやわフロア」を導入しました。
患者様の行動を制限せず、その人らしく過ごせる配慮のためです。
ころやわは、歩行安定性と衝撃吸収性の両立を実現した商品であるため、転倒骨折によるQOLの低下を防いでくれることを期待しています。
その他、患者様が自分らしく過ごせるために、以下の取り組みにも注力しています。
- ・心のこもったチーム医療の提供
- ・患者様が安心して過ごせる空間の構築
- ・患者様の嗜好にあわせた食事の工夫
- ・病室内でのペット面会
- ・最寄りの公園への散歩など自然とのふれあい
- ・音楽会、アロマセラピーなど各種イベント
病棟を利用する方がその人らしく心地よく過ごせる環境づくりを今後も目指していきます。
まとめ

がん患者様の高齢化により、医療現場の課題は多いです。
しかし、一人ひとりと向き合い、アプローチを進めていくことで個を尊重したケアの実現が可能です。
患者様の本当に望むことは何かをチームで連携しながら引き出しケアを行うことで、患者様の満足度や現場のモチベーションを上げることができるでしょう。
今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。