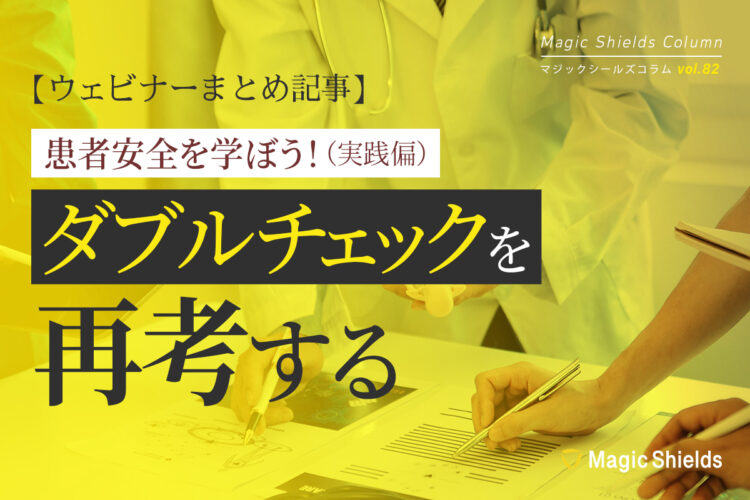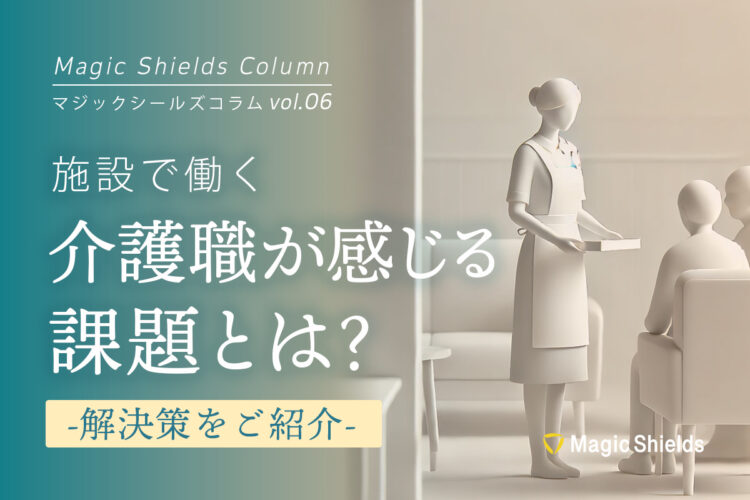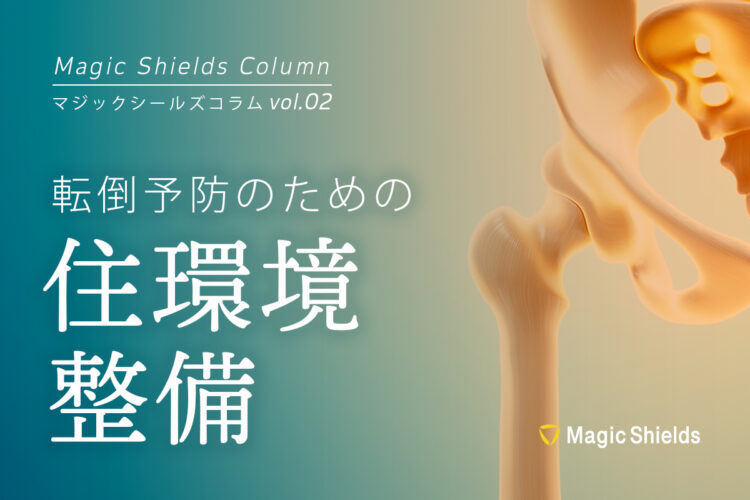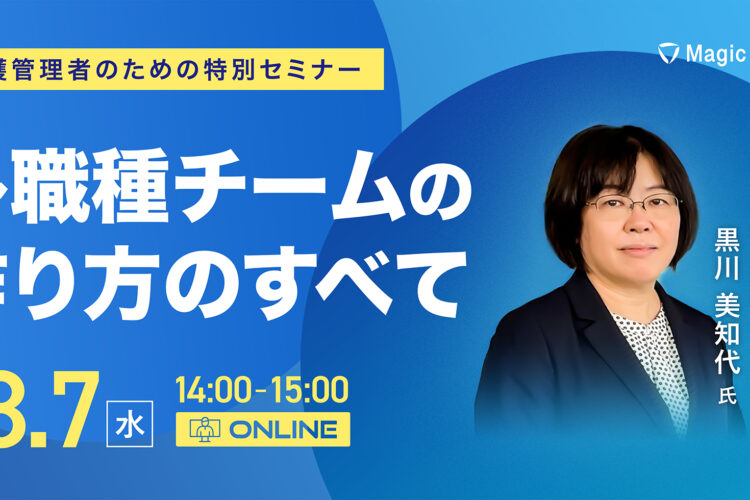目次
「がん患者との関わり方に悩んでいる」「看護師として、がん看護の専門性を高めたい」という思いを持っている方もいるのではないでしょうか。
また、苦痛緩和や意思決定支援の実践を深めたいと感じている方もいるかもしれません。
今回のWEBセミナーでは、済生会千里病院 がん総合診療センター副センター長であり、がん看護専門看護師/がん性疼痛看護認定看護師でもある岩上様に、エビデンスに基づく実践と、患者の「その人らしさ」を支える看護についてお話しいただきました。
その内容を簡単にまとめましたので、紹介していきます。
がん患者様のADL低下の背景

がん患者様へのサポートを考える前に、ADL低下の背景を再確認しておくことも大切です。
ここからは、がん患者様のADL低下の背景について解説していきます。
ADL低下の原因
ADLとは、日常生活動作のことを指し、具体的には以下のような日常生活上で必要な動作のことを言います。
- 食事
- 移動
- 更衣
- 入浴
- 整容
- 排泄
- 階段昇降
脳や運動器の一つでも障害されると、体が思い通りに動かないためADLが低下します。
しかし、それだけではなく、実は人間の各臓器もADLの質に大きく影響するのです。
例えば、がん患者様のように臓器にダメージを受けることにより、動作がしにくい体へと変化していくことがあります。
具体的な例は次のとおりです。
- 心臓・肺・血液の働きの低下→息切れ
- 腎臓・肝臓→浮腫、倦怠感
- 消化器→栄養障害、体重減少(筋肉量減少)
このような臓器障害が進行すると、辛うじて動けるけど動作が大変な状態になります。
動くのがしんどくなると、動く量が減少します。
動く量が減れば筋肉量が減少し、やがて大きく筋力が低下することになるのです。
がん患者様の病気が進行すると、こうした悪循環が生まれADLが低下しやすいのも特徴のひとつです。
がん患者様のADL低下の理由をさらに掘り下げていくと、原因は大きくわけて2つです。
ひとつ目は、がんそのものによる影響です。
がん細胞からの炎症性サイトカインにより、筋肉が萎縮したり、食欲が低下したりします。
次に、がん治療による影響になります。
がん治療による影響については、手術や化学療法、放射線療法による副作用などが挙げられます。
進行がんの場合は、化学療法が中心になりますので、多様な副作用による倦怠感や低栄養などの合併症から、動くことが制限されることも多いです。
進行がん患者様とADL
進行がん患者様の自然経過としては、死亡6か月から緩やかにADLが低下しはじめ、死亡前3か月から1か月にかけて急激に下がるのが特徴です。
また、がん患者様は高齢者が多いです。
がんと診断された全体の75.6%は65歳であるのが現状です。
参照:国立研究がんセンターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)データ
加齢によりすでにフレイルの状態であるうえに、がんを発症することで、さらにADLが低下しやすくなります。
ADLを維持・向上する意義

がん治療は、治療に対する効果を高めようとすると、正常組織に対する副作用が増える特徴があります。
大前提としてがん治療の大きな使命は生存期間を延ばすことですが、それだけでは不十分です。
生存期間を延ばすことを目的としつつ、がん患者様のADLを維持することに視点を向けることも大切なのです。
がん患者様の全身状態は、以下の指標で表します。
全身状態の指標:PS(SDL)
| スコア | 患者様の状態 |
| 0 | 無症状で社会的活動ができ、制限をうけることなく発病前と同等にふるまえる |
| 1 | 軽度の症状があり、筋肉労働は制限をうけるが歩行、軽労働や座業はできる |
| 2 | 歩行や身の回りのことはできるが、少し介助がいることもある。軽作業はできないが日中50%以上は起居している |
| 3 | 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助がいり、日中の50%は就床している |
| 4 | 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている |
上記のPS0~2が治療に耐えられるレベルであり、PS3~4になると治療を中止し緩和ケア中心の支援しかできなくなります。
ADLが自立していない場合、がん治療の継続が難しくなります。
がん患者様のADLは、治療の可否を判断する重要な因子であるともいえます。
つまり、治療の継続のためには、ADLレベルをいかに維持できるかが大切だということです。
また、化学療法の再開が生命予後を伸ばすカギとなりますので、まず一歩としてADLを維持・向上させることが重要です。
過去の事例では、あるがん患者様は術後7日目から歩行練習を開始しました。
日々のリハビリの成果もあり、その後は車椅子を自走できるまでになったのです。
その結果、化学療法が継続でき、しばらくは自宅で過ごすということができるようになりました。
歩行や自宅退院だけでなく、外来通院を含め、化学療法を再開できるように調整することで生命予後に寄与します。
歩行については可否によって、生存率が異なることも明らかになっています。
大阪国際がんセンターのデータによりますと、歩行障害を改善できたがん患者様とそうでないがん患者様を比較すると、前者のほうが生存率が高いという結果が出ています。
このデータからも、がん患者様のQOL健康寿命、または命を延ばすためには、ADLを維持・向上させることが重要であるということがわかります。
がん患者様ADL支援の現場からの実践紹介

昨今、入院日数の短縮化が進み、外来治療へシフトしているのが現状です。
平均入院日数は短くなる一方で、通院しながら治療を続けている患者様が増えています。
その影響もあり、入院中のリハビリテーションでは実施できる範囲に限界があります。
そのため、自宅でのリハビリテーションが重要になるのです。
また、転移性非小細胞肺がん患者様で早期に緩和ケアを始めた方とそうでない方を比較したところ、前者のほうが生命予後がよいということが明らかになったというデータもあります。
緩和ケアをがん治療が終わってからするのではなく、がん治療が始まった段階で少しずつ進めていくことが増えました。
ADLを支援するといった意味でも、緩和ケアを早期に開始することは有効です。
行動変容のステージモデルとしては、無関心な状態からがん患者になることで、自分の体への関心を持ち始めます。
そのタイミングで、患者様に準備をしていくよう働きかけ、実行を促していくことが大切です。
予防など、介入できるところから始めていきましょう。
アセスメント
ADLの維持・向上を目指すために、まずは患者様のアセスメントから実施していきましょう。
がん患者様のADL低下の背景を理解し、原因や要因を探索していくことが重要です。
現時点で、PSレベルのどの段階に位置しているかをチェックします。
また、アセスメントはベッドサイドでも実施可能です。
ベッド再度でできるアセスメント例は以下になります。
筋力低下判定
5回立ち上がりテストをし、腕を組んだ状態で5回立てるかを確認します。
できたとしても、とてもゆっくり(12秒以上)の場合は、筋力低下が疑われます。
バランス判定
片足立ちをしてもらい、保持できる時間を確認します。
5秒以下である場合は、バランス力の低下が疑われます。
がん患者様に推奨する運動療法
がんのリハビリテーションガイドラインでは、進行がんの患者様に対し、運動療法を実施することを勧めています。
ただし、あくまでガイドラインであるため、重度にADLが低下した患者様であれば、様子をみながら進めたり中止したりしていくことも大切です。
推奨される運動療法と頻度は、具体的に次のとおりです。
- 有酸素運動:週3~5日
- 筋トレ:週2~3日
- ストレッチ:毎日
強度に関しては、中等度の負荷で実施することが理想的ですが、無理は禁物です。
できることから始めていくようにしましょう。
また、運動療法は、がん関連倦怠感を軽減させる効果もあると言われています。
がん関連倦怠感は、放射線療法または化学療法中の80〜90%のがん患者に出現し、睡眠や急速によって軽減はしないものです。
倦怠感があるからといって臥床を延長してしまうと、夜間の質を下げてしまい、日中の活動性がさらに低下するため、避けたいところです。
倦怠感があっても、無理のない範囲で運動療法を続けていくことが重要だといえるでしょう。
ヨガなどの負荷が軽い運動から始めるのもおすすめです。
また、運動療法が重要なのは前提として、リハビリ職種が患者様と関わる時間は一日の中でそう多くはないのも事実です。
リハビリの時間以外に生活活動として、患者様自身が日常生活上での過ごし方も大切な着目ポイントです。
デジタルヘルス機器や福祉用具の活用
患者様の動きを管理するために、デジタルヘルス機器を活用するのもよいでしょう。
そして、患者様が負担なく身体機能を維持していけるために、さまざまなサポート体制を整えていくことも大切です。
例えば、自宅生活で必要な福祉用具(手すりや杖など)や支援を提案してみるのもよいでしょう。
まとめ

がん患者様においては、時間軸に注視し、ご本人の希望に沿った支援をしていくことが大切です。
ただ、身体機能維持・向上を目指すだけではなく、「なんのためにそれをするのか」を明確にしておくことも重要だと言えるでしょう。
ADLの維持・向上ももちろん大切ですが、ご本人のQOLの維持・向上についても忘れないようにしましょう。
元気なときからコミュニケーションをとって、患者様の望むことを支援者側が理解しておくことが理想的です。