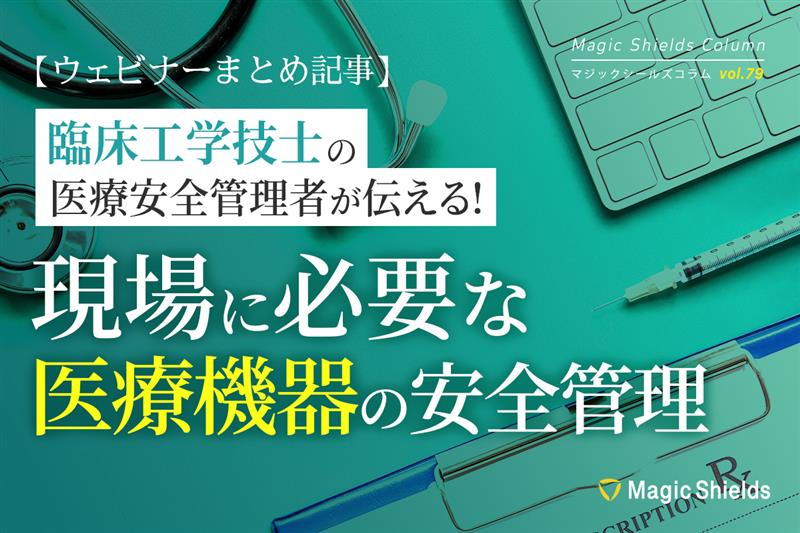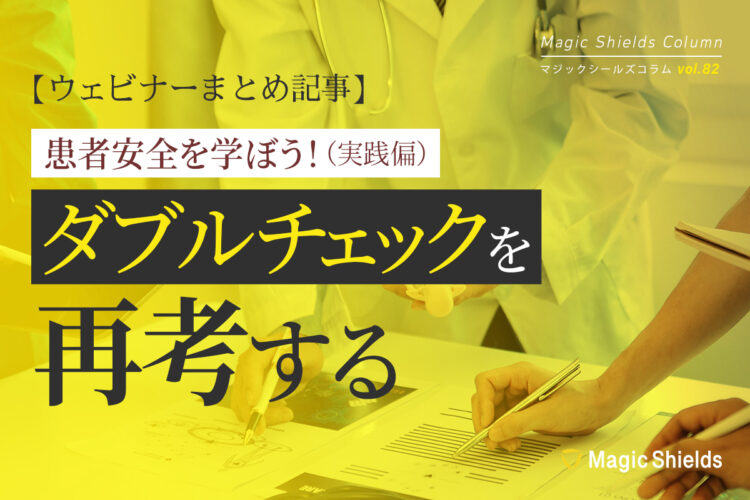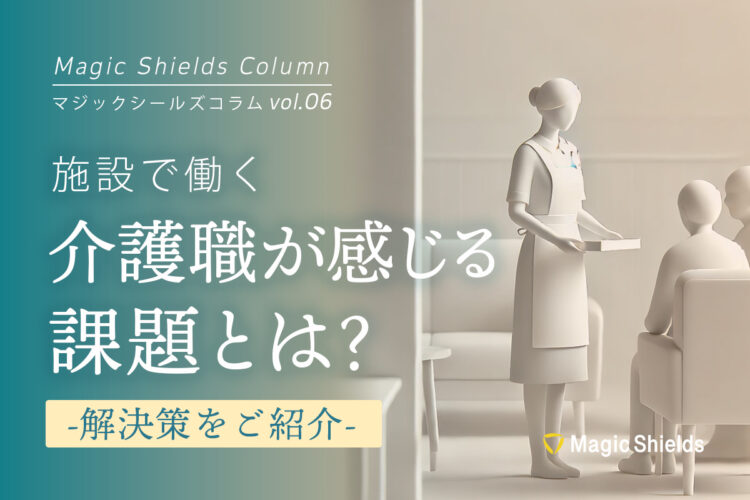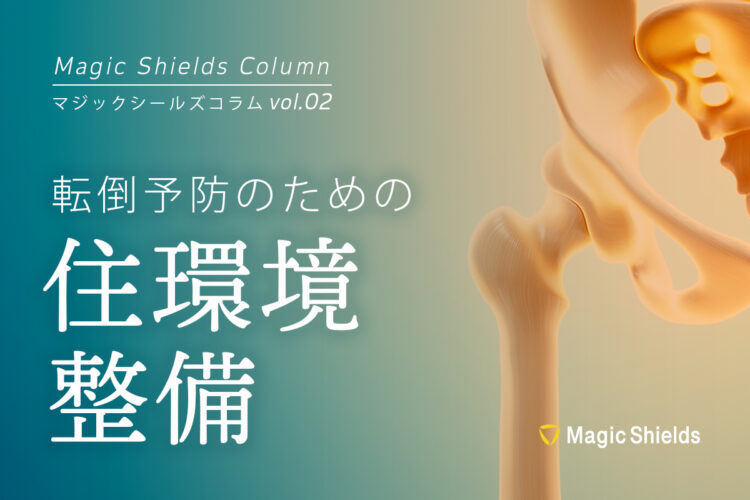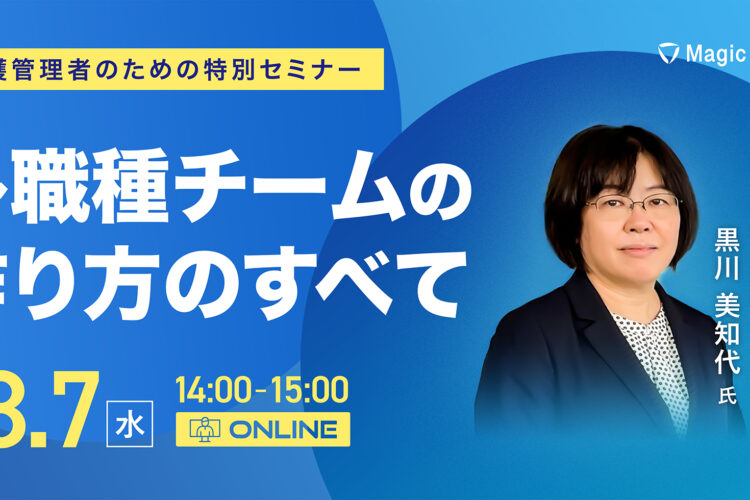目次
「医療機器の取り扱いに不安がある」「医療機器について後輩を指導する自信がない」と思っている人もいるのではないでしょうか。
今回のウェビナーでは、日本臨床工学技士会医療安全対策委員会の委員長である松田様に、現場に必要な医療機器の完全管理について講演いただきました。
臨床工学技士としての現場経験、教員として教育機関での経験、そして医療安全管理者としての立場から医療機器についてお話いただきましたので、その内容を簡単に解説していきます。
医療安全への考え方

ここからは、医療安全への考え方について解説していきます。
安全・安心できる医療のために
安全とは、危険がないこと、被害を受ける可能性がないことです。
そして、安全である状態とは、身体的に危険がないと信頼している状態で心も落ち着いている状態を指します。
安全は安心に限りなく近い状態です。
つまり、安全な医療の提供とは、言い換えれば安心できる医療の提供とも言い換えられます。
提供側の職員が安心して医療提供をし、患者様やご家族様も安心して安全な医療を受けられる状態が理想的です。
安心できる医療提供のためには、次の2つが特に大切なポイントになります。
- ・安全文化の醸成
- ・心理的安全性の構築
これらの考え方を大切にできると、安心・安全な医療提供へとつながります。
また、医療安全の考え方は、時代と共に変化してきました。
具体的には次のとおりです。
| 1999年以前 | 医療事故はあってはならないこととされ、個々の注意で防ぐことができるものと認識されていた |
| 2000年頃以降 | 医療事故は起こるものであるため、個人を決して責めないという風潮に変化してきました。システムやチームや組織全体のあり方や、環境(文化)考え方を改善しなければ防げないと認識されている |
最近では、医療事故は起こるものであるため、個人を責めるのではなく組織全体の在り方を見直す考え方に変わってきています。
つまり、チーム・組織全体でのヒューマンファインプレーが重要だということです。
ブロークンウィンドウ理論
ブロークンウィンドウ理論とは、アメリカの犯罪学者であるジョージ・ケリング博士とジョームズ・ウィルソン氏が提唱した理論で、1枚の割れた窓ガラスをそのまま放置しておくと、他の窓も割られていき、街全体が荒廃してしまうということです。
軽微な犯罪やルール違反なども放置するとモラルがどんどん低下していき、大きな事故に繋がってしまう可能性があるというのは、医療現場にも言えることではないでしょうか。
医療安全を守るためには、軽微な倫理やルールへの違和感などにも目を向け、組織全体の改善を促していくことが大切であるともいえます。
安全文化とは
安全文化とは、具体的に以下のような文化から成り立ちます。
- ・報告する文化
- ・公正な文化
- ・柔軟な文化
- ・学習する文化
また、もっとわかりやすく表現すると以下になります。
- ・責めない文化
- ・謙虚な文化
- ・自律の文化
- ・助け合える文化
- ・空気を読める文化
目に見えない文化を大切にしていくことが重要になります。
つまり、協力するということがチーム医療でとても大切であるということです。
「助けること」や「助けてもらうこと」を意識し、協力できる関係を構築していきましょう。
医療安全のためのそれぞれの役割

ここからは、医療安全のために配置されたそれぞれの職種や責任者の役割について紹介していきます。
医療安全のための各責任者
各病院では医療安全のために、さまざまな責任者が設置されています。
- ・医療安全管理者
- ・医療品安全管理責任者(薬剤師等)
- ・医療機器安全管理責任者(臨床工学技士等)
- ・医療放射線安全管理責任者(診療放射線技師等)
- ・院内感染管理者
医療安全のためのさまざまな責任者がいますが、それぞれ違う職種が担当しています。
そのため、各専門家の連携が常に必要になります。
臨床工学技士の役割
臨床工学技士とは、生命維持管理装置の操作・保守・点検をする職種です。
それぞれの領域での医療機器の安全使用及び院内全ての医療機器の安全管理を担います。
しかし、医療安全に関しては、まだ未熟な部分があると思っています。
医療機器管理業務は次のとおりです。
- ・購入前の選定から廃棄までのトータルマネジメント
- ・使用前・使用中・使用後の点検や清掃
- ・使用状況の把握
- ・定期点検・メンテナンス・確実な点検計画
- ・付属部品を含めた管理
- ・教育・研修・使用方法指導
- ・故障・不具合対応
- ・各種情報の管理と発信
- ・安全使用のための日々の改善
臨床工学技士の業務特性からも、医療安全管理に適している立場になります。
医療機器安全管理とは
医療機器はこれまで深く考えず「使えているから大丈夫」と使用されてきた現状がありました。
しかし、ようやく安全に使用しましょうという考えに変わってきたのです。
医療機器を安全に使用するために、取扱説明書や添付文書は厳守です。
汚れただけでも不具合は起こります。
例えば、輸血ポンプ点滴プローブや輸血ポンプ閉塞検出部は汚れで固まり不具合が起こります。
モニタECGリード線やシリンジポンプ流量設定ダイアルも同様です。
つまり大前提として、清掃が大切になります。
汚れた状態では、点検すらできません。
安全管理のための体制を確保しなければならない医療機器とは、病院等が管理する医療機器の全てだけではなく、患者の自宅、その他病院等以外の場所で使用される医療機器及び、病院等に対し、貸し出された医療機器も含まれます。
しかし、患者様の自宅で使用している医療機器まで管理が及ばないのが現状です。
こちらの体制整備も今後大切になるとされています。
医療機器安全管理責任者
医療安全管理者の業務は、組織全体を俯瞰した安全管理を行う人のことです。
そして、これらをとおし、安全管理体制を組織内に根付かせ機能させることで医療機関における安全文化の醸成を促進します。
参照:厚生労働省「医療安全管理者の業務指針」
また、医療機器安全管理責任者は、臨床工学技士が担当することが適切と言われています。
しかし、医療機器の管理については全病院内での各部署の協力が必要です。
なぜなら、全ての医療機器を一人の医療機器安全管理責任者や一つの部署で管理することは絶対に不可能だからです。
専門の各部門で管理していくことが理想的です。
(MEセンター、放射線科、検査科、看護部、各科、事務部)
そのうえで、なにかあれば、医療機器安全管理責任者へ報告をしましょう。
また、無駄なチームや会議は、無駄な時間の消費です。
日常業務から無駄を省き、不必要なチームの解散などを検討しましょう。
医療機器に係わる安全管理のための体制の確保
医療機器に係わる完全管理のための体制確保として、最低限抑えておきたいものは次の4つです。
- 医療機器完全管理責任者の配置
- 医療機器の安全使用のための研修会(勉強会)の実施
- 点検計画の策定・点検の実施
- 医療機器の安全使用のための情報収集
これらは、安全管理の体制を確保するうえで、大切なこととなります。
網羅できるように、院内で工夫していけることが理想的です。
安全な医療機器使用のために

ここからは、安全に医療機器を使用するために必要なことを解説していきます。
医療安全管理に必要なこと
添付文書に従っていれば、インシデントは起きにくいです。
医療機器を使用する際には、取扱説明書で正式な使用方法を必ず確認しましょう。
テクニカルアラームは、添付文書に従っていれば激減する可能性が高いです。
また、医療機器において使用環境の確認は、重要なポイントになります。
例えば、人工呼吸器を使用している患者様の場合、機器に異変があっても看護師がすぐに気づけない可能性もあります。
生命維持管理装置を使用していながら、誰かがすぐに行けない環境の中で患者様は過ごします。
それらを踏まえたうえでも、医療機器安全管理に必要なことは、使用状況・環境の把握です。
医療機器の確認は、保守点検だけすれば安全ということではありません。
どう使用されているかの環境確認が重要です。
臨床工学技士がいない病院について
臨床工学技士は、日本でまだまだ数少ない職種です。
実は、全体の38%程度しか在籍しておらず、まだまだ在籍しない病院が多いのも現状です。
臨床工学技士が在籍していない場合は、医療機器の安全管理のために、近隣の病院同士で助け合うなど他職種団体との連携が重要になります。
臨床工学技士がいない病院・施設においての完全管理のためにおすすめの書籍は以下です。
- ・医療機器安全管理指針
- ・医療機器を介した感染予防のための指針
- ・医療機器安全管理業務における医療ガス及び電波の利用に関する指針
これらの書籍にて、繰り返されている医療事故をまずは把握しましょう。
医療事故の事例については、時代が変わっても本質的な内容は実は変わっていないことも多いからです。
過去の事故事例を知り、自施設では絶対に起こさないという強い思いが大切です。
医療安全管理者が知るだけでなく、使用者・チームメンバーへの迅速な共有がカギとなります。
全ての医療機器に共通するやるべきことは、次のとおりです。
- ・綺麗に使用する
- ・安全に使用する
- ・適正に使用する
- ・正しい目的でルールを守り使用する
- ・不明点は即確認する
- ・確実な保守・点検・管理を行う
- ・使用者への教育を徹底する
- ・あらゆる情報収集をする
特に大切なことは、取扱説明書や添付文書の絶対順守と清掃です。
これを厳守するだけでインシデントリスクは下がります。
これらを守っていれば、医療機器の安全使用につながります。
まとめ

医療安全管理者としては、何よりも安全を優先することが大切です。
現場(使用者)の要望にも応えながら、使用中の点検や使用状況の確認を徹底するようにしていきましょう。
株式会社Magic Shieldsでは、今後もさまざまなウェビナーを開催していきます。
今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。