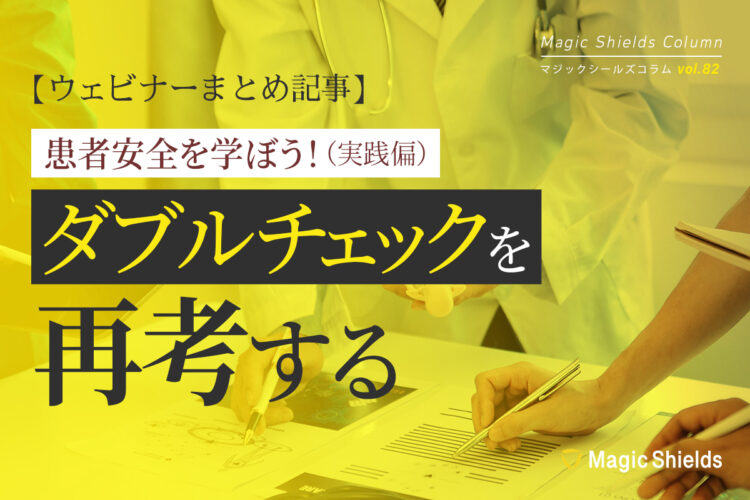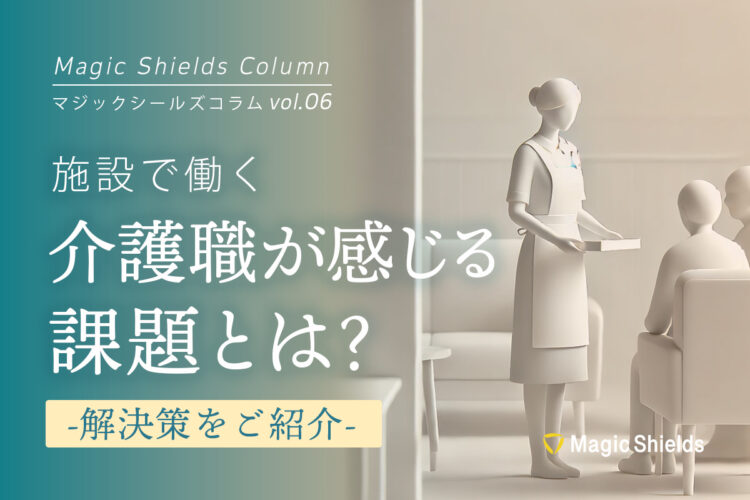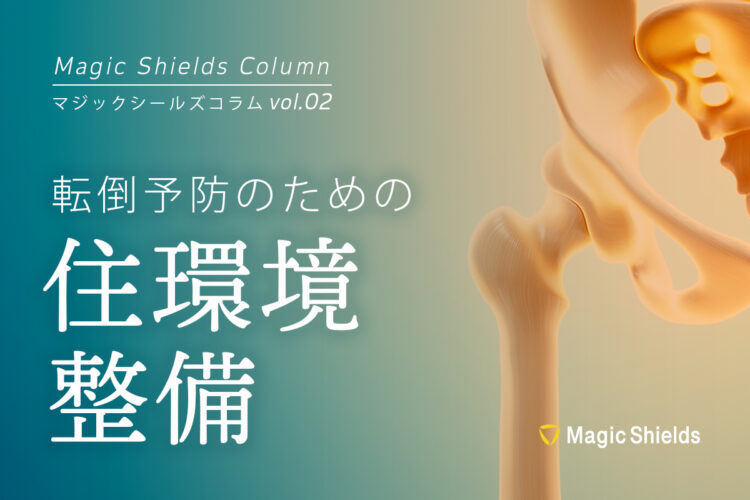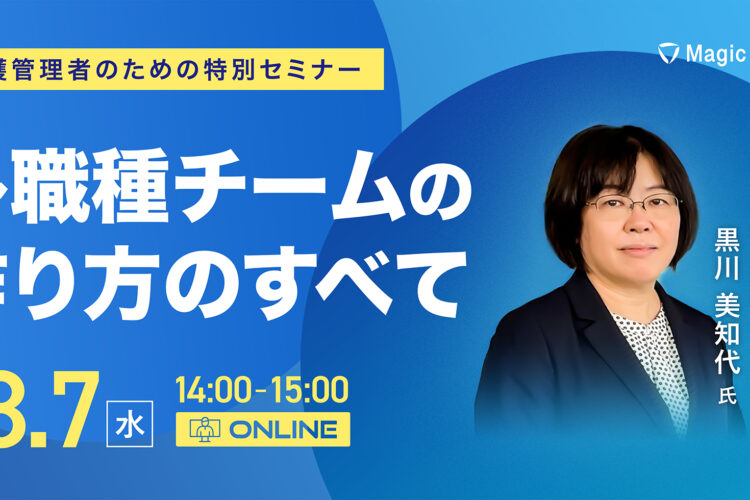目次
「日頃の業務の中で、ミスをしてしまわないか常に心配」、または「看護管理者として、安全な医療の提供のためにヒューマンエラーを減らしたい」と思っている人もいるのではないでしょうか。
また、医療安全管理者として、院内の医療安全のレベルを上げていきたいと感じている人もいるでしょう。
今年度の医療の質・安全学会学術集会大会長の松村先生に、患者安全についての講義を2回(基礎編・実践編)にわたりお話いただきました。
今回の基礎編では、患者安全を考える上で非常に重要な『ヒューマンエラー』について講義していただきましたので、その内容を紹介していきます。
ヒューマンエラーと確認の重要性

ここからは、ヒューマンエラーの発生と確認の重要性について解説していきます。
ヒューマンエラーの分類
ヒューマンエラーの分類(J.Reason)は、不安全行動として意図せぬ行動と意図した行動にわかれます。
- 【不安全行動】意図せぬ行動:スリップ、ラプス
- 【不安全行動】意図した行動:ミステイク、規約違反
ここからは、基本的なエラー対応について具体的に解説していきます。
スリップ:行動段階の誤り
スリップとは、行動段階の誤りのヒューマンエラーを指します。
例えば、エレベータの開閉ボタンの押し間違えなどです。
スリップ対策としては、人間工学的な知識を使うことが大切です。
間違えやすい操作に対しては、わかりやすいデザインを採用するなどの対処法がよいでしょう。
ラプス:失念エラー、記憶の誤り
ラプスは、記憶段階の誤りを指します。
忘れてしまって失敗するヒューマンエラーのことです。
例えば、グリルで魚を焼いていることを忘れて焦がすなどです。
ラプスへの対策は、事故になる前に対応できるシステムを導入することが重要になります。
上記のグリルのラプス事例に対しては、タイマーをセットできるグリルに買い替えるなどの対処法が有効です。
ミステイク:思い込みのエラー
ミステイクは、判断が最初から誤っていてそれに基づいて行動していた思い込みのエラーのことです。
医療現場では、診察ミスが該当します。
日常生活に例えると、「アボカドしか知らなければ、ワサビをアボカドだと思う」などのエラーもこれにあたります。
ミステイクの対策としては、事例の共有や知識を整理することが大切です。
また、教訓を共有し、ミスを語り継ぐことを意識していきましょう。
規約違反:文化の問題
規約違反は、面倒などの理由で決まっていたことをしないことです。
例えば、政治家のキックバック・裏金問題などがそれに該当します。
ルールを破ったほうが「得」になるために、このような行為をしてしまいます。
規約違反は文化の問題でもあり、個人の教育等だけでは改善できない可能性も。
対策としては、ルールの意味を理解したり、ルールを守る人をリスペクトしたりすることが大切でしょう。
確認とは何か
医療現場では、次の2種類の確認方策を意識・区別します。
- ・妥当性チェック
- ・照合型チェック
それぞれのチェックの種類を意識したエラー対策が大切です。
2つの種類について、次の表にまとめました。
| 確認方策の種類 | 特徴 | 注意点 | 該当する確認内容の例 |
| 妥当性チェック | 知識・ルールに基づいて正しい(合理的)であることを判断 | ・自分の能力の限界を知る・判断困難であれば助けを求め、複数人で妥当性を検討する | 診断 |
| 照合型チェック | 正しい(確定情報)と照らし合わせ、エラーの有無を確認 | ・誰にでもできるけど確定情報(正しい手元情報)が必須・記憶に基づかない・自分が責任を持つ | 患者の確認 |
患者の確認は、常に照合型チェックが必要です。
国際標準の患者確認方策としては、少なくとも2点の独立した識別子を用いて照合が必要とされています。
例えば、病院の患者確認でよく使われているのが、名前と生年月日などだと思います。
患者確認には、こうした正確な情報の照合を行うことが必須です。
患者確認が患者安全上重要である理由
患者確認が重要である理由は次のとおりです。
- ・誤った患者への手術・投薬をなくしたい
- ・誤った情報に基づく誤った判断をなくしたい
- ・繊細なヒューマンエラーによる悲惨な結果をなくしたい
- ・患者確認の能力・文化は、他の患者完全活動に応用できる
このように、患者確認が必要な理由を明確に認識しておくことも大切です。
また、ヒューマンエラーによる誤薬が死亡につながった事例もあります。
誤薬の事例では、患者に名乗ってもらい薬を渡したが、持っていた薬自体が間違っていたために誤薬してしまい患者が約3週間後に死亡してしまったということがありました。
この事例からも、患者に名乗ってもらうことの意味を理解することが大切です。
また、実効性のある患者確認を定着させるためにできることを考えておきましょう。
そして、名乗ることができない場面での患者確認の方策や自分だったらどうするかという視点でも事例について考えることがエラー防止につながります。
患者安全インシデントとレポート

ここからは、患者安全インシデントとそのレポートの記載ポイントについて解説していきます。
患者安全インシデントとは
患者安全インシデントとは、通常医療行為からあらゆる逸脱のうち患者に害を及ぼした、もしくは害のリスクがあったものをいいます。
また、患者安全インシデントは、まず患者に実施されたものかそうでないかで以下のようにわかれます。
【患者に実施された】
- 有害なインシデント
- 無害なインシデント
【患者に実施されてない】
- ニアミス
患者に実施された処置等でインシデントが発生しそれが患者にとって有害であった場合、予防可能なものであったかそうでなかったかの判断も重要になります。
予防可能であったものは、対策を講じていきます。
インシデントレポートの目的
インシデントレポートの目的は誘発した背景を知り業務工程を改善することにあります。
決して個人の責任を問うものではないということは、忘れてはなりません。
そして、このような考え方は安全文化の醸成において重要なことです。
報告文化は、「患者の安全を第一」だとする組織の成長に必要だからです。
インシデント発生した際に、報告して検討することで組織としての成長にもつながります。
報告文化と学習文化
報告文化と学習文化を構築していくためには、次の3つが大切です。
- ・失敗を恥ずかしいものではないとする
- ・疑問を話してくれた人に感謝を表す
- ・それを前向きな経験にすることを考える
報告を推奨する文化を育てていきましょう。
インシデントレポートの記載での記載項目
医療安全管理者のよくある悩みは、次のとおりです。
- ・レポートを読んでも何かどうしてこうなったのかわからない
- ・改善につながらない
これらの悩みの原因は、「分析に必要な内容」を意識して書かれていないことにあります。
レポートは、事故分析に必要なことへの記載を意識し、反省文にしないようにしましょう。
インシデントレポートで記載する項目は、主に次のとおりです。
【分析に必要な4つの情報】
①予定した行動(意図したこと)
②今回の行動(実施したこと)
③背景要因として考えられるもの
④患者の害の有無
分析に必要な4つの情報を整理したうえで、インシデントレポートを記載することが大切です。
レポートの記入例
ここからは、インシデントレポートについて、誤配薬の場合の例文を紹介していきます。
特に今回の行動や背景要因を明確にさせながら、記載していくことがポイントとなります。
①予定した行動(意図したこと)
患者に氏名を名乗っていただき、準備薬の患者氏名と照合し、患者に服用させる
②今回の行動(実施したこと)
患者に氏名を名乗ってもらったが、準備薬の患者氏名と照合せず、患者に別患者の薬を服用させた
③背景要因
業務が重なって心理的に焦りがあった
④患者の害の有無
2時間後に患者の血圧が低下し、ショックバイタルとなりICUに入室
改善策の方向性の例
インシデントレポートで状況や背景などを記載をしたら、次は改善策も考えていきたいところです。
そこで、改善策の方向性例について、以下2つを紹介していきます。
①患者の害を最小化することを目的とする
・名乗ることもでき、薬がいつも少ない指摘できる患者様であれば患者様に薬袋ごと渡して、自己管理してもらう
・確認を機械にさせる(リストバンドのバーコードの活用等)
②背景要因への介入
・能力の発揮を妨げている要因があることを認識して要因を取り除くか要因があっても能力が発揮できるようにする
改善策は「何を軸とするか」の考え方が大切になります。
背景要因への介入や害を最小限にする方法を起案していけたら、理想的です。
ヒューマン・ファクターズに基づいたSHELモデル
ヒューマン・ファクターズとは、間違いを起こしやすい人間がツール・機会・システム・業務・責務・環境などに適応し、安全で快適な使用ができるようにするためにはどのようにしたらよいかを研究する学問のことです。
ヒューマン・ファクターズに基づいたSHELモデルは、ヒューマンエラーの誘発に関わる当事者と周囲の要因です。
誘発要因とは、具体的に次の5つを指します。
- ・マニュアル、教育方法
- ・機器・器具、設備
- ・作業環境
- ・当事者
- ・周囲スタッフ
人は、完璧ではありません。
人間の行動、能力には限界があることを前提とし、人とシステムの複雑な関係に目を向けるという考え方になります。
また、当事者がエラーを発生させる素地となる要因は、空腹・怒り・遅れ・疲労です。
これらを感じたときには、一度立ち止まり周囲に頼ることができる環境も大切です。
まとめ

患者安全のために、ヒューマンエラーの分類を学び、医療安全のために自分ができることを考えていくことが大切です。
また、インシデント報告とは決して誰かを責めるためのものではなく、報告文化や学習文化においては欠かせないものであるということを再認識しましょう。
株式会社Magic Shieldsでは、今後もさまざまなウェビナーを開催していきます。
今回のウェビナーついて、もっと詳しく知りたい方はぜひアーカイブ動画をご覧ください。